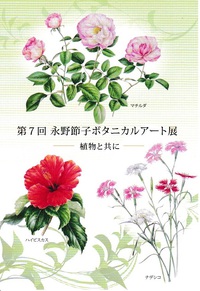会員様から
「闘論!高橋コレクションをめぐって、がらがらぽん!」
高橋龍太郎×木下直之×川谷承子の三人の討論会・・おっと・・ちらしには闘論会と書いてあったので、これは行かねばと県立美術館に向かった。県美ギャラリーでは絵手紙や写真展・講堂ではピアノの発表会があって、駐車にちょっと苦労してたどり着いた。
エントランスでの闘論会は珍しいと思いつつ新鮮な感じがした。
高橋氏がこういう展覧会を始めて18回目。名古屋の美術館では名古屋出身の作家の作品を選べたのに、ここ静岡では出身の作家が少ないので、今回のような静岡県立美術館コレクションと高橋氏のコレクションの関係性を探るテーマにしたとの事。それだけでも残念。
「いないないばあ」「おとなこども」「なぞらえ」のテーマの絞り方はいいとしても、言葉の意味で全体の展覧会を想像するのは私には難しかった。ので・・頭使う?このタイトルはやりたかったんだねと私自身を納得させた。
たとえば「いないないばあのくくりは負け犬根性・不在の感覚が日本人の美学の基本に立つ。」「おとなこどもでは、ネオテニーと言う言葉があり、生物学的用語だが成体になるのに、赤ちゃんの形のまま大人になる。日本は未成熟なのかな。」と高橋氏は話す。鹿児島霧島アートの森では「ネオテニー・ジャパン====高橋コレクション」展がすでに2010には行われているので、高橋氏の未成熟なのかなというネオテニィーの作品をその意識で集めればしっかりメッセージになってしまうほどのコレクションの質?と量なのか。
静岡県立美術館は1986年に開館。1994年ロダン館が開館。2001年までは現代作品の収集が継続的に行われていたが、その後は減っていたらしい。高橋氏はその状況の中で逆に作品を買っていく。
「山口晃の展覧会で、展示してある作品全部買いたい。と言うと画廊の返事では全部は・・と躊躇した」とも話す。高橋氏の大人買いをしたい衝動の話。「アートを含めたものが好き。自分の人生を最初から蘇らせてくれる作品。30年の負け戦。自分が失ったものをコレクションすることで、オセロのように自分の人生をひっくり返したかった。」とも話す。「盗んでみたいと思うほどの絵と対峙する。だから手に入れてしまえばもう見ない」
「高橋コレクションは自分一人のものなのに、もう一人のものじゃない。」「今の日本だけが、世界で現代美術を括弧でくくっているので、現代アートを括弧でくくらないようにもっていきたい」との言葉に闘う意思を感じた。全体では闘論にはなっていなかったが、高橋氏の話す言葉は、何十万と人が入る東京の展覧会に対する挑戦の言葉でもあるのだった。
こうした県立美術館という箱の中で展覧会をすることで、既存なものに取って代わるalternative的な新しさをちょっとは無理に納得させられる感じがした。悪いことではないが高橋氏のコレクターの本質を読み取れない部分があるのは自分の能力がないのかと感じてしまう。今回の県立美術館の展示にはもっと解かりやすいメッセージとか、風穴をあけて発信して欲しい。私も時代の流れの混沌も理解したいし、楽しく鑑賞したいしと色々考えた高橋氏の言葉だった。
高橋龍太郎×木下直之×川谷承子の三人の討論会・・おっと・・ちらしには闘論会と書いてあったので、これは行かねばと県立美術館に向かった。県美ギャラリーでは絵手紙や写真展・講堂ではピアノの発表会があって、駐車にちょっと苦労してたどり着いた。
エントランスでの闘論会は珍しいと思いつつ新鮮な感じがした。
高橋氏がこういう展覧会を始めて18回目。名古屋の美術館では名古屋出身の作家の作品を選べたのに、ここ静岡では出身の作家が少ないので、今回のような静岡県立美術館コレクションと高橋氏のコレクションの関係性を探るテーマにしたとの事。それだけでも残念。
「いないないばあ」「おとなこども」「なぞらえ」のテーマの絞り方はいいとしても、言葉の意味で全体の展覧会を想像するのは私には難しかった。ので・・頭使う?このタイトルはやりたかったんだねと私自身を納得させた。
たとえば「いないないばあのくくりは負け犬根性・不在の感覚が日本人の美学の基本に立つ。」「おとなこどもでは、ネオテニーと言う言葉があり、生物学的用語だが成体になるのに、赤ちゃんの形のまま大人になる。日本は未成熟なのかな。」と高橋氏は話す。鹿児島霧島アートの森では「ネオテニー・ジャパン====高橋コレクション」展がすでに2010には行われているので、高橋氏の未成熟なのかなというネオテニィーの作品をその意識で集めればしっかりメッセージになってしまうほどのコレクションの質?と量なのか。
静岡県立美術館は1986年に開館。1994年ロダン館が開館。2001年までは現代作品の収集が継続的に行われていたが、その後は減っていたらしい。高橋氏はその状況の中で逆に作品を買っていく。
「山口晃の展覧会で、展示してある作品全部買いたい。と言うと画廊の返事では全部は・・と躊躇した」とも話す。高橋氏の大人買いをしたい衝動の話。「アートを含めたものが好き。自分の人生を最初から蘇らせてくれる作品。30年の負け戦。自分が失ったものをコレクションすることで、オセロのように自分の人生をひっくり返したかった。」とも話す。「盗んでみたいと思うほどの絵と対峙する。だから手に入れてしまえばもう見ない」
「高橋コレクションは自分一人のものなのに、もう一人のものじゃない。」「今の日本だけが、世界で現代美術を括弧でくくっているので、現代アートを括弧でくくらないようにもっていきたい」との言葉に闘う意思を感じた。全体では闘論にはなっていなかったが、高橋氏の話す言葉は、何十万と人が入る東京の展覧会に対する挑戦の言葉でもあるのだった。
こうした県立美術館という箱の中で展覧会をすることで、既存なものに取って代わるalternative的な新しさをちょっとは無理に納得させられる感じがした。悪いことではないが高橋氏のコレクターの本質を読み取れない部分があるのは自分の能力がないのかと感じてしまう。今回の県立美術館の展示にはもっと解かりやすいメッセージとか、風穴をあけて発信して欲しい。私も時代の流れの混沌も理解したいし、楽しく鑑賞したいしと色々考えた高橋氏の言葉だった。