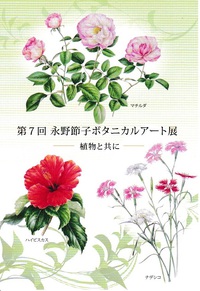会員様から
「無言館」戦没画学生慰霊美術館
新緑の木立に囲まれた少し勾配の道を歩くと、コンクリートの教会風の建物にたどり着いた。そこが無言館の入り口で、正面ではなく両サイドの木のドアを開けるとむき出しのままの絵の作品達が私に語りかけた。名前でまとめられた展示方法で、絵ばかりでなくケースの中には卒業証書や油絵の具の筆や家族への手紙もあった。
館主のメッセージが掛けてあった。タイトルは あなたを知らない だった。
遠い見知らぬ異国で死んだ 画学生よ 私ははあなたを知らない
知っているのは あなたが遺したたった一枚の絵だ 力強いメッセージ。読んだ瞬間涙が溢れた。
作品達の中に24歳で戦死した曽宮俊一さんの絵があった。静岡県立美術館に館蔵品がある曽宮一念の息子さんだ。父の曽宮さんは101才まで生きることができたが、戦後50年以上息子さんのことを話さなかった。
1987年に94歳の一念さんの自宅を「アトリエ訪問」取材助手として訪ねたことがある。エッセイストクラブ賞を受けた「海辺の溶岩」をはじめ随筆、詩歌、画集などを出版し「へなぶり雁わたる」の歌集の準備をしていて話題になっていた。すでに失明していてエスコートの娘夕見(ゆみ)さんと一緒に現れゆっくり肘掛椅子に座った。近くの窓から見える潤川のせせらぎだけが強く記憶に残っている。助手同行でも緊張した。それから曽宮一念氏の作品が好きになった。館蔵品の「毛無連峯」の作品が好きだ。
館内ではたくさんの自画像に目がいった。個性溢れる表現で心に残ったのは竹内秀太郎さんの自画像。大正4年生まれだった。
館主の窪島誠一郎氏の講演に10年程前参加したことがある。藤枝の文学館仲間で企画したのだ。最後には大広間で座って一緒にご飯を食べた。彫りの深い顔にかかる髪の毛がふわふわと揺れて掻き揚げるしぐさが記憶の中に浮かぶ。声をストレートに揺るぎなく発する人だった。
在館していたらと思い、受付のお嬢さんに伺った。東京から少しの期間お手伝いに来ている窪島さんの娘さんだった。「今年3月に閉館したばかりのデッサン館で原稿執筆中」とのことで残念ながらお会いできなかった。出口にコーヒータイムの小さな空間があり「感想文ノート」に沢山のメッセージが書かれていた。窓外のやわらかい緑を見ながら私もノートに沢山書いた。最後に「せめて握手をしたかったです」と書いた。お嬢さんが「必ず伝えます。喜ぶと思いますよ」と言ってくださった。
第二展示館「傷ついた画布のドーム オリーブの図書館」に向かった。分厚い画集達が天井まで届く本棚の中で整然と並んでいる広い空間だった。図書館では1万5千冊程(蔵書は4万5千冊以上)を楽しめる空間でもあった。父である水上勉氏から譲り受けた本もあるということだった。
「無言館」の建設は満州に出征して罹病のため生還した画家・野見山暁治氏の戦死した仲間たちへの鎮魂の思いから出発した事業で、窪島さんは一緒に収集を手伝っていたことは有名である。「無言」の意味は沢山ある。無言でいることは、強い思いを内包している。窪島氏の無言の意志。無くなった人達の無言の遺志。そして生きてここにたどり着いた私の無言の意思・・。窪島氏は「無言館」の存在を守る天才だ。

新緑の木立に囲まれた少し勾配の道を歩くと、コンクリートの教会風の建物にたどり着いた。そこが無言館の入り口で、正面ではなく両サイドの木のドアを開けるとむき出しのままの絵の作品達が私に語りかけた。名前でまとめられた展示方法で、絵ばかりでなくケースの中には卒業証書や油絵の具の筆や家族への手紙もあった。
館主のメッセージが掛けてあった。タイトルは あなたを知らない だった。
遠い見知らぬ異国で死んだ 画学生よ 私ははあなたを知らない
知っているのは あなたが遺したたった一枚の絵だ 力強いメッセージ。読んだ瞬間涙が溢れた。
作品達の中に24歳で戦死した曽宮俊一さんの絵があった。静岡県立美術館に館蔵品がある曽宮一念の息子さんだ。父の曽宮さんは101才まで生きることができたが、戦後50年以上息子さんのことを話さなかった。
1987年に94歳の一念さんの自宅を「アトリエ訪問」取材助手として訪ねたことがある。エッセイストクラブ賞を受けた「海辺の溶岩」をはじめ随筆、詩歌、画集などを出版し「へなぶり雁わたる」の歌集の準備をしていて話題になっていた。すでに失明していてエスコートの娘夕見(ゆみ)さんと一緒に現れゆっくり肘掛椅子に座った。近くの窓から見える潤川のせせらぎだけが強く記憶に残っている。助手同行でも緊張した。それから曽宮一念氏の作品が好きになった。館蔵品の「毛無連峯」の作品が好きだ。
館内ではたくさんの自画像に目がいった。個性溢れる表現で心に残ったのは竹内秀太郎さんの自画像。大正4年生まれだった。
館主の窪島誠一郎氏の講演に10年程前参加したことがある。藤枝の文学館仲間で企画したのだ。最後には大広間で座って一緒にご飯を食べた。彫りの深い顔にかかる髪の毛がふわふわと揺れて掻き揚げるしぐさが記憶の中に浮かぶ。声をストレートに揺るぎなく発する人だった。
在館していたらと思い、受付のお嬢さんに伺った。東京から少しの期間お手伝いに来ている窪島さんの娘さんだった。「今年3月に閉館したばかりのデッサン館で原稿執筆中」とのことで残念ながらお会いできなかった。出口にコーヒータイムの小さな空間があり「感想文ノート」に沢山のメッセージが書かれていた。窓外のやわらかい緑を見ながら私もノートに沢山書いた。最後に「せめて握手をしたかったです」と書いた。お嬢さんが「必ず伝えます。喜ぶと思いますよ」と言ってくださった。
第二展示館「傷ついた画布のドーム オリーブの図書館」に向かった。分厚い画集達が天井まで届く本棚の中で整然と並んでいる広い空間だった。図書館では1万5千冊程(蔵書は4万5千冊以上)を楽しめる空間でもあった。父である水上勉氏から譲り受けた本もあるということだった。
「無言館」の建設は満州に出征して罹病のため生還した画家・野見山暁治氏の戦死した仲間たちへの鎮魂の思いから出発した事業で、窪島さんは一緒に収集を手伝っていたことは有名である。「無言」の意味は沢山ある。無言でいることは、強い思いを内包している。窪島氏の無言の意志。無くなった人達の無言の遺志。そして生きてここにたどり着いた私の無言の意思・・。窪島氏は「無言館」の存在を守る天才だ。