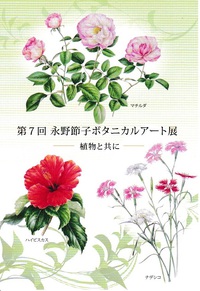会員様から
芸術は楽しい!! 静岡県文化プログラムスペシャルトーク2
清水華澄+しりあがり寿&宮城聡
静岡芸術劇場(グランシップ内)
一部・いきなりオペラ歌手の清水華澄さんの歌声で始まった。 ビゼーの『カルメン』 アルマ・マーラーの『5つの歌曲』 ストラビンスキーの『エディプス王』 マスカーニ作曲『カブァレリア・ルスティカーナ』の中の一部。ミニ・リサイタルだった。
ちらしでは ~オペラ歌手と漫画家が語る舞台裏~となっていたので、リサイタルがあるという意識は無かった。オペラはそれぞれフランス語・ドイツ語・イタリア語・ラテン語で歌っていたらしい。私は音楽のリズムは好きだが、言葉がわからないのとオペラ通でも無かったので楽しく聴いていたわけではなかった。
16世紀にイタリアで生まれたオペラ。今は日本の歌い手も世界の劇場で活躍している。清水さんもその1人だと知った。
2部・続いて3人のトークがはじまった。SPACの監督宮城聡氏が「歌の意味は解からなかったので、訳を急いでプリントしてもらった」と話し始めた。
意味はわからなくても充分楽しめた。理由は歌う人の体の動きをしっかり見ていたから。それで理解できる。えー私にはそんな聴き方や見方をしたことなんて無かったのに・・。違うレベルで聞いていて楽しんでいたんだ。宮城さんが語った。「歌う人は自分の体が楽器」・・・私たちは誰でも体があるんだから、それぞれ個性的な楽器なんだから・・と理解していて、歌曲は言葉と身体とも言っていた。歌の言葉で体の動きが違う。それが理解できて楽しいらしい。そうなんだ!!
「何でオペラをつくっちゃうのか。人間だからつくっちゃう。人間を知るために。人間は何をするものなのか。時が過ぎると、芸術が残る。人間はすてた者じゃないと思えるために。」と宮城氏。オペラは、様々な芸術の要素・・音楽・演劇・美術・文学でお互いに魅力を発揮する総合的な芸術だ。宮城氏の率いる舞台芸術センターの立ち位置を理解することが少し出来た。
結局このトークでわかったのは、「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた文化プログラム。スポーツだけの祭典ではなく、文化・芸術振興や文化・芸術による地域社会対応を目指していくという取り組みをしていく」とアピールしていたのだ
日本語でオペラの林光(はやしひかる)氏の舞台を東京に何度も観にいったことがある。気軽で、意味もわかるので楽しめたが、宮城氏の言う「言葉と体」の話を聞いてしまうと、歴史のある各国のオペラを理解するのは、その国の言語が大切だと頭では理解した。だったら日本語で素敵なオペラをいろんな人につくってほしいなー。そしたら体の動きと言葉で自然に楽しめるのに・・。

清水華澄+しりあがり寿&宮城聡
静岡芸術劇場(グランシップ内)
一部・いきなりオペラ歌手の清水華澄さんの歌声で始まった。 ビゼーの『カルメン』 アルマ・マーラーの『5つの歌曲』 ストラビンスキーの『エディプス王』 マスカーニ作曲『カブァレリア・ルスティカーナ』の中の一部。ミニ・リサイタルだった。
ちらしでは ~オペラ歌手と漫画家が語る舞台裏~となっていたので、リサイタルがあるという意識は無かった。オペラはそれぞれフランス語・ドイツ語・イタリア語・ラテン語で歌っていたらしい。私は音楽のリズムは好きだが、言葉がわからないのとオペラ通でも無かったので楽しく聴いていたわけではなかった。
16世紀にイタリアで生まれたオペラ。今は日本の歌い手も世界の劇場で活躍している。清水さんもその1人だと知った。
2部・続いて3人のトークがはじまった。SPACの監督宮城聡氏が「歌の意味は解からなかったので、訳を急いでプリントしてもらった」と話し始めた。
意味はわからなくても充分楽しめた。理由は歌う人の体の動きをしっかり見ていたから。それで理解できる。えー私にはそんな聴き方や見方をしたことなんて無かったのに・・。違うレベルで聞いていて楽しんでいたんだ。宮城さんが語った。「歌う人は自分の体が楽器」・・・私たちは誰でも体があるんだから、それぞれ個性的な楽器なんだから・・と理解していて、歌曲は言葉と身体とも言っていた。歌の言葉で体の動きが違う。それが理解できて楽しいらしい。そうなんだ!!
「何でオペラをつくっちゃうのか。人間だからつくっちゃう。人間を知るために。人間は何をするものなのか。時が過ぎると、芸術が残る。人間はすてた者じゃないと思えるために。」と宮城氏。オペラは、様々な芸術の要素・・音楽・演劇・美術・文学でお互いに魅力を発揮する総合的な芸術だ。宮城氏の率いる舞台芸術センターの立ち位置を理解することが少し出来た。
結局このトークでわかったのは、「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた文化プログラム。スポーツだけの祭典ではなく、文化・芸術振興や文化・芸術による地域社会対応を目指していくという取り組みをしていく」とアピールしていたのだ
日本語でオペラの林光(はやしひかる)氏の舞台を東京に何度も観にいったことがある。気軽で、意味もわかるので楽しめたが、宮城氏の言う「言葉と体」の話を聞いてしまうと、歴史のある各国のオペラを理解するのは、その国の言語が大切だと頭では理解した。だったら日本語で素敵なオペラをいろんな人につくってほしいなー。そしたら体の動きと言葉で自然に楽しめるのに・・。