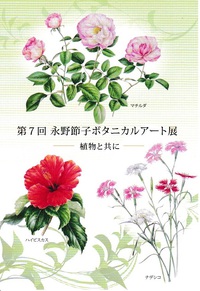会員様から
大人の遠足①
秩父銘仙館 大正ロマン・昭和モダン

旧埼玉県繊維工業試験場
私の裂織(さきおり)の材料になる古布に銘仙の着物がある。デザインが大胆で日本人なのにこんな元気さを持っているなんてと感動する明るい色彩で大好き。着物生地なのにどうしてこんな風に織れるのだろうとずっと不思議だった。柄の出し方がわからなかった。表も裏も同じ色なので確かに織っているのだ。大正時代や昭和初期に銘仙は規格外の繭を使って大人の普段着になっていた。当時の華やかな雰囲気を想像すると、弾けていた日常がみえる。イベントに「藤枝おんぱく」がある。その情報誌の表紙を飾る人は銘仙の着物を着ている。着物姿の表紙でも、今の着物でないのが素敵。
秩父が銘仙の産地と知って行ってみる事にした。たどり着く道筋は山に囲まれ稲作をする田んぼがほとんど無かった。養蚕が盛んだったと思える風景だった。2013年に国の伝統的工芸品に指定された。日常で着物を着る人が減り、素敵な銘仙柄も理解する人が減っている。
埼玉県繊維工業試験場が秩父銘仙の織体験が出来る場所だった。そこには銘仙が出来るまでの工程が何となくわかる様に展示して置かれていた。縦糸をたてる。固定してから横糸を粗く織りこむ。型紙で模様を刷り、次に横糸を一度ほぐしながら正式に織りこむ・・という工程だった。仮織りで模様を染めていたのだ。織ってから染めている発想をしていなかったのでびっくりだった。そして染めてからまたほぐして織り直す織り方を考え付いた人が凄いと納得できたと思う見学だった。秩父の町の色も心に残った。


秩父銘仙館 大正ロマン・昭和モダン
旧埼玉県繊維工業試験場
私の裂織(さきおり)の材料になる古布に銘仙の着物がある。デザインが大胆で日本人なのにこんな元気さを持っているなんてと感動する明るい色彩で大好き。着物生地なのにどうしてこんな風に織れるのだろうとずっと不思議だった。柄の出し方がわからなかった。表も裏も同じ色なので確かに織っているのだ。大正時代や昭和初期に銘仙は規格外の繭を使って大人の普段着になっていた。当時の華やかな雰囲気を想像すると、弾けていた日常がみえる。イベントに「藤枝おんぱく」がある。その情報誌の表紙を飾る人は銘仙の着物を着ている。着物姿の表紙でも、今の着物でないのが素敵。
秩父が銘仙の産地と知って行ってみる事にした。たどり着く道筋は山に囲まれ稲作をする田んぼがほとんど無かった。養蚕が盛んだったと思える風景だった。2013年に国の伝統的工芸品に指定された。日常で着物を着る人が減り、素敵な銘仙柄も理解する人が減っている。
埼玉県繊維工業試験場が秩父銘仙の織体験が出来る場所だった。そこには銘仙が出来るまでの工程が何となくわかる様に展示して置かれていた。縦糸をたてる。固定してから横糸を粗く織りこむ。型紙で模様を刷り、次に横糸を一度ほぐしながら正式に織りこむ・・という工程だった。仮織りで模様を染めていたのだ。織ってから染めている発想をしていなかったのでびっくりだった。そして染めてからまたほぐして織り直す織り方を考え付いた人が凄いと納得できたと思う見学だった。秩父の町の色も心に残った。