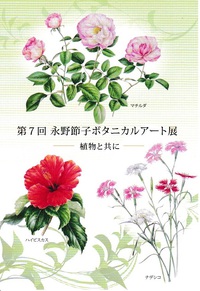会員様からの寄稿
コレクション

私の唯一のコレクション。作品でもある。骨董屋の片隅で見つけたボロボロの藍の刺し子と染めで座布団ほどの大きさの塊。紐で縛られていた。染めが藍の古布だったので手に入れた。家に帰ってまずそうっと紐を解いた。破れた半纏(はんてん)に包まれて下着の股引(ももひき)があらわれた。びっくりぽんだ。包んでまるめてあったが・・広げたときにそんなものが入っているなんて想像外だった。それからは洗濯機で洗いの作業に。勿論股引は捨てた。
半纏の形があったので、解いて平らな布にもどした。ばらばらになった布は重なった部分はまだ藍の色が濃かった。何故かその色に癒されていた。使い切った半纏には刺し子がしてあったが、それでも布の表面は溶け始めていた。布が溶けるなんて凄いことだ。刺し子の糸でかろうじて布に留まっているという状態だった。めげずに一枚のタペストリー風の敷物の形に挑戦した。外側に濃い色がくるように組み合わせていくことも難しかったが、まとめていくことが私の色彩感を磨く修行だと思った。藍の色彩の風化していく色が美しかったのだ。
古布だがここまでボロボロだと捨てられている。だが青森出身の田中忠三郎氏(1933~2013)がそうした古布を収集していた。浅草に「浅草アミューズミュージアム」が出来て展示されていると知った。生活のために破れたら縫って着て、また破れたら縫って着て・・そうして暮らした人達はそれを知られることを恥じていて・・田中氏が収集しなかったら残っていないものだったのだ。2009年に開館した私設美術館に岩手出身の森下さんと一緒に見に出かけてみた。こうした布は 寺山修二「田園に死す」・黒澤明「夢」という映画に使われたことも知った。また2013年春夏パリ・メンズコレクション/2014年春夏ニューヨークコレクション/2015年春夏コレクションで私の大好きなコム デ ギャルソンも展覧会をしていた。 ぼろ=BORO をモチーフにして。そして『BORO』展 も十和田市現代美術館でも2014に開かれていたことも知った。
藍の風化の色彩の美しさは芸術だと思う。布に魅かれる私がいる。藍は日本人の心に浸透しているので大事にしていきたい。2019年3月に閉館の噂がある。コレクションはどうなっちゃうんだろう。
私の唯一のコレクション。作品でもある。骨董屋の片隅で見つけたボロボロの藍の刺し子と染めで座布団ほどの大きさの塊。紐で縛られていた。染めが藍の古布だったので手に入れた。家に帰ってまずそうっと紐を解いた。破れた半纏(はんてん)に包まれて下着の股引(ももひき)があらわれた。びっくりぽんだ。包んでまるめてあったが・・広げたときにそんなものが入っているなんて想像外だった。それからは洗濯機で洗いの作業に。勿論股引は捨てた。
半纏の形があったので、解いて平らな布にもどした。ばらばらになった布は重なった部分はまだ藍の色が濃かった。何故かその色に癒されていた。使い切った半纏には刺し子がしてあったが、それでも布の表面は溶け始めていた。布が溶けるなんて凄いことだ。刺し子の糸でかろうじて布に留まっているという状態だった。めげずに一枚のタペストリー風の敷物の形に挑戦した。外側に濃い色がくるように組み合わせていくことも難しかったが、まとめていくことが私の色彩感を磨く修行だと思った。藍の色彩の風化していく色が美しかったのだ。
古布だがここまでボロボロだと捨てられている。だが青森出身の田中忠三郎氏(1933~2013)がそうした古布を収集していた。浅草に「浅草アミューズミュージアム」が出来て展示されていると知った。生活のために破れたら縫って着て、また破れたら縫って着て・・そうして暮らした人達はそれを知られることを恥じていて・・田中氏が収集しなかったら残っていないものだったのだ。2009年に開館した私設美術館に岩手出身の森下さんと一緒に見に出かけてみた。こうした布は 寺山修二「田園に死す」・黒澤明「夢」という映画に使われたことも知った。また2013年春夏パリ・メンズコレクション/2014年春夏ニューヨークコレクション/2015年春夏コレクションで私の大好きなコム デ ギャルソンも展覧会をしていた。 ぼろ=BORO をモチーフにして。そして『BORO』展 も十和田市現代美術館でも2014に開かれていたことも知った。
藍の風化の色彩の美しさは芸術だと思う。布に魅かれる私がいる。藍は日本人の心に浸透しているので大事にしていきたい。2019年3月に閉館の噂がある。コレクションはどうなっちゃうんだろう。