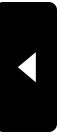「木下館長と行く伊豆仏教美術日帰り見学旅行」旅行代金について
チラシでは19,000円(会員)で募集していましたがgotoトラベルを利用して参加が決定しましたので、
12,000~13,000円(参加人数による)で行けることになりました。
まだ募集していますので検討中の方はぜひお申込みください!
お問い合わせは 静岡県立美術館友の会事務局 前田(火・木・金 9:00~16:00)
電話 054-264-0897
12,000~13,000円(参加人数による)で行けることになりました。
まだ募集していますので検討中の方はぜひお申込みください!
お問い合わせは 静岡県立美術館友の会事務局 前田(火・木・金 9:00~16:00)
電話 054-264-0897
「木下館長と行く伊豆仏教美術日帰り見学旅行」参加者募集中!
展覧会のお知らせ
1月に開催する友の会実技講座「日本画講座」の講師でもあります田宮話子氏の作品展が開催されています
2020年 10月9日(金)~10月18日(日)
AM11:00~PM5:00(会期中無休)
Gallery Futaba 静岡市葵区双葉町3-18
tel・fax 054-255-5200
2020年 10月9日(金)~10月18日(日)
AM11:00~PM5:00(会期中無休)
Gallery Futaba 静岡市葵区双葉町3-18
tel・fax 054-255-5200
展覧会のお知らせ
「展覧会のお知らせ」
11月に行う友の会実技講座「ボールペン画講座」の講師でもあるある渋谷たかし氏の展覧会です
「ボールペンで描く三保松原と欧州の世界遺産 渋谷たかしと仲間展」
三保文化創造センター「みほしるべ」
静岡市清水区三保1338-45(無料駐車場あり)
資料館電話054-340-2700
<展示会期>9月24日(木)13時~10月8日(木)16時30分
11月に行う友の会実技講座「ボールペン画講座」の講師でもあるある渋谷たかし氏の展覧会です
「ボールペンで描く三保松原と欧州の世界遺産 渋谷たかしと仲間展」
三保文化創造センター「みほしるべ」
静岡市清水区三保1338-45(無料駐車場あり)
資料館電話054-340-2700
<展示会期>9月24日(木)13時~10月8日(木)16時30分
友の会会員向けレクチャー
「富野由悠季の世界」レクチャー申し込み受付中
【日 時】 令和2年10月11日(日)11:00~ 40分程度(定員20名)
【集合場所】 美術館1階 講座室
【持 ち 物】 友の会会員証
【受 講 料】 無料
【締め 切り】 10月8日(木)
【申し込み方法】 事務局までお電話、FAXにてお申込み下さい。お申込みの際には
レクチャー希望・お名前・会員番号・電話番号をお知らせください。
なお、特別会員様のみ1名同伴可能です。
【申し込み先】 友の会事務局(火・木・金在館)TEL・FAX 054-264-0897
Eメール tomonokai@spmoa.shizuoka.shizuoka.jp
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の為展示室での解説を講座室に変更いたします。
友の会会員証に付いている入場引換券を使用して鑑賞される方は先にチケットに交換してから
1階講座室にお集まりください。時間に余裕をもってご来館下さい。

【日 時】 令和2年10月11日(日)11:00~ 40分程度(定員20名)
【集合場所】 美術館1階 講座室
【持 ち 物】 友の会会員証
【受 講 料】 無料
【締め 切り】 10月8日(木)
【申し込み方法】 事務局までお電話、FAXにてお申込み下さい。お申込みの際には
レクチャー希望・お名前・会員番号・電話番号をお知らせください。
なお、特別会員様のみ1名同伴可能です。
【申し込み先】 友の会事務局(火・木・金在館)TEL・FAX 054-264-0897
Eメール tomonokai@spmoa.shizuoka.shizuoka.jp
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の為展示室での解説を講座室に変更いたします。
友の会会員証に付いている入場引換券を使用して鑑賞される方は先にチケットに交換してから
1階講座室にお集まりください。時間に余裕をもってご来館下さい。
展覧会のお知らせ
友の会会報誌プロムナード アトリエ訪問のコーナーで取材した
風鈴丸氏の展覧会が開催されます
牧野宗則 風鈴丸
「ふたり展 -木版画の新たな展開-」
9月12日(土)~11月29日(日)
フェルケール博物館


風鈴丸氏の展覧会が開催されます
牧野宗則 風鈴丸
「ふたり展 -木版画の新たな展開-」
9月12日(土)~11月29日(日)
フェルケール博物館


会員様からの寄稿
『大自在』
論説委員長海野氏に会う

新聞の魅力を伝える連続地域講座「やいづ新聞の楽校」(全6回)の2回目の講座に初めて参加した。場所は焼津市栄町の静岡福祉大焼津駅前サテライトキャンパス。「学校」ではなく「楽校」となっていて、しかも静岡新聞のコラム担当の海野俊也論説委員長が今回講師だと知って申し込んだ。私はエッセイ風の文を楽しみに書いているので、学べることがあればという思いで参加してみた。
焼津は東北の地震津波以来、海近くに住む人達が次々に山側の藤枝に移り始めて、空洞化が続いている。キャンパスのある商店街も閑散としていて寂しかった。
『大自在』は地元紙静岡新聞の1面コラムで私は大好きなのだ。
「今5人で担当している。書きたいことが新鮮な話題でなければいけない。読み手の興味を引き付ける為に冒頭部分の文章に力を入れ最後にそのまとめをするパターンで書いている。忙しい中で書くほうが案外良い文になっている」と海野論説委員は言っていた。
コラムを面白がって書くことが大事らしい。なかなかのレベルで書き込んでいて、優れたコラムだと私は感心する。
今回は焼津地域の記事に特化して6種類コピーしてあった。それが教材だった。その中から1つを選んで読み込み、感想を書くという授業?だった。私は平成30年10/30日のを選んだ。そして私の感想は・・
『天皇皇后両陛下の人柄を、その記事の中に見つけて頷いた。当時私もテレビで「第21回全国豊かな海づくり大会」の様子を同時進行で見ていた。天皇陛下が傘をさしていらしたのに肩が濡れていたのを、ものともしないでセレモニーに参加していた姿に吃驚した記憶がある。記事の中に近くの人が雨具をあわてて脱いだと書かれていたが、参加した人々の心のさまがわかる行為で、もし同席していたら、同じようにしただろうと思う。あの時のテレビのシーンは忘れられない』
私のは読んだとき心に触れた理由を書いた。いつも私はどんなことを感じたか表現したいタイプなのだ。他の受講者男性は、記事から受けたものに連動した形で地元の他の過疎化の問題点を突っ込んでいた。なかなか説得力のある内容だった。
読み込む視点の違いのあることが面白かった。
論説委員長海野氏に会う
新聞の魅力を伝える連続地域講座「やいづ新聞の楽校」(全6回)の2回目の講座に初めて参加した。場所は焼津市栄町の静岡福祉大焼津駅前サテライトキャンパス。「学校」ではなく「楽校」となっていて、しかも静岡新聞のコラム担当の海野俊也論説委員長が今回講師だと知って申し込んだ。私はエッセイ風の文を楽しみに書いているので、学べることがあればという思いで参加してみた。
焼津は東北の地震津波以来、海近くに住む人達が次々に山側の藤枝に移り始めて、空洞化が続いている。キャンパスのある商店街も閑散としていて寂しかった。
『大自在』は地元紙静岡新聞の1面コラムで私は大好きなのだ。
「今5人で担当している。書きたいことが新鮮な話題でなければいけない。読み手の興味を引き付ける為に冒頭部分の文章に力を入れ最後にそのまとめをするパターンで書いている。忙しい中で書くほうが案外良い文になっている」と海野論説委員は言っていた。
コラムを面白がって書くことが大事らしい。なかなかのレベルで書き込んでいて、優れたコラムだと私は感心する。
今回は焼津地域の記事に特化して6種類コピーしてあった。それが教材だった。その中から1つを選んで読み込み、感想を書くという授業?だった。私は平成30年10/30日のを選んだ。そして私の感想は・・
『天皇皇后両陛下の人柄を、その記事の中に見つけて頷いた。当時私もテレビで「第21回全国豊かな海づくり大会」の様子を同時進行で見ていた。天皇陛下が傘をさしていらしたのに肩が濡れていたのを、ものともしないでセレモニーに参加していた姿に吃驚した記憶がある。記事の中に近くの人が雨具をあわてて脱いだと書かれていたが、参加した人々の心のさまがわかる行為で、もし同席していたら、同じようにしただろうと思う。あの時のテレビのシーンは忘れられない』
私のは読んだとき心に触れた理由を書いた。いつも私はどんなことを感じたか表現したいタイプなのだ。他の受講者男性は、記事から受けたものに連動した形で地元の他の過疎化の問題点を突っ込んでいた。なかなか説得力のある内容だった。
読み込む視点の違いのあることが面白かった。
友の会会員向けフロアレクチャー
会員様からの寄稿
歴史家磯田道史氏講演会

講演会『掛川で歴史を語る』に出かけた。会場は愛称「シオーネ」。潮+音をイメージした施設。初めて行く文化会館だったが田舎道をくねくねと曲がりながら走ると、本当にたどり着けるのか心配になる場所だった。
講師は国際日本文化研究センター准教授磯田氏で人気がある。講演チケットは600席が即完売。知り合いが申し込んだが完売だと言われて残念がっていた。
掛川の歴史と言えば戦国時代から江戸時代にかけて重要な役割を果たした難航不落の高天神城跡と江戸の華横須賀城跡。きっとその話だと密かに期待していた。
講演がはじまって開口一番「僕は高天神城にまだ登っていないんですよ」と磯田氏が恐縮して話しはじめた。高天神城址に登っていない・・素直だが、それで「掛川の歴史を語る」とタイトルをつけたのは詐欺?じゃないのかと私は思った。
話しの中心は南海トラフの津波の事だった。磯田氏が古文書を読み解き過去の津波の高さを推測した話だ。藤枝に住む私にも他人事ではない南海トラフ津波のことだ。揺れの時間は200秒。津波の高さは超巨大津波10㍍・巨大津波6㍍・大波3㍍。だから講演会のある場所は決して安心できる場所ではない。揺れがおさまったらすぐ高い山に走るのが大切だと力説していた。古文書を読み解いた磯田氏の津波の話はリアリティーがあった。
私が高天神城に登ったのは2009年11月。静岡県が国民文化祭担当県になった時だ。舞踏家田中泯が本丸跡で踊るという情報が入り出かけたのだ。山道を登っていると「ぞくぞくするね」と周りでしゃべっていた。徳川家康軍に殺された沢山の兵士の霊を感じる人がいるようだ。舞台はつい最近まで丈が1㍍程の雑草のように生えた細い竹を刈り取った地面の上。私達はその一角を取り囲んで座った。そして裸足の田中泯が伏せたり、のたうちまわったり踊りはじめた。戦いの兵の心を私達に伝えようとしているのか・・。踊る地面はまだ緑の色を残した3㍉程の小さな細い竹の切口がいたるところに生えている。着物が乱れた。裸足が竹の尖がったところで血だらけにならないか心配した。でも最後までそんな血も流れなく踊りきったことも魔法のようだった。息を呑んで生まれて始めて観た舞踏だった。忘れられない衝撃だ。
そんな高天神城跡の歴史を磯田氏の話で聞いてみたかった私だったのに。
講演会『掛川で歴史を語る』に出かけた。会場は愛称「シオーネ」。潮+音をイメージした施設。初めて行く文化会館だったが田舎道をくねくねと曲がりながら走ると、本当にたどり着けるのか心配になる場所だった。
講師は国際日本文化研究センター准教授磯田氏で人気がある。講演チケットは600席が即完売。知り合いが申し込んだが完売だと言われて残念がっていた。
掛川の歴史と言えば戦国時代から江戸時代にかけて重要な役割を果たした難航不落の高天神城跡と江戸の華横須賀城跡。きっとその話だと密かに期待していた。
講演がはじまって開口一番「僕は高天神城にまだ登っていないんですよ」と磯田氏が恐縮して話しはじめた。高天神城址に登っていない・・素直だが、それで「掛川の歴史を語る」とタイトルをつけたのは詐欺?じゃないのかと私は思った。
話しの中心は南海トラフの津波の事だった。磯田氏が古文書を読み解き過去の津波の高さを推測した話だ。藤枝に住む私にも他人事ではない南海トラフ津波のことだ。揺れの時間は200秒。津波の高さは超巨大津波10㍍・巨大津波6㍍・大波3㍍。だから講演会のある場所は決して安心できる場所ではない。揺れがおさまったらすぐ高い山に走るのが大切だと力説していた。古文書を読み解いた磯田氏の津波の話はリアリティーがあった。
私が高天神城に登ったのは2009年11月。静岡県が国民文化祭担当県になった時だ。舞踏家田中泯が本丸跡で踊るという情報が入り出かけたのだ。山道を登っていると「ぞくぞくするね」と周りでしゃべっていた。徳川家康軍に殺された沢山の兵士の霊を感じる人がいるようだ。舞台はつい最近まで丈が1㍍程の雑草のように生えた細い竹を刈り取った地面の上。私達はその一角を取り囲んで座った。そして裸足の田中泯が伏せたり、のたうちまわったり踊りはじめた。戦いの兵の心を私達に伝えようとしているのか・・。踊る地面はまだ緑の色を残した3㍉程の小さな細い竹の切口がいたるところに生えている。着物が乱れた。裸足が竹の尖がったところで血だらけにならないか心配した。でも最後までそんな血も流れなく踊りきったことも魔法のようだった。息を呑んで生まれて始めて観た舞踏だった。忘れられない衝撃だ。
そんな高天神城跡の歴史を磯田氏の話で聞いてみたかった私だったのに。
会員様からの寄稿
彫刻家 渡辺憲二

伊豆の国市在住の彫刻家渡辺憲二氏にお会いした。緑に囲まれた工房では天井から重い石を吊り上げるクレーンもあり、大理石・ブロンズ・テラコッタで制作された胸像頭像の彫刻作品が印象的だった。
憲二氏は15歳で洗礼を受けている。なりたい自分になると決心して生きていた人だった。「デッサンしている時は神様を感じる瞬間」と話すていねいな話しぶり。クリスチャンの目で観る美術。49歳で結婚し現在52歳。人との係わりの中で生きていることへの感謝の言葉が溢れていた。こんな風に感謝の言葉を話すアーティストに出会ったのははじめてで・・魂が生きていると感じて私は涙が流れた。
1996年自費留学してフィレンツェで彫刻。ウィーンで絵画、建築装飾を研究。パオリ大理石工房(ピエトラサンタ)。イーヴォ・カッチャ青銅鋳造所(ピエトラサンタ)。イーヴォ・ポーリテラコッタ工房(ピエトラサンタ)。ラスタンペリア銅版画工房(サンジミニャーノ)。フォルナイーニ・フレスコ画工房(ピサ)。こうした多くの工房での履歴は驚きだ。でもイタリアでは貸し工房があり、そこでの体験の履歴。工房に職人がいてそこでアーティストを支え作品が出来上がる。彫刻家に必要な星取り機も見せていただいた。原形の上に基準となる点を打ち、それと同じところに制作するものの上に点を付け無数の点を繋ぐことで複雑な形を再現する道具である。アーティストのオリジナルを模刻して作品にするとき、内側から外へ向かう力強い力まではなかなか写し取れない難しさがあるとのことだった。静岡県立美術館のロダン館にあるロダンの大理石の作品達も星取り機を用いて職人たちが模刻したものである。
ミラノの修道院宿舎に泊まった翌日、隣接する聖フランチェスコ教会のミサに参列しながら祭壇を眺めていたときのこと。光で壁に浮かびあがっ天使の羽影を見て・・聖なる影を意識した作品をこれからも制作していきたいと語った。
私は今まで静岡県と関係ある作家さん40人程にお会いし、県立美術館友の会会報誌「プロムナード アトリエ訪問」に16人の取材記事を書かせてもらっている。様々な発想やこだわりを伺って感銘を受けた体験は本当に宝物であると思う。渡辺憲二氏にも感謝だ。
別れ際工房の裏の柿の大木に若葉が瑞々しく美しく広がっていた。
伊豆の国市在住の彫刻家渡辺憲二氏にお会いした。緑に囲まれた工房では天井から重い石を吊り上げるクレーンもあり、大理石・ブロンズ・テラコッタで制作された胸像頭像の彫刻作品が印象的だった。
憲二氏は15歳で洗礼を受けている。なりたい自分になると決心して生きていた人だった。「デッサンしている時は神様を感じる瞬間」と話すていねいな話しぶり。クリスチャンの目で観る美術。49歳で結婚し現在52歳。人との係わりの中で生きていることへの感謝の言葉が溢れていた。こんな風に感謝の言葉を話すアーティストに出会ったのははじめてで・・魂が生きていると感じて私は涙が流れた。
1996年自費留学してフィレンツェで彫刻。ウィーンで絵画、建築装飾を研究。パオリ大理石工房(ピエトラサンタ)。イーヴォ・カッチャ青銅鋳造所(ピエトラサンタ)。イーヴォ・ポーリテラコッタ工房(ピエトラサンタ)。ラスタンペリア銅版画工房(サンジミニャーノ)。フォルナイーニ・フレスコ画工房(ピサ)。こうした多くの工房での履歴は驚きだ。でもイタリアでは貸し工房があり、そこでの体験の履歴。工房に職人がいてそこでアーティストを支え作品が出来上がる。彫刻家に必要な星取り機も見せていただいた。原形の上に基準となる点を打ち、それと同じところに制作するものの上に点を付け無数の点を繋ぐことで複雑な形を再現する道具である。アーティストのオリジナルを模刻して作品にするとき、内側から外へ向かう力強い力まではなかなか写し取れない難しさがあるとのことだった。静岡県立美術館のロダン館にあるロダンの大理石の作品達も星取り機を用いて職人たちが模刻したものである。
ミラノの修道院宿舎に泊まった翌日、隣接する聖フランチェスコ教会のミサに参列しながら祭壇を眺めていたときのこと。光で壁に浮かびあがっ天使の羽影を見て・・聖なる影を意識した作品をこれからも制作していきたいと語った。
私は今まで静岡県と関係ある作家さん40人程にお会いし、県立美術館友の会会報誌「プロムナード アトリエ訪問」に16人の取材記事を書かせてもらっている。様々な発想やこだわりを伺って感銘を受けた体験は本当に宝物であると思う。渡辺憲二氏にも感謝だ。
別れ際工房の裏の柿の大木に若葉が瑞々しく美しく広がっていた。

 054-264-0897(火・木・金在館)
054-264-0897(火・木・金在館)