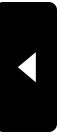5月12日(火)美術館再開いたします
新型コロナウィルス感染症の防止に向けた「緊急事態宣言」を受け4月18日(土)から
臨時休館していましたが5月12日(火)より再開することになりました。
友の会会員の皆様にはご迷惑おかけいたしました。
来館の際は感染症対策に十分注意してください。
ステイホームでなかなか外出できない日々が続いていますが、
GWの間オンライン通話で久しぶりに友達と話をしました。
家事をしながら食事をしながら自由にできてとても楽しく便利だなぁと感じました。
そんな今どきとはまた違い昨日別の友達から手紙も届きました。
友の会の会員方からも事務局にお手紙をいただくことがあります。
美術館の絵葉書や素敵な便せんでいただくことも多いです。
いただく私もこんな美術館に行ったんだなぁとか達筆な文字だなぁなんて
思いなが拝読しています。
時間があるこんな時だからこそできることって意外にありますよね。
臨時休館していましたが5月12日(火)より再開することになりました。
友の会会員の皆様にはご迷惑おかけいたしました。
来館の際は感染症対策に十分注意してください。
ステイホームでなかなか外出できない日々が続いていますが、
GWの間オンライン通話で久しぶりに友達と話をしました。
家事をしながら食事をしながら自由にできてとても楽しく便利だなぁと感じました。
そんな今どきとはまた違い昨日別の友達から手紙も届きました。
友の会の会員方からも事務局にお手紙をいただくことがあります。
美術館の絵葉書や素敵な便せんでいただくことも多いです。
いただく私もこんな美術館に行ったんだなぁとか達筆な文字だなぁなんて
思いなが拝読しています。
時間があるこんな時だからこそできることって意外にありますよね。
会員様からの寄稿
鷹を手に
放たれた鷹が近づいてくる。勿論覚悟はしている。でも皮の手袋をはめた右手はしっかり伸ばしていても思わず目をつぶってしまった。するとふんわりとやさしい重みを感じた。そっと目を開けると鷹が私の手にすでに乗っていた。眼光は鋭いが静かにしていた。鷹はそれまで怖いと思っていたが、なんだかこそばゆい嬉しさだった。
その体験をしたのは静岡県担当の国民文化祭の年で10年前のこと。地元のまつりのイベント広場で鷹匠を呼んでその技を見せる情報があった。絶対行きたいと思った。
イベント広場に着くと、鷹匠が高草山の方へ鷹を飛ばしていた。鷹は山の上を飛行し、しばらくすると鷹匠の元に戻ってきた。鷹の習性のことは知らないが獲物を見つける訓練かもと思った。それからイベントが始まったのだ。鷹匠同士が離れて向かい合い、一人は餌の肉を隠し持ち、手袋をした手を横に出していた。赤い色の肉が私の目にもはっきり見えた。もう一人が鷹を放つ。高く飛ぶと思っていたのにすーっと低く飛んで相手の鷹匠に一直線だった。餌は鷹がついばんでいた。
江戸時代の通信使は鷹を徳川への贈り物として50居(もと・・鷹を数える単位)持参している。途中で死亡することも珍しくなかったので、予備で多く連れてきたのだ。1居につき1日に鶉3羽、雀12羽、鳩大1羽半小2羽の食事。
家康は鷹が好きで駿府公園に鷹を手にしている銅像があり、公園の近くに鷹匠という地名も残っている。家康は天下統一を成し遂げた後、鷹の売買を禁止し、鷹狩りを権威の象徴にした。鷹狩りと称しての領地視察もしている。野生の鷹を飼い馴らすには根気と技術も必要だった。贈り物で貰った鷹は本当に嬉しかったと思う。当時鷹は奥羽諸藩、松前藩(北海道)で捕らえられたものと朝鮮半島のものが上物とされていた。松前藩では藩の収入の半分近くは鷹の売り上げによるものだったらしい。巣山(愛知県)や巣高山(尾張藩)の名は狩猟や入山を禁じて鷹の繁殖をはかるための名前として残っている。
初夢にみると縁起が良いとされた鷹。家康は1612年に鷹狩りで手に入れた鶴を朝廷に献上している。白鳥の肉と同様高級食材で、鷹狩りでは鶴をたくさん捕らえている。

放たれた鷹が近づいてくる。勿論覚悟はしている。でも皮の手袋をはめた右手はしっかり伸ばしていても思わず目をつぶってしまった。するとふんわりとやさしい重みを感じた。そっと目を開けると鷹が私の手にすでに乗っていた。眼光は鋭いが静かにしていた。鷹はそれまで怖いと思っていたが、なんだかこそばゆい嬉しさだった。
その体験をしたのは静岡県担当の国民文化祭の年で10年前のこと。地元のまつりのイベント広場で鷹匠を呼んでその技を見せる情報があった。絶対行きたいと思った。
イベント広場に着くと、鷹匠が高草山の方へ鷹を飛ばしていた。鷹は山の上を飛行し、しばらくすると鷹匠の元に戻ってきた。鷹の習性のことは知らないが獲物を見つける訓練かもと思った。それからイベントが始まったのだ。鷹匠同士が離れて向かい合い、一人は餌の肉を隠し持ち、手袋をした手を横に出していた。赤い色の肉が私の目にもはっきり見えた。もう一人が鷹を放つ。高く飛ぶと思っていたのにすーっと低く飛んで相手の鷹匠に一直線だった。餌は鷹がついばんでいた。
江戸時代の通信使は鷹を徳川への贈り物として50居(もと・・鷹を数える単位)持参している。途中で死亡することも珍しくなかったので、予備で多く連れてきたのだ。1居につき1日に鶉3羽、雀12羽、鳩大1羽半小2羽の食事。
家康は鷹が好きで駿府公園に鷹を手にしている銅像があり、公園の近くに鷹匠という地名も残っている。家康は天下統一を成し遂げた後、鷹の売買を禁止し、鷹狩りを権威の象徴にした。鷹狩りと称しての領地視察もしている。野生の鷹を飼い馴らすには根気と技術も必要だった。贈り物で貰った鷹は本当に嬉しかったと思う。当時鷹は奥羽諸藩、松前藩(北海道)で捕らえられたものと朝鮮半島のものが上物とされていた。松前藩では藩の収入の半分近くは鷹の売り上げによるものだったらしい。巣山(愛知県)や巣高山(尾張藩)の名は狩猟や入山を禁じて鷹の繁殖をはかるための名前として残っている。
初夢にみると縁起が良いとされた鷹。家康は1612年に鷹狩りで手に入れた鶴を朝廷に献上している。白鳥の肉と同様高級食材で、鷹狩りでは鶴をたくさん捕らえている。
無人駅の芸術祭/大井川 ご案内2
会員様からの寄稿
家康はやっぱり埋めたんだ
大坂城(大阪城)

有料拝観チケットを買うまで150人以上の人が列を成していた。日本100名城に選定された大阪城。今空前のお城ブーム。「大阪城の石垣がすごい。1番大きいのは畳36畳・重さ108㌧」とテレビで話題にしていた。大阪に来るたびに遠くから眺めていただけで、城の中に入ったことはなかった。天守が昭和6年に鉄骨鉄筋コンクリート構造によって復興された国宝ではない残念なお城だったから。
ところで大阪城の字。「坂」は転げ落ちて縁起が悪いので「坂」→明治20年に「阪」に変わったらしい。
車をNHK側に近い駐車場に止めて大阪城に入った。桜門を入ると巨石が見えた。蛸石と呼ばれ有名だ。この巨石はクレーンの無い時代に人力でどう運んだのだろう。高さ6㍍・最大巾14㍍。瀬戸内海の島の花崗岩を備前国岡山藩主池田忠雄が運んでいる。海路で運ぶには大きな筏(いかだ)をつくりその下に網で吊り下げ、筏の周囲には空樽などを浮かべて浮力を増したらしい。苦労が偲ばれる。その大阪城の石垣は「太閤さん=秀吉」が造ったと地元の人は思っていたらしい。ところが・・・昭和34年発掘調査ですべてが地下に埋もれているとわかった。安土桃山時代に築かれたお城は江戸時代に修築。その時、高さ数㍍の盛り土をして現在私達が見ている城は1620~1629にかけて徳川秀忠が造ったものだとわかったのだった。地下で見つかった太閤さんの石垣は野面積み(のずらづみ)だったのだ。
駿府の城の発掘でも、豊臣の金箔の瓦が駿府城の下に埋められていたことがわかり、新聞を賑わした。まさか土で埋められているとは考えてもいなかった。静岡まつりでも発掘現場の風景が見えるように囲みの塀の1部を透明なビニールにしていて外から見える配慮がしてあった。静岡市の配慮がいいなと思った。
チケットを買うために並んでいたとき、城の近くでバンバンと鉄砲の音がした。煙があがったので「並んでる場合じゃない」と列を離れて見に行った。ステージがあり六文銭の旗印の間で甲冑を着ていた人達が銃を撃っていた。アナウンスで「空撃ちです」と言っていたが、音が大きくリアル感があってわくわくした。私はこういう音が好きなんだと思った。
でもG20のために大阪城の堀に潜って不審物がないか大阪府警警備本部は確認している。首脳会議で本物の鉄砲の音が響かないことを祈った。
大坂城(大阪城)
有料拝観チケットを買うまで150人以上の人が列を成していた。日本100名城に選定された大阪城。今空前のお城ブーム。「大阪城の石垣がすごい。1番大きいのは畳36畳・重さ108㌧」とテレビで話題にしていた。大阪に来るたびに遠くから眺めていただけで、城の中に入ったことはなかった。天守が昭和6年に鉄骨鉄筋コンクリート構造によって復興された国宝ではない残念なお城だったから。
ところで大阪城の字。「坂」は転げ落ちて縁起が悪いので「坂」→明治20年に「阪」に変わったらしい。
車をNHK側に近い駐車場に止めて大阪城に入った。桜門を入ると巨石が見えた。蛸石と呼ばれ有名だ。この巨石はクレーンの無い時代に人力でどう運んだのだろう。高さ6㍍・最大巾14㍍。瀬戸内海の島の花崗岩を備前国岡山藩主池田忠雄が運んでいる。海路で運ぶには大きな筏(いかだ)をつくりその下に網で吊り下げ、筏の周囲には空樽などを浮かべて浮力を増したらしい。苦労が偲ばれる。その大阪城の石垣は「太閤さん=秀吉」が造ったと地元の人は思っていたらしい。ところが・・・昭和34年発掘調査ですべてが地下に埋もれているとわかった。安土桃山時代に築かれたお城は江戸時代に修築。その時、高さ数㍍の盛り土をして現在私達が見ている城は1620~1629にかけて徳川秀忠が造ったものだとわかったのだった。地下で見つかった太閤さんの石垣は野面積み(のずらづみ)だったのだ。
駿府の城の発掘でも、豊臣の金箔の瓦が駿府城の下に埋められていたことがわかり、新聞を賑わした。まさか土で埋められているとは考えてもいなかった。静岡まつりでも発掘現場の風景が見えるように囲みの塀の1部を透明なビニールにしていて外から見える配慮がしてあった。静岡市の配慮がいいなと思った。
チケットを買うために並んでいたとき、城の近くでバンバンと鉄砲の音がした。煙があがったので「並んでる場合じゃない」と列を離れて見に行った。ステージがあり六文銭の旗印の間で甲冑を着ていた人達が銃を撃っていた。アナウンスで「空撃ちです」と言っていたが、音が大きくリアル感があってわくわくした。私はこういう音が好きなんだと思った。
でもG20のために大阪城の堀に潜って不審物がないか大阪府警警備本部は確認している。首脳会議で本物の鉄砲の音が響かないことを祈った。
無人駅の芸術祭/大井川 ご案内
会員様からの寄稿
郡山市立美術館

バリー・フラナガン「野兎と鐘」が美術館にたどり着くまでのプロムナードでとっても目立っている。建物と美しい森に囲まれた空間が川のせせらぎに見えるように設計された石達の表情が自然を超えてアートにもなっていた。ただ水が流れていなかった。不思議に思い聞いてみると「本当は水が流れていたんです。でも福島の地震で配管が壊れ・・・石の下にあるものだから、修理にお金がかかるので・・」と地元の人に教えてもらった。地震の影響はこんなところにもあった。
『フジフィルム・フォトコレクション展』日本の写真史を飾った写真家の「私の1枚」の展示会が企画されていた。この企画はフジフィルム(株)創立80周年を記念して収集されたもので、2014年にフジフィルム スクェア(東京)で展示され、その後は日本各地の美術館で巡回しているものだった。「101の私の一枚」。上野彦馬・下岡蓮杖から始まり、私の大好きな写真家たちの選ばれた1枚。立木義浩・篠山紀信・土門拳・荒木経惟・東松照明・森山大道・中村征夫・長倉洋海・林忠彦・植田正治・木村伊兵衛・大竹省二・田沼武能・細江英公・木之下晃・石内都・竹内敏信・星野道夫・田中光常・秋山庄太郎・・たくさんの写真家の作品が輝いていた。101枚の展示の中で、20枚程が私の人生の中で影響を受けた写真家だ。
作品の中で一番ぐっと来たのは星野道夫の作品。龍村仁監督の映画『地球交響曲第3番』で登場して素敵だと心惹かれた人。冒険家でロシアのカムチャッカ半島のテントでヒグマの襲撃を受け43歳で亡くなっている。『夕暮れの河を渡るカリブー(1988年頃)』の1枚のみずみずしい力あふれる生命力の写真に脱帽だ。
またあこがれの写真家は木之下昇さん。音楽写真家としてクラシック音楽の世界を撮影している。演奏シーンなどは胸がきゅんきゅんする。アルフレート・ブレンデルの演奏風景。めがねのレンズにピアノの鍵盤が写り込んでいる。シャッター音を気にする演奏家に近づけるなんて幸せすぎる。
私は子育て中に写真二科の会員になった。県レベルの写真集に作品が掲載されてもいる。初めての撮影会では女性のモデルを撮る体験をした。大勢の男の人達の熱気にびっくりしたが「前に行って撮ればいいよ」と場所を譲ってくれたことも懐かしい。その後の写真ブームでは100人以上も集まる撮影スポットでは場所取りに苦労している。記憶の中では大室山の山焼きに通って、火の上昇気流が起した竜巻を撮って入選した作品がちょっと心に残る自慢の1枚。
たった1枚の作品は運命でしか撮れないのだ。
バリー・フラナガン「野兎と鐘」が美術館にたどり着くまでのプロムナードでとっても目立っている。建物と美しい森に囲まれた空間が川のせせらぎに見えるように設計された石達の表情が自然を超えてアートにもなっていた。ただ水が流れていなかった。不思議に思い聞いてみると「本当は水が流れていたんです。でも福島の地震で配管が壊れ・・・石の下にあるものだから、修理にお金がかかるので・・」と地元の人に教えてもらった。地震の影響はこんなところにもあった。
『フジフィルム・フォトコレクション展』日本の写真史を飾った写真家の「私の1枚」の展示会が企画されていた。この企画はフジフィルム(株)創立80周年を記念して収集されたもので、2014年にフジフィルム スクェア(東京)で展示され、その後は日本各地の美術館で巡回しているものだった。「101の私の一枚」。上野彦馬・下岡蓮杖から始まり、私の大好きな写真家たちの選ばれた1枚。立木義浩・篠山紀信・土門拳・荒木経惟・東松照明・森山大道・中村征夫・長倉洋海・林忠彦・植田正治・木村伊兵衛・大竹省二・田沼武能・細江英公・木之下晃・石内都・竹内敏信・星野道夫・田中光常・秋山庄太郎・・たくさんの写真家の作品が輝いていた。101枚の展示の中で、20枚程が私の人生の中で影響を受けた写真家だ。
作品の中で一番ぐっと来たのは星野道夫の作品。龍村仁監督の映画『地球交響曲第3番』で登場して素敵だと心惹かれた人。冒険家でロシアのカムチャッカ半島のテントでヒグマの襲撃を受け43歳で亡くなっている。『夕暮れの河を渡るカリブー(1988年頃)』の1枚のみずみずしい力あふれる生命力の写真に脱帽だ。
またあこがれの写真家は木之下昇さん。音楽写真家としてクラシック音楽の世界を撮影している。演奏シーンなどは胸がきゅんきゅんする。アルフレート・ブレンデルの演奏風景。めがねのレンズにピアノの鍵盤が写り込んでいる。シャッター音を気にする演奏家に近づけるなんて幸せすぎる。
私は子育て中に写真二科の会員になった。県レベルの写真集に作品が掲載されてもいる。初めての撮影会では女性のモデルを撮る体験をした。大勢の男の人達の熱気にびっくりしたが「前に行って撮ればいいよ」と場所を譲ってくれたことも懐かしい。その後の写真ブームでは100人以上も集まる撮影スポットでは場所取りに苦労している。記憶の中では大室山の山焼きに通って、火の上昇気流が起した竜巻を撮って入選した作品がちょっと心に残る自慢の1枚。
たった1枚の作品は運命でしか撮れないのだ。
会員様からの寄稿
利休にたずねよ

2013年制作の「利休にたずねよ」のDVDを観た。セリフを抑えた利休の所作の美しさが際立っていた。
監督の美意識のすべてをつくり込んで出来た映画だ。「茶を教えてくれた人からの頂き物」と言い放ち、秀
吉が欲しがる香合を謎の茶器のようにして映画が進行していった。
史実とは違っていても、香合を物語の展開の中心に置くことを考え付いた原作者のアイデアはすごい。国宝級の三井寺、大徳寺、神護寺、南禅寺、彦根城などのロケも取り入れてあったが、沢山の文化財の映像よりも、ただただ市川海老蔵扮する利休の墨染めの衣の似合う茶席が天下一品だった。ところで実在の利休はこんなにかっこ良かったのだろうか? 調べてみると身長180㌢程でかなりの巨躯。長谷川等伯の描いた像ではちょっとぽっちゃりしている。
利休の本名は「宗易(そうえき)」。信長、秀吉と二代にわたる戦国の天下人に仕えた茶人で、私が知っている「利休」の名は正親町天皇(おおぎまちてんのう)より与えられた号とのこと。茶人でもあり商人だった宗易が、町人の身分では宮中参内できないためもらった名前だった。名の由来は諸説あって「利心、休せよ」《才能におぼれず、古老錐(きり)の境地を目指せ》からだと知った。
黄金の茶室は秀吉が造らせたのだと思っていたが、設計は利休だと知ったときには、びっくりぽんだった。映像では上手に茶室として使っていた。
「美はわたしが決めること」と利休は言った・・利休の美意識が、今の茶道の流れに繋がっているのか? あんなにも有名な利休のことを私はほとんど知らないでいた。でも・・お茶の世界が日常の生活とはかけ離れすぎてしまっている。テレビで「急須でお茶を」とコマーシャルが流れていても、日々はペットボトルで暮らしている。どうしてこんな私達になってしまったのだろうか。
利休の茶の湯の重要な点は、名物を尊ぶ既成の価値観を否定したところにあるのだと知った。実は禁欲的だったのだ。新たに創作したのが楽茶碗や万代屋釜(もずやがま)などの利休道具。高価でなかった点が重要だったはずなのに・・。
2013年制作の「利休にたずねよ」のDVDを観た。セリフを抑えた利休の所作の美しさが際立っていた。
監督の美意識のすべてをつくり込んで出来た映画だ。「茶を教えてくれた人からの頂き物」と言い放ち、秀
吉が欲しがる香合を謎の茶器のようにして映画が進行していった。
史実とは違っていても、香合を物語の展開の中心に置くことを考え付いた原作者のアイデアはすごい。国宝級の三井寺、大徳寺、神護寺、南禅寺、彦根城などのロケも取り入れてあったが、沢山の文化財の映像よりも、ただただ市川海老蔵扮する利休の墨染めの衣の似合う茶席が天下一品だった。ところで実在の利休はこんなにかっこ良かったのだろうか? 調べてみると身長180㌢程でかなりの巨躯。長谷川等伯の描いた像ではちょっとぽっちゃりしている。
利休の本名は「宗易(そうえき)」。信長、秀吉と二代にわたる戦国の天下人に仕えた茶人で、私が知っている「利休」の名は正親町天皇(おおぎまちてんのう)より与えられた号とのこと。茶人でもあり商人だった宗易が、町人の身分では宮中参内できないためもらった名前だった。名の由来は諸説あって「利心、休せよ」《才能におぼれず、古老錐(きり)の境地を目指せ》からだと知った。
黄金の茶室は秀吉が造らせたのだと思っていたが、設計は利休だと知ったときには、びっくりぽんだった。映像では上手に茶室として使っていた。
「美はわたしが決めること」と利休は言った・・利休の美意識が、今の茶道の流れに繋がっているのか? あんなにも有名な利休のことを私はほとんど知らないでいた。でも・・お茶の世界が日常の生活とはかけ離れすぎてしまっている。テレビで「急須でお茶を」とコマーシャルが流れていても、日々はペットボトルで暮らしている。どうしてこんな私達になってしまったのだろうか。
利休の茶の湯の重要な点は、名物を尊ぶ既成の価値観を否定したところにあるのだと知った。実は禁欲的だったのだ。新たに創作したのが楽茶碗や万代屋釜(もずやがま)などの利休道具。高価でなかった点が重要だったはずなのに・・。
会員様からの寄稿
静岡まつり
手筒花火

力強いゴーという轟音と共に火柱が立つ。竹の筒から吹き上がる火は5㍍。オレンジ色の中に白いキラキラした火の粉が舞い落ちる。筒を抱えた若者の頭上に火の粉が落ちる。その瞬間短い強いボンと大きな音がして地面から火の粉が沸き上がる。手筒の底から破裂する「はね」の衝撃音。そのたびに興奮して大声を出してしまう自分がいた。
静岡まつりのフィナーレが手筒花火だ。今年は安全の為のロープの周りにパイプイスが用意してあった。私が1時間前に到着した時には、最前列は既に人で埋まっていた。
1613年徳川家康がイギリス国王使節ジョン・セリーヌを明国の商人が駿府城内に案内して城の二の丸で花火を見学した・・・と「駿府政事録」「宮中秘策」「武徳編年集成」に書かれていると静岡まつりの情報にあった。その花火が手筒花火らしい。静岡祭りのフィナーレでお披露目のこの手筒花火。迫力が何と言っても凄い。音と炎と男たちに降りかかる火の粉に心がわしづかみになる。
地元の男衆が最初の竹を切るところから最後の火薬を詰めるところまで全て自分自身の手によってつくると聞いたことがある。なぜなら筒から噴出す火の量がまちまちだったから、やっぱり上手下手があるのかとも思う。
ところで私の住む岡部町に龍勢花火がある。これは地元の地区ごとに連があり、各部落ごとに製造方法は秘伝で伝えていた。この龍勢は細い竹の筒に火薬を詰めて打ち上げる。のろしの役目をしたのではとも言われている。
火薬といえば・・猪鉄砲(野荒しの猪や鹿を退治する)に関する古文書がある。江戸時代は領主から鉄砲を借りる形で、作物を守るための道具として幕府や藩は無税で鉄砲を貸与している。ただ管理はしっかりしていて、古文書にはどこの誰に何丁と書かれている。藤枝の横内陣屋では、「浜固め」のときに鉄砲を使える農民を異国船の漂着に動員している。
思うに、火薬を扱う花火は、農民を兵力に考えていたからだ。岡部の龍勢花火・清水の龍勢花火そして手筒花火などは常に農民に火薬のあつかいをさせる事で、駿府の徳川を守らせようとしたのだと・・私は考えている。
手筒花火
力強いゴーという轟音と共に火柱が立つ。竹の筒から吹き上がる火は5㍍。オレンジ色の中に白いキラキラした火の粉が舞い落ちる。筒を抱えた若者の頭上に火の粉が落ちる。その瞬間短い強いボンと大きな音がして地面から火の粉が沸き上がる。手筒の底から破裂する「はね」の衝撃音。そのたびに興奮して大声を出してしまう自分がいた。
静岡まつりのフィナーレが手筒花火だ。今年は安全の為のロープの周りにパイプイスが用意してあった。私が1時間前に到着した時には、最前列は既に人で埋まっていた。
1613年徳川家康がイギリス国王使節ジョン・セリーヌを明国の商人が駿府城内に案内して城の二の丸で花火を見学した・・・と「駿府政事録」「宮中秘策」「武徳編年集成」に書かれていると静岡まつりの情報にあった。その花火が手筒花火らしい。静岡祭りのフィナーレでお披露目のこの手筒花火。迫力が何と言っても凄い。音と炎と男たちに降りかかる火の粉に心がわしづかみになる。
地元の男衆が最初の竹を切るところから最後の火薬を詰めるところまで全て自分自身の手によってつくると聞いたことがある。なぜなら筒から噴出す火の量がまちまちだったから、やっぱり上手下手があるのかとも思う。
ところで私の住む岡部町に龍勢花火がある。これは地元の地区ごとに連があり、各部落ごとに製造方法は秘伝で伝えていた。この龍勢は細い竹の筒に火薬を詰めて打ち上げる。のろしの役目をしたのではとも言われている。
火薬といえば・・猪鉄砲(野荒しの猪や鹿を退治する)に関する古文書がある。江戸時代は領主から鉄砲を借りる形で、作物を守るための道具として幕府や藩は無税で鉄砲を貸与している。ただ管理はしっかりしていて、古文書にはどこの誰に何丁と書かれている。藤枝の横内陣屋では、「浜固め」のときに鉄砲を使える農民を異国船の漂着に動員している。
思うに、火薬を扱う花火は、農民を兵力に考えていたからだ。岡部の龍勢花火・清水の龍勢花火そして手筒花火などは常に農民に火薬のあつかいをさせる事で、駿府の徳川を守らせようとしたのだと・・私は考えている。
会員様からの寄稿 行ってきました
「百年の編み手たち」展
100年をキーワード+全館リニューアル・オープン

●東京都現代美術館
『本展は、1910年代から現代までの日本の美術について、編集的な視点で新旧の表現を捉えて独自の創作を展開した作家たちの実践として、当館のコレクションを格に再考するものです。
岸田劉生が活躍した大正時代から今日まで、それぞれの時代の「編み手たち」は、その時々の課題と向き合い、「日本の美術のありよう」をめぐって批評的に制作してきました。本展では日本の近現代美術のなかで、さまざまな要素の選択的な「編集」を通して主体を揺るがしつつ制作を行う作家たちの活動に着目し、その背景を探っていきます。さらに、時代とともに変化してきた、当館が位置する木場という地域をめぐる創造も紹介します。
日本の近現代美術史のなかに点在する重要な作品群を、当館の3フロアの展示室全体を使って総覧することで、百年にわたる歴史のひとつの側面があきらかになるでしょう』がコンセプト。
小さい白いライラックの香りがほんのり漂う木場公園を歩いた。8年ぶりかもと思う。道すがら都心の公園でテニスを楽しむ人達を左に見ながらたどり着いた。途中の広場は災害の時の避難地にもなっていた。
どうやって搬入したのかとびっくりの大きな作品達の数々。静岡県立美術館でも現代美術を観ることも出来るが、やはりここ現代美術館は半端ない数だ。現代美術が内包している、作家の批評精神を読みきれない作品もまだまだあるなと思って観た。たくさんの冊子も保有しているので、同時に展示していて、それも感動だった。
美術館が評価し応援している「編み手」たちの展示。だが私は、むしろ美術館学芸員が「編み手」だと頷いた展覧会だった。
自分の人生と共に変容してきた様々なアートシーン。この先をまだまだ覗いていたいな。
そんなことを考えた展覧会だった。
100年をキーワード+全館リニューアル・オープン
●東京都現代美術館
『本展は、1910年代から現代までの日本の美術について、編集的な視点で新旧の表現を捉えて独自の創作を展開した作家たちの実践として、当館のコレクションを格に再考するものです。
岸田劉生が活躍した大正時代から今日まで、それぞれの時代の「編み手たち」は、その時々の課題と向き合い、「日本の美術のありよう」をめぐって批評的に制作してきました。本展では日本の近現代美術のなかで、さまざまな要素の選択的な「編集」を通して主体を揺るがしつつ制作を行う作家たちの活動に着目し、その背景を探っていきます。さらに、時代とともに変化してきた、当館が位置する木場という地域をめぐる創造も紹介します。
日本の近現代美術史のなかに点在する重要な作品群を、当館の3フロアの展示室全体を使って総覧することで、百年にわたる歴史のひとつの側面があきらかになるでしょう』がコンセプト。
小さい白いライラックの香りがほんのり漂う木場公園を歩いた。8年ぶりかもと思う。道すがら都心の公園でテニスを楽しむ人達を左に見ながらたどり着いた。途中の広場は災害の時の避難地にもなっていた。
どうやって搬入したのかとびっくりの大きな作品達の数々。静岡県立美術館でも現代美術を観ることも出来るが、やはりここ現代美術館は半端ない数だ。現代美術が内包している、作家の批評精神を読みきれない作品もまだまだあるなと思って観た。たくさんの冊子も保有しているので、同時に展示していて、それも感動だった。
美術館が評価し応援している「編み手」たちの展示。だが私は、むしろ美術館学芸員が「編み手」だと頷いた展覧会だった。
自分の人生と共に変容してきた様々なアートシーン。この先をまだまだ覗いていたいな。
そんなことを考えた展覧会だった。