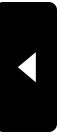会員様からの寄稿
いってきました①
「アイチ アート クロニクル」展
100年をキーワード+全館リニューアル・オープン
●愛知県立美術館
『今から100年前の1919年を起点にして、20-30年代の洋画壇やアブァンギャルドの活発な活動、40-50年代の混乱と復興、60-70年代の反芸術やオフ・ミュージアムの傾向、80-90年代の現代美術を扱うギャラリーの増加、そして2000-10年代の官主導の公募展や芸術祭の隆盛にいたるまでの100年のあいだに、愛知の前衛的なアートシーンを様々なかたちで揺り動かしてきたムーブメントや事件を辿る企画です』がコンセプト。
4月の桜満開の日訪ねてみた。静岡に住んでいる私は申し訳ないが愛知の作家たちのことは良く知らない。でも展示は自分の知っている美術の流れが解るように構成されていた。桜画廊とその周辺のゼロ次元のハプニング記録の映像・「ゴミ裁判1971」の関連資料があった。
展示室で北川民次氏の《南国の花》と《砂の工場》に出会ったとき、そのフォルムの力強さにやっぱり引き付けられた。民次氏は静岡県島田市の生まれだが、奥さんの実家の愛知県に住んでいたことがある。静岡県立美術館でも郷土の画家として10点以上の館蔵品があり、其の中でも私は《タスコの祭り》が好きだ。今から30年程前に「かみや美術館」で晩年の民次氏にお会いした。その記憶も蘇った。粋な和服姿の女性と一緒だった。作品以外のこうした出会いも作品を観ながら思い出して懐かしかった。
アイチのアートの立ち位置が見える展覧会だった。

「アイチ アート クロニクル」展
100年をキーワード+全館リニューアル・オープン
●愛知県立美術館
『今から100年前の1919年を起点にして、20-30年代の洋画壇やアブァンギャルドの活発な活動、40-50年代の混乱と復興、60-70年代の反芸術やオフ・ミュージアムの傾向、80-90年代の現代美術を扱うギャラリーの増加、そして2000-10年代の官主導の公募展や芸術祭の隆盛にいたるまでの100年のあいだに、愛知の前衛的なアートシーンを様々なかたちで揺り動かしてきたムーブメントや事件を辿る企画です』がコンセプト。
4月の桜満開の日訪ねてみた。静岡に住んでいる私は申し訳ないが愛知の作家たちのことは良く知らない。でも展示は自分の知っている美術の流れが解るように構成されていた。桜画廊とその周辺のゼロ次元のハプニング記録の映像・「ゴミ裁判1971」の関連資料があった。
展示室で北川民次氏の《南国の花》と《砂の工場》に出会ったとき、そのフォルムの力強さにやっぱり引き付けられた。民次氏は静岡県島田市の生まれだが、奥さんの実家の愛知県に住んでいたことがある。静岡県立美術館でも郷土の画家として10点以上の館蔵品があり、其の中でも私は《タスコの祭り》が好きだ。今から30年程前に「かみや美術館」で晩年の民次氏にお会いした。その記憶も蘇った。粋な和服姿の女性と一緒だった。作品以外のこうした出会いも作品を観ながら思い出して懐かしかった。
アイチのアートの立ち位置が見える展覧会だった。
展覧会のお知らせ
会員様からの寄稿
花泥棒

「花泥棒のコーヒーは美味しいよ」と久しぶりに会った知り合いが言った。「花泥棒・・懐かしい」と思わず口に出た。下北沢で入ったお店の匂いが蘇って心がワープした。
静岡県生まれの私も3人の孫を持つ年になってしまった。もう《東京へ家出したい》と思わないが、子供を育てている間でも東京への憧れがあった。うじうじ生きていた。「東京は生き馬の目を抜くところ」と話す母親に育てられ刷り込まれ、勇気が無かった私だった。そんな自分の過去の感情を話すと「そういうことを含めて才能が無かったんじゃない」と知り合いにやんわり一喝された。
息子が18歳のとき、私の目の前で両手を合わせ「東京へ行かせてください」と言った。そのしぐさは真剣そのもの。飛び立とうとしている心根に勿論何故かワクワクしてオッケーした。主人は「男が音楽なんかで食っていけるわけがないから」と言い放って無視した。でも私はその後東京で暮らしていくお金を送るために仕事をした。息子の一人応援団の私は心配やら喜びやら一言では語れない感情で仕事をこなして6年程過ぎた。やりたいことを自分で選んで、さらっと飛び立った
子供が羨ましかった。そんな息子を応援することが幸せな私だった。
ある日突然電話があって「もうお金送ってくれなくても大丈夫だから」と受話器の向こうからの声が聞こえた。その言葉にいい子だなーと思う私がいた。黙っていれはまだ黙々と送金するのは嫌じゃない。でも何とか食べていけることができるようになったのだとホッとした。同時に諦めてしまっている自分の夢の破片が見えて涙が流れた。
花泥棒という言葉の響きが好きだ。フランス風のイメージが沸きあがる・・・花が綺麗で盗みたいと思うほどの花が人生の中で一度だけあった。
寒い冬の山道の脇に咲いていたアジサイ。梅雨の頃のそのままの綺麗な形でまだ咲いていた。強い風にあたらない位置なので、形がそのまま残ることが出来たのだろう。パウル・クレーの《ポリフォニーに囲まれた白》の中の複雑な赤紫の色だったのだ。寒い冷気の中、自然の中でドライフラワーになって生まれた色なのだ。
この環境の中でも、素敵な色になる方法をまだ模索したいと花を見ながら思った私自身だった。
「花泥棒のコーヒーは美味しいよ」と久しぶりに会った知り合いが言った。「花泥棒・・懐かしい」と思わず口に出た。下北沢で入ったお店の匂いが蘇って心がワープした。
静岡県生まれの私も3人の孫を持つ年になってしまった。もう《東京へ家出したい》と思わないが、子供を育てている間でも東京への憧れがあった。うじうじ生きていた。「東京は生き馬の目を抜くところ」と話す母親に育てられ刷り込まれ、勇気が無かった私だった。そんな自分の過去の感情を話すと「そういうことを含めて才能が無かったんじゃない」と知り合いにやんわり一喝された。
息子が18歳のとき、私の目の前で両手を合わせ「東京へ行かせてください」と言った。そのしぐさは真剣そのもの。飛び立とうとしている心根に勿論何故かワクワクしてオッケーした。主人は「男が音楽なんかで食っていけるわけがないから」と言い放って無視した。でも私はその後東京で暮らしていくお金を送るために仕事をした。息子の一人応援団の私は心配やら喜びやら一言では語れない感情で仕事をこなして6年程過ぎた。やりたいことを自分で選んで、さらっと飛び立った
子供が羨ましかった。そんな息子を応援することが幸せな私だった。
ある日突然電話があって「もうお金送ってくれなくても大丈夫だから」と受話器の向こうからの声が聞こえた。その言葉にいい子だなーと思う私がいた。黙っていれはまだ黙々と送金するのは嫌じゃない。でも何とか食べていけることができるようになったのだとホッとした。同時に諦めてしまっている自分の夢の破片が見えて涙が流れた。
花泥棒という言葉の響きが好きだ。フランス風のイメージが沸きあがる・・・花が綺麗で盗みたいと思うほどの花が人生の中で一度だけあった。
寒い冬の山道の脇に咲いていたアジサイ。梅雨の頃のそのままの綺麗な形でまだ咲いていた。強い風にあたらない位置なので、形がそのまま残ることが出来たのだろう。パウル・クレーの《ポリフォニーに囲まれた白》の中の複雑な赤紫の色だったのだ。寒い冷気の中、自然の中でドライフラワーになって生まれた色なのだ。
この環境の中でも、素敵な色になる方法をまだ模索したいと花を見ながら思った私自身だった。
会員様からの寄稿
みほしるべ
静岡市三保松原文化創造センター

みほしるべは「三保を知る+道しるべ」の意味で生まれたネーミング。5年前に世界文化遺産「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」として登録された「三保松原」。国内では17件目の世界遺産だった。(今は22件が世界遺産になっている)。その地に「静岡市三保松原文化創造センターみほしるべ」が開設された。
県立美術館友の会の会報誌のアトリエ訪問で取材し記事を書かせていただいた澤田裕一氏から作品(~松にふれて~)を展示していると案内が届き、出かけてみた。取材させていただいた澤田氏のメインテーマは「松ぼっくり」。センター内に展示されていた、版画は外光の中で輝いていた。会場で久しぶりにお会いできた。
到着するとセンター名誉館長の近藤誠一氏の講演があることがわかったので会場に入った。元外交官・文化庁長官。ユネスコの遺産に選ばれるための対策のポイントを熱く語った。三保は富士山から離れていたが日本人の心の中に三保と富士山が繋がっていることを説明した。目に見えないものの価値・精神性などを伝えた話だった。「プノンペンでの世界遺産委員会で、自作英文をネイティブの方たちのアドバイスを受けて手直し、アピーした」とぶっちゃけ話があった
ところで、心魅かれて訪ねたい文化遺産。歴史の中から伝わってくる想いに触れてみたい。
●長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産に行って祈りたい。
静岡市三保松原文化創造センター
みほしるべは「三保を知る+道しるべ」の意味で生まれたネーミング。5年前に世界文化遺産「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」として登録された「三保松原」。国内では17件目の世界遺産だった。(今は22件が世界遺産になっている)。その地に「静岡市三保松原文化創造センターみほしるべ」が開設された。
県立美術館友の会の会報誌のアトリエ訪問で取材し記事を書かせていただいた澤田裕一氏から作品(~松にふれて~)を展示していると案内が届き、出かけてみた。取材させていただいた澤田氏のメインテーマは「松ぼっくり」。センター内に展示されていた、版画は外光の中で輝いていた。会場で久しぶりにお会いできた。
到着するとセンター名誉館長の近藤誠一氏の講演があることがわかったので会場に入った。元外交官・文化庁長官。ユネスコの遺産に選ばれるための対策のポイントを熱く語った。三保は富士山から離れていたが日本人の心の中に三保と富士山が繋がっていることを説明した。目に見えないものの価値・精神性などを伝えた話だった。「プノンペンでの世界遺産委員会で、自作英文をネイティブの方たちのアドバイスを受けて手直し、アピーした」とぶっちゃけ話があった
ところで、心魅かれて訪ねたい文化遺産。歴史の中から伝わってくる想いに触れてみたい。
●長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産に行って祈りたい。
友の会新会長就任
木下直之館長講座「水族館巡礼」
第2回 木下直之館長講座
『水族館巡礼』
静岡県立美術館木下直之館長による特別講座
動物園巡礼に続き第2弾として『水族館巡礼』を開催いたします
東海大学海洋科学博物館の見学と博物館元館長でもある
西源二郎氏と鈴木克美氏のレクチャーそれから木下直之館長も加わり鼎談を行います
ご興味のある方はお申込みお待ちしています


『水族館巡礼』
静岡県立美術館木下直之館長による特別講座
動物園巡礼に続き第2弾として『水族館巡礼』を開催いたします
東海大学海洋科学博物館の見学と博物館元館長でもある
西源二郎氏と鈴木克美氏のレクチャーそれから木下直之館長も加わり鼎談を行います
ご興味のある方はお申込みお待ちしています
展覧会のお知らせ
会員様からの寄稿
これからの動物園とは・・
動物園巡礼・木下直之著(静岡県立美術館館長)を読んで

「動物巡礼」という本を読んだ。動物園をめざして東奔西走、地図を持たない巡礼の旅。通天閣とサバンナとサイ、別府地獄のカバとワニ、大須観音商店街のラクダ行列・・・行く先々の風景から、人と動物との関係がみえてくる。と本の帯に書かれていた。表紙の写真はリタとロイドのセメント像(戦前の大阪市天王寺動物園で人気者だったチンパンジー)。著者は「いつ会いに行っても、リタ&ロイドには哀愁が漂っている。どうしてこんな姿で彫像と化してしまったのかふたりは納得がいかない。釈然としないという表情だ。」と書いている。お城の中になぜ動物園があるのだろうか?と動物園の歴史を紐解き「動物園と人の物語をつむぐ」内容になっていた。1歳の時に浜松の動物園を訪れた時から巡礼がはじまり動物の本来の生態を生かす動物園へと至る。旅を重ね、動物園が博物館とつながる可能性に光を見ている感がある。
転勤族の私が小学校1年に住んでいた近くに動物園があった。朝はやく祖母に連れられて誰もいない動物園を散歩した。動物を眺めることだけで楽しかった。自分に子供が生まれてからは静岡市立動物園に通った。大人になっても動物に逢うことが楽しかった。動物との関係はそんな立ち位置だった。
動物との思い出の体験・・。
日本平動物園のニシキヘビ。ラジオの生放送の仕事。ニシキヘビを触ってしゃべる体験だった。ところが飼育員が「大丈夫だから」と体に巻き付けはじめた。イメージではぬるっとしていて死ぬほど気持ち悪いと思っていたが、ニシキヘビの皮膚はさらっとしていて、ヒヤッと冷たい感触で全然気持ち悪くなかった。貴重な体験をさせていただいた。
また扉の開いた檻があり、動物のいない檻の入口には「人間」と表示してあった。「そうか自分で檻に入るのか」ブラックジョークみたいだと感じていた。考えてみれば動物園側は人間も動物なのだと意識させたかったのだろうとも感じた。
「動物園巡礼」を読みながら、動物園の存在をこんなにも真剣に考える人がいたことにびっくりした。
最近『伊豆アニマルキングダム』動物園のマーコールとシマウマが話題だ。ヤギの仲間のマーコール「きなこ」がグリム童話ブレーメンの音楽隊みたいにシマウマの背中に乗っている姿がかわいいからだ。
そこは動植物自然公園の動物園だった。
動物園巡礼・木下直之著(静岡県立美術館館長)を読んで
「動物巡礼」という本を読んだ。動物園をめざして東奔西走、地図を持たない巡礼の旅。通天閣とサバンナとサイ、別府地獄のカバとワニ、大須観音商店街のラクダ行列・・・行く先々の風景から、人と動物との関係がみえてくる。と本の帯に書かれていた。表紙の写真はリタとロイドのセメント像(戦前の大阪市天王寺動物園で人気者だったチンパンジー)。著者は「いつ会いに行っても、リタ&ロイドには哀愁が漂っている。どうしてこんな姿で彫像と化してしまったのかふたりは納得がいかない。釈然としないという表情だ。」と書いている。お城の中になぜ動物園があるのだろうか?と動物園の歴史を紐解き「動物園と人の物語をつむぐ」内容になっていた。1歳の時に浜松の動物園を訪れた時から巡礼がはじまり動物の本来の生態を生かす動物園へと至る。旅を重ね、動物園が博物館とつながる可能性に光を見ている感がある。
転勤族の私が小学校1年に住んでいた近くに動物園があった。朝はやく祖母に連れられて誰もいない動物園を散歩した。動物を眺めることだけで楽しかった。自分に子供が生まれてからは静岡市立動物園に通った。大人になっても動物に逢うことが楽しかった。動物との関係はそんな立ち位置だった。
動物との思い出の体験・・。
日本平動物園のニシキヘビ。ラジオの生放送の仕事。ニシキヘビを触ってしゃべる体験だった。ところが飼育員が「大丈夫だから」と体に巻き付けはじめた。イメージではぬるっとしていて死ぬほど気持ち悪いと思っていたが、ニシキヘビの皮膚はさらっとしていて、ヒヤッと冷たい感触で全然気持ち悪くなかった。貴重な体験をさせていただいた。
また扉の開いた檻があり、動物のいない檻の入口には「人間」と表示してあった。「そうか自分で檻に入るのか」ブラックジョークみたいだと感じていた。考えてみれば動物園側は人間も動物なのだと意識させたかったのだろうとも感じた。
「動物園巡礼」を読みながら、動物園の存在をこんなにも真剣に考える人がいたことにびっくりした。
最近『伊豆アニマルキングダム』動物園のマーコールとシマウマが話題だ。ヤギの仲間のマーコール「きなこ」がグリム童話ブレーメンの音楽隊みたいにシマウマの背中に乗っている姿がかわいいからだ。
そこは動植物自然公園の動物園だった。
会員様からの寄稿
東海道中膝栗毛

駿府生まれの十返舎一九。名前は知っていたが、静岡出身ということを知ったのは岡部に住み始めてからだった。《おかべ》は宮中用語でおとふという意味だということも。何故なら宮中の壁は白いからだと。膝栗毛の中の「豆腐なる岡部の宿に・・」の豆腐はそういう意味である。でも町の有志でおとふで町おこしと動き始めたのに・・叶わなかった。失敗?。良いアイデアでも具体的に形にするのは難しいんだと思った。
十返舎一九は明和2年(1765)駿府の武士の子として生まれた。幼名を市九。若い頃江戸に出て武家奉公をしたり、大阪で奉行に仕えたりしたが、後に版元蔦谷重三郎に寄宿。独学で洒落本、人情本も出していた。十返舎一九は終生故郷の駿河にこだわり、架空の弥次・喜多の出身も駿河だったのだ。天保2年(1831)に67歳で亡くなっている。
職業作家の先駆け。享和2年(1802)に初版品川~箱根間が出版され、毎年1編ずつ書き上げ、7年後に京都・大阪見物編を。最終編までには初編から20年に及ぶロングセラーになっていた。取材のための旅とお酒好きらしく、職業作家とはいえ貧乏だったらしい。江戸時代を知るにはとても良い資料なのかとも思うが・・私はまだ読破していない。
弥次・喜多は一九の手を離れて全国の共有のアイドルとして扱われ、面白い旅といえば・・弥次・喜多のみが有名になった。実は・・・弥次・喜多は貧相で下品。くだらないいたずらを繰り返し、失敗ばかりする。内容の多くが飯盛り女という旅人相手の女郎買いや夜這いの話。人の小便を間違えて飲んだり、遺骨をかじったりなど汚い話。だから成人向きの本。が当時は庶民の共感を得た時代の本だったと解説にある。理由はこの時代には寺子屋で庶民も文字が読めるようになったこと、しかも自分より下の人として読んでいるうちに、自分の思ってもやれない愚考を代わりにやってくれる弥次と喜多に笑いを見つけたということだと。
ところで亡くなった遺体を火葬にすると、あらかじめ中に仕込んだ花火がドーンとあがって人々をたまげさせたと書かれていた。本当かどうかわからない・・・が、潔い死に方だ。
この世をばどりゃおいとまにせん香の煙とともに灰さようなら
駿府生まれの十返舎一九。名前は知っていたが、静岡出身ということを知ったのは岡部に住み始めてからだった。《おかべ》は宮中用語でおとふという意味だということも。何故なら宮中の壁は白いからだと。膝栗毛の中の「豆腐なる岡部の宿に・・」の豆腐はそういう意味である。でも町の有志でおとふで町おこしと動き始めたのに・・叶わなかった。失敗?。良いアイデアでも具体的に形にするのは難しいんだと思った。
十返舎一九は明和2年(1765)駿府の武士の子として生まれた。幼名を市九。若い頃江戸に出て武家奉公をしたり、大阪で奉行に仕えたりしたが、後に版元蔦谷重三郎に寄宿。独学で洒落本、人情本も出していた。十返舎一九は終生故郷の駿河にこだわり、架空の弥次・喜多の出身も駿河だったのだ。天保2年(1831)に67歳で亡くなっている。
職業作家の先駆け。享和2年(1802)に初版品川~箱根間が出版され、毎年1編ずつ書き上げ、7年後に京都・大阪見物編を。最終編までには初編から20年に及ぶロングセラーになっていた。取材のための旅とお酒好きらしく、職業作家とはいえ貧乏だったらしい。江戸時代を知るにはとても良い資料なのかとも思うが・・私はまだ読破していない。
弥次・喜多は一九の手を離れて全国の共有のアイドルとして扱われ、面白い旅といえば・・弥次・喜多のみが有名になった。実は・・・弥次・喜多は貧相で下品。くだらないいたずらを繰り返し、失敗ばかりする。内容の多くが飯盛り女という旅人相手の女郎買いや夜這いの話。人の小便を間違えて飲んだり、遺骨をかじったりなど汚い話。だから成人向きの本。が当時は庶民の共感を得た時代の本だったと解説にある。理由はこの時代には寺子屋で庶民も文字が読めるようになったこと、しかも自分より下の人として読んでいるうちに、自分の思ってもやれない愚考を代わりにやってくれる弥次と喜多に笑いを見つけたということだと。
ところで亡くなった遺体を火葬にすると、あらかじめ中に仕込んだ花火がドーンとあがって人々をたまげさせたと書かれていた。本当かどうかわからない・・・が、潔い死に方だ。
この世をばどりゃおいとまにせん香の煙とともに灰さようなら
会員様からの寄稿
バレンタインの日に水野彰夫氏語る

34年間アメリカで暮らした水野さん。「日本はチョコレートを男の人が貰うけどアメリカのバレンタインでは奥さんに花束をあげる・・だからこれから奥さんと美味しい刺身を伊豆土肥に食べに行くんです」とまるでそれが水野さん流のプレゼントだよと匂わせた。にっこり笑った奥さんが羨ましかった。
水野さんは元野球選手。昭和49年法政大学に江川卓と一緒に入学した人だ。小学校6年ですでに体が大きくて、同級生より頭一つ分大きかった。親の進めもあって昭和46年静岡高校へ。入学した当時野球部は弱かった。前年16対0で高松商業に敗れる「ボロ負けの戦歴」だった・・そこで時代の先駆けで静岡高校では県内から優れた野球少年を集めた。その中に水野氏がいたと言う訳だ。静高2年生の秋、負け試合を経験する。あとが無い・・と3年になったとき全員が本気100倍の集中力で夏の甲子園に突入。そして・・何と準優勝したのだった。マスコミが大騒ぎ。静岡の高校野球ファンの記憶に残る「静岡×広島商」の戦いだった。
その後静岡高校のメンバーは江川卓などと共に法政大学に入学。花の49年組と呼ばれている。そして怒涛の春・夏・春・夏・春の五連勝がはじまった。
大学では授業に出ただけで野球部の先輩に怒られ、風呂場で水をかけられたり叩かれたりが日常茶飯事にあったそうだ。自分のイメージしていた大学生活とのギャップ。また肩を痛めたり、地元でちやほやされたりの生活の中・・〈本当の自分の力ってどんなものだろう〉と思ったとき、大学を辞めることを決心する。新聞社の知り合いの伝(つて)で、結局アメリカのワトソンビル(カリフォルニア州)に渡り果物を日本に送る仕事に就く。・・40度近いアリゾナの畑の行き止まりの道で立ち往生した。脱水症状で顔や手の皮膚がピリピリ音をたてる中、レモンをかじりコヨーテの声を聞いて助けられた体験。また湾岸戦争終了の2ヶ月後、イスラエルに仕入れに行き戦争のつめ跡のリアルな風景を見.る体験。そしてイスラエル産スウィーティーという緑色の皮の柑橘を買い入れ、日本で流行らせたことも。
7年前日本に帰って高校の野球少年にフリーの立位置で指導をはじめている。言葉かけで技術がより良く変わっていくポイントが分かると語った。
バレンタインの日、大きな体で、やさしい凄い人に会えて嬉しかった。
34年間アメリカで暮らした水野さん。「日本はチョコレートを男の人が貰うけどアメリカのバレンタインでは奥さんに花束をあげる・・だからこれから奥さんと美味しい刺身を伊豆土肥に食べに行くんです」とまるでそれが水野さん流のプレゼントだよと匂わせた。にっこり笑った奥さんが羨ましかった。
水野さんは元野球選手。昭和49年法政大学に江川卓と一緒に入学した人だ。小学校6年ですでに体が大きくて、同級生より頭一つ分大きかった。親の進めもあって昭和46年静岡高校へ。入学した当時野球部は弱かった。前年16対0で高松商業に敗れる「ボロ負けの戦歴」だった・・そこで時代の先駆けで静岡高校では県内から優れた野球少年を集めた。その中に水野氏がいたと言う訳だ。静高2年生の秋、負け試合を経験する。あとが無い・・と3年になったとき全員が本気100倍の集中力で夏の甲子園に突入。そして・・何と準優勝したのだった。マスコミが大騒ぎ。静岡の高校野球ファンの記憶に残る「静岡×広島商」の戦いだった。
その後静岡高校のメンバーは江川卓などと共に法政大学に入学。花の49年組と呼ばれている。そして怒涛の春・夏・春・夏・春の五連勝がはじまった。
大学では授業に出ただけで野球部の先輩に怒られ、風呂場で水をかけられたり叩かれたりが日常茶飯事にあったそうだ。自分のイメージしていた大学生活とのギャップ。また肩を痛めたり、地元でちやほやされたりの生活の中・・〈本当の自分の力ってどんなものだろう〉と思ったとき、大学を辞めることを決心する。新聞社の知り合いの伝(つて)で、結局アメリカのワトソンビル(カリフォルニア州)に渡り果物を日本に送る仕事に就く。・・40度近いアリゾナの畑の行き止まりの道で立ち往生した。脱水症状で顔や手の皮膚がピリピリ音をたてる中、レモンをかじりコヨーテの声を聞いて助けられた体験。また湾岸戦争終了の2ヶ月後、イスラエルに仕入れに行き戦争のつめ跡のリアルな風景を見.る体験。そしてイスラエル産スウィーティーという緑色の皮の柑橘を買い入れ、日本で流行らせたことも。
7年前日本に帰って高校の野球少年にフリーの立位置で指導をはじめている。言葉かけで技術がより良く変わっていくポイントが分かると語った。
バレンタインの日、大きな体で、やさしい凄い人に会えて嬉しかった。