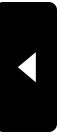会員様からの寄稿
小野小町(おののこまち)の姿見の橋

岡部に「小野小町姿見の橋」がある。知ったのは観光ボランティアになった時。こんな小さな橋が有名なのか・・と不思議に思ったり、本心では作り話かもと思ったりした。でも絵入りで地元の観光用パンフレットにのっていて、その橋の傍に石で作られた案内板もある。
岡部の昔話を要約すると〈晩年に東国へ下る途中、岡部宿に泊まった。その時、この橋に立って下を流れる川の水面に自分の姿を映し、長旅で疲れた自分の姿を見て、過ぎし日の面影を失ってしまった自分の老いを嘆き悲しんだ〉という内容。
花の色は 移りにけりな いたづらに
わが身世にふる ながめせしまに
小町の歌からイメージを広げた物語かも。
ボランティア案内には工夫を凝らさねばと思ったがなかなか良い案が浮かばなかった。まず小野小町の姿をインターネットで探してみた。十二単を着た絵が存在した。そこで浮かんだアイデアは・・羽織を着て「小町は水に映る自分の哀れな姿におよよと泣いた」と言いながら泣き崩れるシーンを思いついた。本番では自前の羽織を数着用意した。まず私が演じて見せた。続いて観光客に羽織を選んで着てもらい、同じように演じてもらった。
周りの応援団に笑いがおこり、楽しんでいただけた。写真を撮る人もいたので良い思い出になるといいなーと思っている。
小野小町の伝説は日本のあちこちにある。それも本当に不思議。股のぞきで有名な天(あまの)橋立(はしだて)で、小町が着物のすそをめくって小用をした時偶然目にした絶景が天橋立。その後股のぞきがはやったと聞いていた。私も股のぞきを体験したが光に輝く美しい風景が目に残っている。小町は晩年に都を離れ天橋立を目指し五十河(いかが・現在の京丹後市大宮町)で亡くなり、小町の墓と伝えられる小町塚や、小町が開基した妙性寺(山号を小町山という)があり、一帯は小町公園になっている。でも小町のお墓は日本に10ヶ所以上もあるのだ。私には何が真実かはわからない・・・。
西行法師と小野小町伝説の多さは何故なのだろう。当時の人々は有名な人の顔を知るすべが無い。ただ名前は伝わっていただろう。ヒーローやヒロイン。そんな名前を使って、岡部の人も説得力のある物語をつくったんじゃないのだろうか。日々の暮らしにスパイスを!!!!なのか? 小町がこの岡部を歩いたことを想像するだけでも優雅な気持ちになる。
岡部に「小野小町姿見の橋」がある。知ったのは観光ボランティアになった時。こんな小さな橋が有名なのか・・と不思議に思ったり、本心では作り話かもと思ったりした。でも絵入りで地元の観光用パンフレットにのっていて、その橋の傍に石で作られた案内板もある。
岡部の昔話を要約すると〈晩年に東国へ下る途中、岡部宿に泊まった。その時、この橋に立って下を流れる川の水面に自分の姿を映し、長旅で疲れた自分の姿を見て、過ぎし日の面影を失ってしまった自分の老いを嘆き悲しんだ〉という内容。
花の色は 移りにけりな いたづらに
わが身世にふる ながめせしまに
小町の歌からイメージを広げた物語かも。
ボランティア案内には工夫を凝らさねばと思ったがなかなか良い案が浮かばなかった。まず小野小町の姿をインターネットで探してみた。十二単を着た絵が存在した。そこで浮かんだアイデアは・・羽織を着て「小町は水に映る自分の哀れな姿におよよと泣いた」と言いながら泣き崩れるシーンを思いついた。本番では自前の羽織を数着用意した。まず私が演じて見せた。続いて観光客に羽織を選んで着てもらい、同じように演じてもらった。
周りの応援団に笑いがおこり、楽しんでいただけた。写真を撮る人もいたので良い思い出になるといいなーと思っている。
小野小町の伝説は日本のあちこちにある。それも本当に不思議。股のぞきで有名な天(あまの)橋立(はしだて)で、小町が着物のすそをめくって小用をした時偶然目にした絶景が天橋立。その後股のぞきがはやったと聞いていた。私も股のぞきを体験したが光に輝く美しい風景が目に残っている。小町は晩年に都を離れ天橋立を目指し五十河(いかが・現在の京丹後市大宮町)で亡くなり、小町の墓と伝えられる小町塚や、小町が開基した妙性寺(山号を小町山という)があり、一帯は小町公園になっている。でも小町のお墓は日本に10ヶ所以上もあるのだ。私には何が真実かはわからない・・・。
西行法師と小野小町伝説の多さは何故なのだろう。当時の人々は有名な人の顔を知るすべが無い。ただ名前は伝わっていただろう。ヒーローやヒロイン。そんな名前を使って、岡部の人も説得力のある物語をつくったんじゃないのだろうか。日々の暮らしにスパイスを!!!!なのか? 小町がこの岡部を歩いたことを想像するだけでも優雅な気持ちになる。
白日会 静岡水彩展 お知らせ
会員様からの寄稿
近代土木遺産(兵庫県美方郡)
余部(あまるべ)橋梁(きょうりょう)

今回山陰本線(単線鉄道)で国道178号を跨ぐ橋梁を通る無人の餘部駅(あまるべえき)を偶然知った。旅行の途中トイレタイムで気軽に寄った道の駅で車を降りたとき、右の方角から沢山の人がマイクロバスへ戻ってきたので、「何かあるんですか?」と聞くと「空の駅があるんですよ」と教えてもらった。愛称余部クリスタルタワーの透明な箱型のエレベターから人が降りていた。高さは40㍍程。エレベーターの中から海も見渡せるかっこいいものだ。面白そうと乗ってみた。降りると、そこが「空の駅」だった。駅長は「かめだ そら」レールがあってその上を歩けるようになっていた。
餘部駅は今でも餘が難しい漢字だ。道の駅は平仮名で「あまるべ」。橋の名前は「余部」。ちょっと戸惑う。昭和34年、駅までの道とプラットホームをつくるために地元の子供達が海岸から石を運び上げて出来た駅。エレベーターができるまでは下から歩いて空の駅まで歩いたのだ。でも大きな鉄道事故が昭和61年に起きた。そんな昔のことではないが知らなかった。余部橋梁の雄姿と事故の教訓を何らかの形で後世に伝えいくことが求められて、一部を取り壊さずに餘部駅寄りの3本の橋脚と桁を残して鉄橋の展望台になったという訳だ。平成22年に余部橋梁が完成し、今回乗ったエレベーターは平成29年11月に完成したばかりだった。まだ1ヶ月たったばかり。ラッキーなタイミングだった。
どんな線路も実際に使われているところでは歩くのは禁止になっている。だから実際は現在の本線の横に元々あった線路を68㍍だけ残していて、歩けるようにしたのだ。20分程すると本当の列車が来る事がわかってプラットホームに立って待った。私は車人間なので、山陰本線は一度も乗ったことが無い。撮り鉄の男の人達がカメラを構えていて人気のある場所みたいだった。鈍空の下に海も見えて日本海なんだとしみじみ思った。
昔の列車の橋梁は電車からペットボトルを投げると40㍍下の道路に落ちたらしい。冬では橋梁に付いた雪も落下したという。そこで今回新しい橋梁は物が落ちない構造にしたという。
列車が出発すると自然に手を振っていた。列車の人も振ってくれた。旅の思い出はこんなことでも出来ていると思った。
余部(あまるべ)橋梁(きょうりょう)
今回山陰本線(単線鉄道)で国道178号を跨ぐ橋梁を通る無人の餘部駅(あまるべえき)を偶然知った。旅行の途中トイレタイムで気軽に寄った道の駅で車を降りたとき、右の方角から沢山の人がマイクロバスへ戻ってきたので、「何かあるんですか?」と聞くと「空の駅があるんですよ」と教えてもらった。愛称余部クリスタルタワーの透明な箱型のエレベターから人が降りていた。高さは40㍍程。エレベーターの中から海も見渡せるかっこいいものだ。面白そうと乗ってみた。降りると、そこが「空の駅」だった。駅長は「かめだ そら」レールがあってその上を歩けるようになっていた。
餘部駅は今でも餘が難しい漢字だ。道の駅は平仮名で「あまるべ」。橋の名前は「余部」。ちょっと戸惑う。昭和34年、駅までの道とプラットホームをつくるために地元の子供達が海岸から石を運び上げて出来た駅。エレベーターができるまでは下から歩いて空の駅まで歩いたのだ。でも大きな鉄道事故が昭和61年に起きた。そんな昔のことではないが知らなかった。余部橋梁の雄姿と事故の教訓を何らかの形で後世に伝えいくことが求められて、一部を取り壊さずに餘部駅寄りの3本の橋脚と桁を残して鉄橋の展望台になったという訳だ。平成22年に余部橋梁が完成し、今回乗ったエレベーターは平成29年11月に完成したばかりだった。まだ1ヶ月たったばかり。ラッキーなタイミングだった。
どんな線路も実際に使われているところでは歩くのは禁止になっている。だから実際は現在の本線の横に元々あった線路を68㍍だけ残していて、歩けるようにしたのだ。20分程すると本当の列車が来る事がわかってプラットホームに立って待った。私は車人間なので、山陰本線は一度も乗ったことが無い。撮り鉄の男の人達がカメラを構えていて人気のある場所みたいだった。鈍空の下に海も見えて日本海なんだとしみじみ思った。
昔の列車の橋梁は電車からペットボトルを投げると40㍍下の道路に落ちたらしい。冬では橋梁に付いた雪も落下したという。そこで今回新しい橋梁は物が落ちない構造にしたという。
列車が出発すると自然に手を振っていた。列車の人も振ってくれた。旅の思い出はこんなことでも出来ていると思った。
会員様からの寄稿
産経新聞
「家族がいてもいなくても」 久田恵

新聞のエッセイのタイトルは「家族がいてもいなくても」。大好きでいつも楽しく読んでいる。わくわくしながら久田さんのリアルの文にのめりこむ。「家族がいてもいなくても」というタイトルが凄い立ち位置。家族がいる私だけれど、いない自分を想像して考えるシュミレーションの発想も自然に思わせてくれた。そして自分も家族に縛られない部分でまだまだいろんな体験をしなくちゃとか、家族でいる時間は感謝と共に大切にする体験にしなくてはとエネルギーに変換している。
久田さんは1947年生まれ。信条は「ファンタスティックに生きる」。こんなせりふを堂々と言えるなんて羨ましい。離婚後に子連れで入ったサーカス団での体験をまとめた『サーカス村裏通り』で大宅壮一ノンフィクション賞候補になり、1990年『フィリピーナを愛した男たち』により第21回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。
インターネットで久田さんを検索してみた。素敵な顔立ちには生き様までがきざまれていて自信に満ち光り輝いていた。同じ女として心のキャパの広さを身につけたいと・・エッセイの言葉を道しるべに思って最近の私は生活している。
2017/12/21 528回目なのだと思うが・・その文を読んで見ると、今の自分と今の日本の現状と自分自身の生き様に関係しているなーと思った文があった。『これから団塊の世代が高齢者になっていった時代にどうなるか・・略・・お世話してくれるのを待つのでなくて、自らがどんな介護を受けて どんな老後を暮らして どんなふうにしていくかということを、自分たちが実践してゆく時代に入っているんじゃないかなあと思います』という内容だった。介護の現場で働く人たちのインタビューを続け、どんな思いで働いているのかしら?と目標は100人。2年間インタビューを続けて既に目標を達成していたとある。目標という言葉に・・あっ目標が大切なんだと強く意識した。子育て時代は怪我も無く大きくしなくてはと目標があった。でもその後はっきりした目標を考えないで生きてきた。生きるだけなら出来たのだ。人を裏切らないでいるとかの漠然とした生き様はあったが、はっきり目標があれば知恵を出して乗り越えられるだろう。
久田恵さんにいつか逢えるといいな。逢いたい。
「家族がいてもいなくても」 久田恵
新聞のエッセイのタイトルは「家族がいてもいなくても」。大好きでいつも楽しく読んでいる。わくわくしながら久田さんのリアルの文にのめりこむ。「家族がいてもいなくても」というタイトルが凄い立ち位置。家族がいる私だけれど、いない自分を想像して考えるシュミレーションの発想も自然に思わせてくれた。そして自分も家族に縛られない部分でまだまだいろんな体験をしなくちゃとか、家族でいる時間は感謝と共に大切にする体験にしなくてはとエネルギーに変換している。
久田さんは1947年生まれ。信条は「ファンタスティックに生きる」。こんなせりふを堂々と言えるなんて羨ましい。離婚後に子連れで入ったサーカス団での体験をまとめた『サーカス村裏通り』で大宅壮一ノンフィクション賞候補になり、1990年『フィリピーナを愛した男たち』により第21回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。
インターネットで久田さんを検索してみた。素敵な顔立ちには生き様までがきざまれていて自信に満ち光り輝いていた。同じ女として心のキャパの広さを身につけたいと・・エッセイの言葉を道しるべに思って最近の私は生活している。
2017/12/21 528回目なのだと思うが・・その文を読んで見ると、今の自分と今の日本の現状と自分自身の生き様に関係しているなーと思った文があった。『これから団塊の世代が高齢者になっていった時代にどうなるか・・略・・お世話してくれるのを待つのでなくて、自らがどんな介護を受けて どんな老後を暮らして どんなふうにしていくかということを、自分たちが実践してゆく時代に入っているんじゃないかなあと思います』という内容だった。介護の現場で働く人たちのインタビューを続け、どんな思いで働いているのかしら?と目標は100人。2年間インタビューを続けて既に目標を達成していたとある。目標という言葉に・・あっ目標が大切なんだと強く意識した。子育て時代は怪我も無く大きくしなくてはと目標があった。でもその後はっきりした目標を考えないで生きてきた。生きるだけなら出来たのだ。人を裏切らないでいるとかの漠然とした生き様はあったが、はっきり目標があれば知恵を出して乗り越えられるだろう。
久田恵さんにいつか逢えるといいな。逢いたい。
友の会会員向けフロアレクチャー
『屏風爛漫』展2019.4.2~5.6 友の会レクチャー(4/27)
屏風は中国発祥で大陸から朝鮮を経由して日本に伝わったとされるが当時の中国製の屏風は日本で観ることは出来ないとのこと。
柱中心でふすまや障子等の建具を多く使う日本建築は壁が少ないため、仕切りや風よけの役目も果たす屏風が独自に発展し易かったのか。
折り曲げることで自立できる屏風は、折り曲げ方や一対の屏風の並べ方に変化をつけて自由に楽しむ余地を与えてくれる。
石上学芸員さんの解説でこれまで知らなかった屏風の特徴や楽しみ方を味わいながら巡ることができた。
狩野探幽作『一ノ谷合戦・二度之懸図屏風』…屏風の右側には大急ぎで馬を走らす武者…屏風の折れ目の山が二つ重なりその先は見えない…左へ移動していくと誰かに刀を振りかざす武者二人…さらに左へ進むと敵と戦う若武者…物語のクライマックスへと誘う屏風の魅力がダイレクトに感じ取れた。

屏風は中国発祥で大陸から朝鮮を経由して日本に伝わったとされるが当時の中国製の屏風は日本で観ることは出来ないとのこと。
柱中心でふすまや障子等の建具を多く使う日本建築は壁が少ないため、仕切りや風よけの役目も果たす屏風が独自に発展し易かったのか。
折り曲げることで自立できる屏風は、折り曲げ方や一対の屏風の並べ方に変化をつけて自由に楽しむ余地を与えてくれる。
石上学芸員さんの解説でこれまで知らなかった屏風の特徴や楽しみ方を味わいながら巡ることができた。
狩野探幽作『一ノ谷合戦・二度之懸図屏風』…屏風の右側には大急ぎで馬を走らす武者…屏風の折れ目の山が二つ重なりその先は見えない…左へ移動していくと誰かに刀を振りかざす武者二人…さらに左へ進むと敵と戦う若武者…物語のクライマックスへと誘う屏風の魅力がダイレクトに感じ取れた。

会員様からの寄稿
安倍川町の遊女が繁盛して・・

家康」のDVDを見ている。関が原の戦いを征して天下人になる流れの中で、津川雅彦が演じている古いDVDだ。静岡では平成27年(2015) 家康公400年祭があり、歴史が苦手な私も「大御所四百年祭推進室」専門員の黒沢氏が制作した情報を真剣に読んでいた。安倍川の川原でたくさんのキリシタンを殺させたこと・岡部の朝比奈氏に「朝比奈粽をつくれ」と献上させたこと・麻機レンコンが好きなこと・葵の紋に似た葉の形の有東木(うとうぎ)の山葵(わさび)を門外不出にしたこと・熱海の温泉が好きで子供達を連れていったことなどなどが記憶に残っている。また駿河土産巻の二の一〇の中に安倍川町の遊女が繁盛しており町奉行へ仰せ付け踊りを上覧のことの記述
『権現様が駿河へご隠居なされた以後の事、安倍川町の傾城などが近いため、旗本の若い人々が遊女町へ通ってくる事が評判となり、時の駿府町奉行の彦坂九兵衛は安倍川町を二三里離れた遠くへ移転させたい旨申し上げました。・・「其方は安倍川町を二三里も遠い所へ移転させるべきと言うが、安倍川町に居る遊女は売物ではないのか、売物であれば全てのものが同じはずでその様な遠い所へ移しては安倍川の者達は生計の立て様がない筈である。従来通りの場所に置くように」と。その後安倍川の繁盛は今までに倍して盛んになり (略)・・ 二丁町は日本最古の公認遊郭で、貧富の差が性を商品化した悪所である。現在は静岡県地震防災センターがある場所で、1万坪の面積だった。駿府城下の町が96あり、その内7箇所が遊郭だった。でも第二次世界大戦の空襲で焼失している。
今駿府城跡天守台発掘現場での写真が新聞に掲載される回数が増えてきている。平成最後の年、駿府本丸の出入り口や豊臣秀吉が家臣に築かせた”秀吉の城 ”の遺構が発見されたばかりなのだ。家康と秀吉が関わった二つの天守台がずれてはいてもほとんど同じ場所に現存していたこともびっくりだ。見学会も開かれている。
DVDでは秀吉政権を翻弄し、政権を家康がぶんどっていく過程の物語だ。
歴史物語にではなく、現実の巨大城郭の石にはわくわくする。これからどんな調査が勧められるのか。そして何が分かってくるのか。楽しみである
家康」のDVDを見ている。関が原の戦いを征して天下人になる流れの中で、津川雅彦が演じている古いDVDだ。静岡では平成27年(2015) 家康公400年祭があり、歴史が苦手な私も「大御所四百年祭推進室」専門員の黒沢氏が制作した情報を真剣に読んでいた。安倍川の川原でたくさんのキリシタンを殺させたこと・岡部の朝比奈氏に「朝比奈粽をつくれ」と献上させたこと・麻機レンコンが好きなこと・葵の紋に似た葉の形の有東木(うとうぎ)の山葵(わさび)を門外不出にしたこと・熱海の温泉が好きで子供達を連れていったことなどなどが記憶に残っている。また駿河土産巻の二の一〇の中に安倍川町の遊女が繁盛しており町奉行へ仰せ付け踊りを上覧のことの記述
『権現様が駿河へご隠居なされた以後の事、安倍川町の傾城などが近いため、旗本の若い人々が遊女町へ通ってくる事が評判となり、時の駿府町奉行の彦坂九兵衛は安倍川町を二三里離れた遠くへ移転させたい旨申し上げました。・・「其方は安倍川町を二三里も遠い所へ移転させるべきと言うが、安倍川町に居る遊女は売物ではないのか、売物であれば全てのものが同じはずでその様な遠い所へ移しては安倍川の者達は生計の立て様がない筈である。従来通りの場所に置くように」と。その後安倍川の繁盛は今までに倍して盛んになり (略)・・ 二丁町は日本最古の公認遊郭で、貧富の差が性を商品化した悪所である。現在は静岡県地震防災センターがある場所で、1万坪の面積だった。駿府城下の町が96あり、その内7箇所が遊郭だった。でも第二次世界大戦の空襲で焼失している。
今駿府城跡天守台発掘現場での写真が新聞に掲載される回数が増えてきている。平成最後の年、駿府本丸の出入り口や豊臣秀吉が家臣に築かせた”秀吉の城 ”の遺構が発見されたばかりなのだ。家康と秀吉が関わった二つの天守台がずれてはいてもほとんど同じ場所に現存していたこともびっくりだ。見学会も開かれている。
DVDでは秀吉政権を翻弄し、政権を家康がぶんどっていく過程の物語だ。
歴史物語にではなく、現実の巨大城郭の石にはわくわくする。これからどんな調査が勧められるのか。そして何が分かってくるのか。楽しみである
会員様からの寄稿
大人の遠足
厳島神社

Panasonicエボルタ電池のコマーシャルが流れた。今回はエボルタNEOくんが広島宮島口から2,5㌔離れた厳島神社まで泳ぐというものだった。世界最長達成チャレンジ編。赤い鳥居がきっと外国でも受けるだろうというCMクリエーターの戦略が感じられた。ロボットクリエーター高橋智隆には、静岡県立美術館の「ロボットと美術」のオープニングで会った。2010年の企画。当時は東海道を歩く企画もあり、岡部大旅籠の前をかわいいエボルタが歩くという企画もあり、とても身近に感じていたロボットだ。
そのコマーシャルの厳島神社に出かけてみた。ユネスコ世界遺産。厳島は神に斎(いつく=仕える)島で、島そのものが神として信仰されている。あの有名な平清盛の氏神さま。

朝早く引き潮だった。島に向かうフェリーの中で隣に座ったおばさんが「お店屋さんの助っ人で働きに行くところ。昔は猿が観光客にいたづらをしたが今はもういない」と話していた。フェリーを降りて右に折れ大鳥居に向かった。途中で「一緒に写真におさまって」と若い女の人に声をかけられた。日本語が上手なアジア系の外国人だった。鳥居に繋がる海の際が歩けるようになっていた。透き通るような青い薄い海草のあおさがたくさん波打ち際にあった。あおさを踏まないで鳥居に近づくと想像していたより硬い砂で、靴でも大丈夫だった。お金が撒き散らされていた。日本円でなく私の知らないお金だった。鳥居の赤が少しはげていて、主柱はクスノキの自然木。堂々としていて貫禄だった。近づけて見るなんて想像していなかったので良かったと思った。木が侵食されていて、木目の隙間にもお金が挟まれていた。幸せを祈る行為がお金を撒くのは世界共通かもしれない。若い頃ローマのトレビの泉でお金を投げたことを思い出した。でもここ厳島ではどうもやめて欲しい行為らしい。
『伊都岐島神社』の扁額が大鳥居の真ん中に掛かっていた。沖合い200㍍なので満潮の海水との高低さが想像以上だ。海水の上昇まで居たかったが、満ち欠けの6時間を費やすのはちょっと大変なので諦めた。ロープウェイで島の頂上まで上り、凪の海を見て今年の幸せを祈った。
厳島神社
Panasonicエボルタ電池のコマーシャルが流れた。今回はエボルタNEOくんが広島宮島口から2,5㌔離れた厳島神社まで泳ぐというものだった。世界最長達成チャレンジ編。赤い鳥居がきっと外国でも受けるだろうというCMクリエーターの戦略が感じられた。ロボットクリエーター高橋智隆には、静岡県立美術館の「ロボットと美術」のオープニングで会った。2010年の企画。当時は東海道を歩く企画もあり、岡部大旅籠の前をかわいいエボルタが歩くという企画もあり、とても身近に感じていたロボットだ。
そのコマーシャルの厳島神社に出かけてみた。ユネスコ世界遺産。厳島は神に斎(いつく=仕える)島で、島そのものが神として信仰されている。あの有名な平清盛の氏神さま。
朝早く引き潮だった。島に向かうフェリーの中で隣に座ったおばさんが「お店屋さんの助っ人で働きに行くところ。昔は猿が観光客にいたづらをしたが今はもういない」と話していた。フェリーを降りて右に折れ大鳥居に向かった。途中で「一緒に写真におさまって」と若い女の人に声をかけられた。日本語が上手なアジア系の外国人だった。鳥居に繋がる海の際が歩けるようになっていた。透き通るような青い薄い海草のあおさがたくさん波打ち際にあった。あおさを踏まないで鳥居に近づくと想像していたより硬い砂で、靴でも大丈夫だった。お金が撒き散らされていた。日本円でなく私の知らないお金だった。鳥居の赤が少しはげていて、主柱はクスノキの自然木。堂々としていて貫禄だった。近づけて見るなんて想像していなかったので良かったと思った。木が侵食されていて、木目の隙間にもお金が挟まれていた。幸せを祈る行為がお金を撒くのは世界共通かもしれない。若い頃ローマのトレビの泉でお金を投げたことを思い出した。でもここ厳島ではどうもやめて欲しい行為らしい。
『伊都岐島神社』の扁額が大鳥居の真ん中に掛かっていた。沖合い200㍍なので満潮の海水との高低さが想像以上だ。海水の上昇まで居たかったが、満ち欠けの6時間を費やすのはちょっと大変なので諦めた。ロープウェイで島の頂上まで上り、凪の海を見て今年の幸せを祈った。
会員様からの寄稿
ラコリーナ近江八幡「人と自然がふれあう空間づくり」

藤森氏は天竜にある「秋野不矩美術館」を建築した人ということで知っていた。秋野不矩さんが生前「友達なので頼んでみたの」と言っていたからだ。どんな人かなーと興味はずっと持っていた。その後「ねむの木こども美術館」も関係したと知ってねむの木の美術館も訪ねた。
世界お茶祭り。2016年グランシップで藤森氏が「茶室」の講演をすると知り、出かけてみた。・・2階映像ホールで『茶室』についての話だった。自然の素材を建築にどう生かすかという風なツリーハウスの映像。その他の映像も私の感覚を超えていて、心に残っていた。飄々とした風情の先生だった。
その藤森氏が建築した《ラコリーナ近江八幡》に静岡県立美術館友の会の旅行で訪ねた。ラコリーナはイタリア語。丘という意味で3万5千坪の土地。何と言うことでしよう。このスケールと美しさ。感動した。メインショップの〈草屋根〉のネイミングも素敵。屋根から雫が・・。屋根の草が生きていくための水なのだが、その雫が私の心を浄化していく。建物の周りの草原の庭は草丈のバランスが・・種から蒔いたと思うが、高く伸びているものが無く、膝丈に統一されている。笹や雑草かも知れないが、統一された草たち。バランスがきれい。
昔八ヶ岳の柳生博氏の八ヶ岳倶楽部に出かけたことを思い出した。自然を愛する気持ちは一緒。建物の屋根に草が生えていて、花が咲いている姿を見ながら食事をした。屋根に咲く花がかわいい。自然の草をこんなに愛せる人がいることが羨ましい。
ラコリーナの〈鎮守の森〉構想。転勤族の私には心の鎮守の森はあっても、本当の地元がない。土地が人に力を与える。どんなときも「ここにいていいよ」と包んでくれる場所。それはすべて心の・・という場所だ。
広島県福山市にある神勝寺の寺務所「松堂」も藤森さんが設計している。手曲げ銅版で葺いた屋根の上に赤松の木があり、土壁の色彩がラコリーナと一緒で、自然に溶け込んでいた。藤森さんが筆で「松堂」と書いた文字が額の中でおさまっていた。骨太でもなく女々しくも無く素朴で優しい文字だった。
藤森氏は天竜にある「秋野不矩美術館」を建築した人ということで知っていた。秋野不矩さんが生前「友達なので頼んでみたの」と言っていたからだ。どんな人かなーと興味はずっと持っていた。その後「ねむの木こども美術館」も関係したと知ってねむの木の美術館も訪ねた。
世界お茶祭り。2016年グランシップで藤森氏が「茶室」の講演をすると知り、出かけてみた。・・2階映像ホールで『茶室』についての話だった。自然の素材を建築にどう生かすかという風なツリーハウスの映像。その他の映像も私の感覚を超えていて、心に残っていた。飄々とした風情の先生だった。
その藤森氏が建築した《ラコリーナ近江八幡》に静岡県立美術館友の会の旅行で訪ねた。ラコリーナはイタリア語。丘という意味で3万5千坪の土地。何と言うことでしよう。このスケールと美しさ。感動した。メインショップの〈草屋根〉のネイミングも素敵。屋根から雫が・・。屋根の草が生きていくための水なのだが、その雫が私の心を浄化していく。建物の周りの草原の庭は草丈のバランスが・・種から蒔いたと思うが、高く伸びているものが無く、膝丈に統一されている。笹や雑草かも知れないが、統一された草たち。バランスがきれい。
昔八ヶ岳の柳生博氏の八ヶ岳倶楽部に出かけたことを思い出した。自然を愛する気持ちは一緒。建物の屋根に草が生えていて、花が咲いている姿を見ながら食事をした。屋根に咲く花がかわいい。自然の草をこんなに愛せる人がいることが羨ましい。
ラコリーナの〈鎮守の森〉構想。転勤族の私には心の鎮守の森はあっても、本当の地元がない。土地が人に力を与える。どんなときも「ここにいていいよ」と包んでくれる場所。それはすべて心の・・という場所だ。
広島県福山市にある神勝寺の寺務所「松堂」も藤森さんが設計している。手曲げ銅版で葺いた屋根の上に赤松の木があり、土壁の色彩がラコリーナと一緒で、自然に溶け込んでいた。藤森さんが筆で「松堂」と書いた文字が額の中でおさまっていた。骨太でもなく女々しくも無く素朴で優しい文字だった。
常葉大学造形学部造形学科 卒業制作展
平成30年度 常葉大学造形学部造形学科 卒業制作展
夢、さめる。
平成31年2月22日(金)~24日(日)
10:00~18:00 最終日は16:00まで
グランシップ 6F・7F
友の会実技講座「面相筆で野菜を描こう」でお手伝いいただいた
常葉大学の学生さんたちの作品も出展されています。
夢、さめる。
平成31年2月22日(金)~24日(日)
10:00~18:00 最終日は16:00まで
グランシップ 6F・7F
友の会実技講座「面相筆で野菜を描こう」でお手伝いいただいた
常葉大学の学生さんたちの作品も出展されています。
会員様からの寄稿
宇津ノ谷隧道群
土木遺産に認定
銭取トンネルは日本で始めて

「土木遺産」という言葉を初めて知った。土木遺産は幕末から明治初期に完成した近代土木遺産の保存やまちづくりへの活用を目的に、土木学会が認定するものらしい。そして宇津ノ谷隧道群が認定された。
私の住む岡部に有名な明治のトンネルがある。明治のトンネルは賃撮りトンネルとしてスタートした。また明治、大正、昭和、平成の各時代に建設されたトンネルが通行可能な状態で存在している。日本でも珍しいのだ。そういうことが評価された結果だという。そのトンネルが平成30年11月に近代土木遺産(Modern civil engineering heritage )に認定されたのだ。
文明開化の波が道路にも押し寄せ、車(人力車・荷車)の通れる道の開拓が行われるようになった。岡部宿の杉山喜平次・仁藤延吉や丸子宿の水谷九郎平など7人は、静岡の宮崎総吾を総括として測量は焼津の数学家古谷道生が担当し、石工人頭には山崎伊十郎を当てて工事に取り掛かった。ここの渓谷は小規模だけど地形が急峻な為、難工事だったらしい。そして明治9年に「宇津ノ谷隋道を東海道本道にとする」布告がでて、昭憲皇太后が通った。
大正トンネルが出来るまでの55年間、
日本の陸上交通における大動脈としての役割を果たすことになる。
道銭
人1人 6厘
荷場1疋 1銭2厘
駕籠1挺 1銭5厘
大荷車 3銭2厘
小荷車 2銭1厘
お金を取ってトンネルを通ったのだ。
岡部に住んで間もない40年前トンネルの中は水溜りが出来ていた。ごみも散らかり放題で汚かった。どんなところかと通ってみたい好奇心があっても1人では怖くてやめたことがある。ただ暑い夏はトンネルの中は少しヒヤッとして気持ち良かったことは思い出す。
それがトンネルの中で展覧会をやってみたいという人が現れる環境になった。他には水窪の峠で有名な国取り綱引きみたいに、静岡と藤枝でとりっこの綱引きの案も浮上している。まだ実現はしていない。許可のハードルは高いらしい。東海道の発展に役立った古道が別の生かされ方になるのもアイデア次第なのか。
土木遺産に認定
銭取トンネルは日本で始めて
「土木遺産」という言葉を初めて知った。土木遺産は幕末から明治初期に完成した近代土木遺産の保存やまちづくりへの活用を目的に、土木学会が認定するものらしい。そして宇津ノ谷隧道群が認定された。
私の住む岡部に有名な明治のトンネルがある。明治のトンネルは賃撮りトンネルとしてスタートした。また明治、大正、昭和、平成の各時代に建設されたトンネルが通行可能な状態で存在している。日本でも珍しいのだ。そういうことが評価された結果だという。そのトンネルが平成30年11月に近代土木遺産(Modern civil engineering heritage )に認定されたのだ。
文明開化の波が道路にも押し寄せ、車(人力車・荷車)の通れる道の開拓が行われるようになった。岡部宿の杉山喜平次・仁藤延吉や丸子宿の水谷九郎平など7人は、静岡の宮崎総吾を総括として測量は焼津の数学家古谷道生が担当し、石工人頭には山崎伊十郎を当てて工事に取り掛かった。ここの渓谷は小規模だけど地形が急峻な為、難工事だったらしい。そして明治9年に「宇津ノ谷隋道を東海道本道にとする」布告がでて、昭憲皇太后が通った。
大正トンネルが出来るまでの55年間、
日本の陸上交通における大動脈としての役割を果たすことになる。
道銭
人1人 6厘
荷場1疋 1銭2厘
駕籠1挺 1銭5厘
大荷車 3銭2厘
小荷車 2銭1厘
お金を取ってトンネルを通ったのだ。
岡部に住んで間もない40年前トンネルの中は水溜りが出来ていた。ごみも散らかり放題で汚かった。どんなところかと通ってみたい好奇心があっても1人では怖くてやめたことがある。ただ暑い夏はトンネルの中は少しヒヤッとして気持ち良かったことは思い出す。
それがトンネルの中で展覧会をやってみたいという人が現れる環境になった。他には水窪の峠で有名な国取り綱引きみたいに、静岡と藤枝でとりっこの綱引きの案も浮上している。まだ実現はしていない。許可のハードルは高いらしい。東海道の発展に役立った古道が別の生かされ方になるのもアイデア次第なのか。