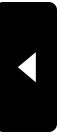会員様からの寄稿
コレクション

私の唯一のコレクション。作品でもある。骨董屋の片隅で見つけたボロボロの藍の刺し子と染めで座布団ほどの大きさの塊。紐で縛られていた。染めが藍の古布だったので手に入れた。家に帰ってまずそうっと紐を解いた。破れた半纏(はんてん)に包まれて下着の股引(ももひき)があらわれた。びっくりぽんだ。包んでまるめてあったが・・広げたときにそんなものが入っているなんて想像外だった。それからは洗濯機で洗いの作業に。勿論股引は捨てた。
半纏の形があったので、解いて平らな布にもどした。ばらばらになった布は重なった部分はまだ藍の色が濃かった。何故かその色に癒されていた。使い切った半纏には刺し子がしてあったが、それでも布の表面は溶け始めていた。布が溶けるなんて凄いことだ。刺し子の糸でかろうじて布に留まっているという状態だった。めげずに一枚のタペストリー風の敷物の形に挑戦した。外側に濃い色がくるように組み合わせていくことも難しかったが、まとめていくことが私の色彩感を磨く修行だと思った。藍の色彩の風化していく色が美しかったのだ。
古布だがここまでボロボロだと捨てられている。だが青森出身の田中忠三郎氏(1933~2013)がそうした古布を収集していた。浅草に「浅草アミューズミュージアム」が出来て展示されていると知った。生活のために破れたら縫って着て、また破れたら縫って着て・・そうして暮らした人達はそれを知られることを恥じていて・・田中氏が収集しなかったら残っていないものだったのだ。2009年に開館した私設美術館に岩手出身の森下さんと一緒に見に出かけてみた。こうした布は 寺山修二「田園に死す」・黒澤明「夢」という映画に使われたことも知った。また2013年春夏パリ・メンズコレクション/2014年春夏ニューヨークコレクション/2015年春夏コレクションで私の大好きなコム デ ギャルソンも展覧会をしていた。 ぼろ=BORO をモチーフにして。そして『BORO』展 も十和田市現代美術館でも2014に開かれていたことも知った。
藍の風化の色彩の美しさは芸術だと思う。布に魅かれる私がいる。藍は日本人の心に浸透しているので大事にしていきたい。2019年3月に閉館の噂がある。コレクションはどうなっちゃうんだろう。
私の唯一のコレクション。作品でもある。骨董屋の片隅で見つけたボロボロの藍の刺し子と染めで座布団ほどの大きさの塊。紐で縛られていた。染めが藍の古布だったので手に入れた。家に帰ってまずそうっと紐を解いた。破れた半纏(はんてん)に包まれて下着の股引(ももひき)があらわれた。びっくりぽんだ。包んでまるめてあったが・・広げたときにそんなものが入っているなんて想像外だった。それからは洗濯機で洗いの作業に。勿論股引は捨てた。
半纏の形があったので、解いて平らな布にもどした。ばらばらになった布は重なった部分はまだ藍の色が濃かった。何故かその色に癒されていた。使い切った半纏には刺し子がしてあったが、それでも布の表面は溶け始めていた。布が溶けるなんて凄いことだ。刺し子の糸でかろうじて布に留まっているという状態だった。めげずに一枚のタペストリー風の敷物の形に挑戦した。外側に濃い色がくるように組み合わせていくことも難しかったが、まとめていくことが私の色彩感を磨く修行だと思った。藍の色彩の風化していく色が美しかったのだ。
古布だがここまでボロボロだと捨てられている。だが青森出身の田中忠三郎氏(1933~2013)がそうした古布を収集していた。浅草に「浅草アミューズミュージアム」が出来て展示されていると知った。生活のために破れたら縫って着て、また破れたら縫って着て・・そうして暮らした人達はそれを知られることを恥じていて・・田中氏が収集しなかったら残っていないものだったのだ。2009年に開館した私設美術館に岩手出身の森下さんと一緒に見に出かけてみた。こうした布は 寺山修二「田園に死す」・黒澤明「夢」という映画に使われたことも知った。また2013年春夏パリ・メンズコレクション/2014年春夏ニューヨークコレクション/2015年春夏コレクションで私の大好きなコム デ ギャルソンも展覧会をしていた。 ぼろ=BORO をモチーフにして。そして『BORO』展 も十和田市現代美術館でも2014に開かれていたことも知った。
藍の風化の色彩の美しさは芸術だと思う。布に魅かれる私がいる。藍は日本人の心に浸透しているので大事にしていきたい。2019年3月に閉館の噂がある。コレクションはどうなっちゃうんだろう。
会員様からの寄稿
福島浪江町を走る

平成最後の30年11月にマイクロシーベルトの数値が表示されている国道6号線を走った。①窓は開けてはいけない。②車の中の空気は車内循環に切り替える。その2つを守って走った。大きな交差点の所々に監視の人が立っていた。家々はどの家も道路から入れないように、灰色のパイプでバリケードされていた。窓ガラスが割れていて雨が吹き込んで廃屋に近い家もあれば、きれいに保たれて人が住んでいそうに見える家もあった。でも道路の表示版は「帰還困難地域」となっていた。元気な人も自分の家で暮らせない現実の光景だった。
走ったのは晩秋で、樹木の葉たちだけが美しく紅葉していた。目に見えない放射能という魔物は・・・人間を混乱させたが、自然の中の樹木は混乱も無く美しかった。見えない放射能のことを知らされていなければ、平安時代の人が感じたその美しさにもののあわれを感じたように美しかったのだ。でも私の心はあわれを哀れと変換していた。人間の悪意の無い愚かさの結果なのだと感じた。
福島第一原子力発電事故は2011年3月11日。毎年その日になると、テレビから流れる慰霊の映像と共に手を合わせる。事故は地震が原因で、しかも東北の津波では沢山の人が海に流されている。私の弟の死も海に流されているので、すべてが繋がってしまう。人々のそれぞれの想いはそれぞれだと感じるけれど、生き延びている人達の心の哀れは底辺では一緒だと思うのだ。考えたり、感じたり、話したりするだけで涙が溢れる。それでも生き延びた人間は・・魔物とも戦えないで、日々を過ごしている。
実は・・ドライブをもっと楽しく!と書かれた Highway Walker11月号の冊子を常磐自動車の中郷SAで手に入れた。表紙のモデルは福士蒼汰。そんな普通の情報誌なのに・・いわきJCTを通り常磐富岡ICで高速をおりるとき、東北エリアマップ中でピンク色のエリアがあり・・それが帰還困難区域(区域内原則通行不可)エリアの表示だった。自動二輪、原動機付自転車、軽車両及び歩行者については通行できません。と書かれていた。地図の中に普通に書かれていることが・・確かに大切な情報だったけど受け入れにくかった。こんなピンク色の地図表示はいつになれば消えるのか・・と考えながらも走った。
平成最後の30年11月にマイクロシーベルトの数値が表示されている国道6号線を走った。①窓は開けてはいけない。②車の中の空気は車内循環に切り替える。その2つを守って走った。大きな交差点の所々に監視の人が立っていた。家々はどの家も道路から入れないように、灰色のパイプでバリケードされていた。窓ガラスが割れていて雨が吹き込んで廃屋に近い家もあれば、きれいに保たれて人が住んでいそうに見える家もあった。でも道路の表示版は「帰還困難地域」となっていた。元気な人も自分の家で暮らせない現実の光景だった。
走ったのは晩秋で、樹木の葉たちだけが美しく紅葉していた。目に見えない放射能という魔物は・・・人間を混乱させたが、自然の中の樹木は混乱も無く美しかった。見えない放射能のことを知らされていなければ、平安時代の人が感じたその美しさにもののあわれを感じたように美しかったのだ。でも私の心はあわれを哀れと変換していた。人間の悪意の無い愚かさの結果なのだと感じた。
福島第一原子力発電事故は2011年3月11日。毎年その日になると、テレビから流れる慰霊の映像と共に手を合わせる。事故は地震が原因で、しかも東北の津波では沢山の人が海に流されている。私の弟の死も海に流されているので、すべてが繋がってしまう。人々のそれぞれの想いはそれぞれだと感じるけれど、生き延びている人達の心の哀れは底辺では一緒だと思うのだ。考えたり、感じたり、話したりするだけで涙が溢れる。それでも生き延びた人間は・・魔物とも戦えないで、日々を過ごしている。
実は・・ドライブをもっと楽しく!と書かれた Highway Walker11月号の冊子を常磐自動車の中郷SAで手に入れた。表紙のモデルは福士蒼汰。そんな普通の情報誌なのに・・いわきJCTを通り常磐富岡ICで高速をおりるとき、東北エリアマップ中でピンク色のエリアがあり・・それが帰還困難区域(区域内原則通行不可)エリアの表示だった。自動二輪、原動機付自転車、軽車両及び歩行者については通行できません。と書かれていた。地図の中に普通に書かれていることが・・確かに大切な情報だったけど受け入れにくかった。こんなピンク色の地図表示はいつになれば消えるのか・・と考えながらも走った。
会員様からの寄稿
二川宿

二川宿は東海道53次の33番目の宿場町。私は21番目の宿場町である岡部宿の観光ボランティアをしている。年1回の研修で今回は豊橋市の二川宿本陣資料館に出かけた。館では予約していた豊川のボランティアの案内を受けた。勿論私達は案内の中から学ぶことを密かに探しながら聞いていた。二川宿は東海道の宿場には2ヶ所しか現存していない貴重な資料館だった。あと1つは草津宿(52番目の宿場。東海道と中山道の分岐・合流の要所。2軒の本陣があった。全国の中では最大)。江戸時代には東海道の宿場には111軒の本陣があった中で残っているのが2軒だったのだ。
豊川のボランティアは「今は外国人も増えているので、英語での案内もしています」と言うので、「私達に英語で説明して」とお願いした。半分も聞き取れなかった。実は私達岡部の観光ボランティアも英語で案内しなくちゃと思ったことがあった。さしあたり日本語の案内を英語に訳すことからだったが、残念なことに会としては挫折した。ボランティアの構成員が高齢だということもあるが、歴史の言葉でややこしいこともあったのだ。
資料館の中には
①旅の名物 とろろ汁や十団子の復元模型があった。
②旅日記 二川宿から江戸への旅日記があった。出費の一覧だったが、その中に文久2年(1862)には安倍川越賃 百六拾四文。安倍川餅 百文があった。
③本陣宿帳 (1807~1866)の60年間の利用者と利用状況の宿帳だった。感動した。参勤交代に伴うものだが琉球人・大村丹後守様御姫君(大村藩) 金百疋・筑州様(福岡藩) 銀5枚・酒井飛騨守奥様方(敦賀藩) なし・桑名様御女中 金百疋・織田近江守様(柏原藩) 金100疋・・御三家では尾張・紀伊の両藩。大名では毛利・島津・蜂須賀・黒田・朝野・山内。なかでも福岡藩の黒田家は57回の宿泊をしていた。
④関札があった。会の皆で「欲しいね」と話した。関札は本陣門前や宿場の入口に掲げる札。関札は大名の姓名が記されているので、丁寧に扱われた。一度使用した後は本陣で大切に保管していたのだ。
岡部の本陣は江戸時代に2軒。今は内野本陣が敷地のみ残って史跡広場になっているだけなので・・二川宿本陣が本当に羨ましかった。
二川宿は東海道53次の33番目の宿場町。私は21番目の宿場町である岡部宿の観光ボランティアをしている。年1回の研修で今回は豊橋市の二川宿本陣資料館に出かけた。館では予約していた豊川のボランティアの案内を受けた。勿論私達は案内の中から学ぶことを密かに探しながら聞いていた。二川宿は東海道の宿場には2ヶ所しか現存していない貴重な資料館だった。あと1つは草津宿(52番目の宿場。東海道と中山道の分岐・合流の要所。2軒の本陣があった。全国の中では最大)。江戸時代には東海道の宿場には111軒の本陣があった中で残っているのが2軒だったのだ。
豊川のボランティアは「今は外国人も増えているので、英語での案内もしています」と言うので、「私達に英語で説明して」とお願いした。半分も聞き取れなかった。実は私達岡部の観光ボランティアも英語で案内しなくちゃと思ったことがあった。さしあたり日本語の案内を英語に訳すことからだったが、残念なことに会としては挫折した。ボランティアの構成員が高齢だということもあるが、歴史の言葉でややこしいこともあったのだ。
資料館の中には
①旅の名物 とろろ汁や十団子の復元模型があった。
②旅日記 二川宿から江戸への旅日記があった。出費の一覧だったが、その中に文久2年(1862)には安倍川越賃 百六拾四文。安倍川餅 百文があった。
③本陣宿帳 (1807~1866)の60年間の利用者と利用状況の宿帳だった。感動した。参勤交代に伴うものだが琉球人・大村丹後守様御姫君(大村藩) 金百疋・筑州様(福岡藩) 銀5枚・酒井飛騨守奥様方(敦賀藩) なし・桑名様御女中 金百疋・織田近江守様(柏原藩) 金100疋・・御三家では尾張・紀伊の両藩。大名では毛利・島津・蜂須賀・黒田・朝野・山内。なかでも福岡藩の黒田家は57回の宿泊をしていた。
④関札があった。会の皆で「欲しいね」と話した。関札は本陣門前や宿場の入口に掲げる札。関札は大名の姓名が記されているので、丁寧に扱われた。一度使用した後は本陣で大切に保管していたのだ。
岡部の本陣は江戸時代に2軒。今は内野本陣が敷地のみ残って史跡広場になっているだけなので・・二川宿本陣が本当に羨ましかった。
空海は生きている
友の会実技講座でお世話になりました
大杉弘子先生が法多山尊永寺(袋井市)で開催される
「空海は生きている」に出品されます。
〇会期 2019年2月7日(木)~11日(月)
10時~16時(入場無料) 初日7日(木)13時開場
法多山尊永寺「紫雲閣・一乗庵茶室」(通常非公開)
大杉弘子先生が法多山尊永寺(袋井市)で開催される
「空海は生きている」に出品されます。
〇会期 2019年2月7日(木)~11日(月)
10時~16時(入場無料) 初日7日(木)13時開場
法多山尊永寺「紫雲閣・一乗庵茶室」(通常非公開)
会員様からの寄稿
大内宿

江戸時代には会津城下と下野の国(日光今市)を結んだ32里の会津西街道の中で、会津から2番目の宿駅だった。大内宿こぶしラインを通過したどり着いた大内宿。茅葺き屋根が連なり美しかった。懐かしい雰囲気を感じた光景だった。1981年に重要伝統的建造物群保存地区になっていた。
静岡からの観光の私も、来て良かったと素直に感激した。500㍍の長さの真っ直ぐな町並みが好い。考えようによってはまるで映画のセットのようだ。途中茅葺の屋根を手入れしているところがあった。静岡でも茅葺の葺き替えは見ていて、島田の智満寺でも大掛かりな修復があり、当時葺き替え中に訪ねた時は、きれいな茅を手に入れる難しさや職人の少なさとかでとてもお金がかかると屋根葺き職人に聞いたことを思い出した。2011年頃だった。
のんびり歩いてどん詰まりの家は食事処になっていた。屋根を見上げると正面の左側のみきれいな茅で拭かれていた。お店の人は「全部をいっぺんに葺き替えるとお金がかかるし、できないので、申請して補助金がおりるとわかってから部分的に葺き変えているんですよ」と話していた。「葺き替えは結いがあるので・・」と聞いたときは・・そうなんだ・・と感心したり、大変だなーとも思った。ここでは部分的にやる方法が上手にまわっているみたいだった。テレビでよく見る岐阜県の白川郷では全面葺き替えで大掛かりが派手でカッコいい結い組織をしている。地域地域での葺き替えの違いをリアルに知った。
お店では高遠そばを商っていた。箸の代わりに葱1本を用いて食べるとのこと。名物になっていた。会津藩主の保科正之が育った長野県高遠から持ち帰った辛み大根の入ったそば。話の種だからと思い初めて食べる体験をした。ところでこんな風習は何故あるのか。会津のそばは昔に祝いの席や徳川将軍への献上品だったため「切る」というのは縁起が悪いので、葱を切らずにそのまま食べたらしい。おじさんの話では「このそばの食べ方はおめでたいから。結婚式にもこの葱で食べている・・何故かと言うと・・お椀は女の人のあそこを意味し、葱は男の人のものを表わしていて、子宝に恵まれるようにだから・・」とさらっと語った。ちょっとセクハラっぽい話しで、本当かなーと思いつつ食べてみた。葱で食べるのは大変だった。
江戸時代には会津城下と下野の国(日光今市)を結んだ32里の会津西街道の中で、会津から2番目の宿駅だった。大内宿こぶしラインを通過したどり着いた大内宿。茅葺き屋根が連なり美しかった。懐かしい雰囲気を感じた光景だった。1981年に重要伝統的建造物群保存地区になっていた。
静岡からの観光の私も、来て良かったと素直に感激した。500㍍の長さの真っ直ぐな町並みが好い。考えようによってはまるで映画のセットのようだ。途中茅葺の屋根を手入れしているところがあった。静岡でも茅葺の葺き替えは見ていて、島田の智満寺でも大掛かりな修復があり、当時葺き替え中に訪ねた時は、きれいな茅を手に入れる難しさや職人の少なさとかでとてもお金がかかると屋根葺き職人に聞いたことを思い出した。2011年頃だった。
のんびり歩いてどん詰まりの家は食事処になっていた。屋根を見上げると正面の左側のみきれいな茅で拭かれていた。お店の人は「全部をいっぺんに葺き替えるとお金がかかるし、できないので、申請して補助金がおりるとわかってから部分的に葺き変えているんですよ」と話していた。「葺き替えは結いがあるので・・」と聞いたときは・・そうなんだ・・と感心したり、大変だなーとも思った。ここでは部分的にやる方法が上手にまわっているみたいだった。テレビでよく見る岐阜県の白川郷では全面葺き替えで大掛かりが派手でカッコいい結い組織をしている。地域地域での葺き替えの違いをリアルに知った。
お店では高遠そばを商っていた。箸の代わりに葱1本を用いて食べるとのこと。名物になっていた。会津藩主の保科正之が育った長野県高遠から持ち帰った辛み大根の入ったそば。話の種だからと思い初めて食べる体験をした。ところでこんな風習は何故あるのか。会津のそばは昔に祝いの席や徳川将軍への献上品だったため「切る」というのは縁起が悪いので、葱を切らずにそのまま食べたらしい。おじさんの話では「このそばの食べ方はおめでたいから。結婚式にもこの葱で食べている・・何故かと言うと・・お椀は女の人のあそこを意味し、葱は男の人のものを表わしていて、子宝に恵まれるようにだから・・」とさらっと語った。ちょっとセクハラっぽい話しで、本当かなーと思いつつ食べてみた。葱で食べるのは大変だった。
会員様から
大人の遠足 山梨県甲州市
恵林寺(乾徳寺)と甘草屋敷の干し柿

武田信玄公菩提寺で臨済宗の古刹の恵林寺を訪ねた。滅却心頭火自涼と快川国師の言葉があった。あまりにも有名なフレーズ。受験勉強ではこの言葉を脳にインプットしてクーラーも無い暑い夏休みを過ごした記憶が蘇った。言葉を考えた生き様はすごいことだが、それに感化された人の何と多いこと。情報が氾濫するスマートフォンなど無い時代だから、素直に心に入ってきたのだとも思えた。
帰りがけに参道の左側のお土産屋さんに寄ってみた。ダンボールの箱の中に釣鐘型の柿が転がっていた。大きいけど既にグジュグジュとして皮が破れかかった柔らかいものや硬いしっかりしたものか混在していた。1個200円~100円の値段がついていた。「おいしいですよ。百目柿」の声に柔らくて少し崩れた柿を買ってみた。お店のおばさんがビニール袋に入れてくれた。覗くと袋の底はサイズあわせて切ったダンホールが敷かれていて柿がつぶれないように収まっていた。
その後甘草屋敷(かんぞうやしき)という瓦葺屋根のお屋敷を訪ねた。江戸時代から甘草を栽培し、その根がクスリになった。
軒下には百目柿が大量にきれいに皮をむかれ吊るされていた。吊るされたばかりの茅葺と柿の風情は素敵だった。丁度テレビ局の生放送があるみたいで、地元信州放送の女性アナウンサーが打ち合わせをしていた。地元の人に干し柿の作り方を聞いていた。打ち合わせなのになんとなく緊張しているのが伝わってきた。
子供の頃食べていた干し柿はこの大きな柿を信州の空っ風で乾燥させて作った物だったかもしれないと思った。信州の人は日本で一番寿命が長い。柿の生り年は医者が青くなるなどの言葉もある。柿を食べていれば元気でいれそう。
静岡のスーパでは見かけない、ぐじゅんぐじゅした柿。家に帰って美味しいのか不安だったが皮をめくってスプーンですくって食べてみた。美味しいではないか!! 百目柿の名前の由来は百もんめ(375g)の重さがあってつけられらしい。実際には大きいものは500gもあるらしい。
そんな体験の後、地元のおばあちゃんに3個の百目柿を偶然もらった。形がくずれていなかった。「どこで手に入れたの?」と聞くと自分の家の裏の山だという。えー!! 静岡県でもあるんだとびっくりした。
恵林寺(乾徳寺)と甘草屋敷の干し柿
武田信玄公菩提寺で臨済宗の古刹の恵林寺を訪ねた。滅却心頭火自涼と快川国師の言葉があった。あまりにも有名なフレーズ。受験勉強ではこの言葉を脳にインプットしてクーラーも無い暑い夏休みを過ごした記憶が蘇った。言葉を考えた生き様はすごいことだが、それに感化された人の何と多いこと。情報が氾濫するスマートフォンなど無い時代だから、素直に心に入ってきたのだとも思えた。
帰りがけに参道の左側のお土産屋さんに寄ってみた。ダンボールの箱の中に釣鐘型の柿が転がっていた。大きいけど既にグジュグジュとして皮が破れかかった柔らかいものや硬いしっかりしたものか混在していた。1個200円~100円の値段がついていた。「おいしいですよ。百目柿」の声に柔らくて少し崩れた柿を買ってみた。お店のおばさんがビニール袋に入れてくれた。覗くと袋の底はサイズあわせて切ったダンホールが敷かれていて柿がつぶれないように収まっていた。
その後甘草屋敷(かんぞうやしき)という瓦葺屋根のお屋敷を訪ねた。江戸時代から甘草を栽培し、その根がクスリになった。
軒下には百目柿が大量にきれいに皮をむかれ吊るされていた。吊るされたばかりの茅葺と柿の風情は素敵だった。丁度テレビ局の生放送があるみたいで、地元信州放送の女性アナウンサーが打ち合わせをしていた。地元の人に干し柿の作り方を聞いていた。打ち合わせなのになんとなく緊張しているのが伝わってきた。
子供の頃食べていた干し柿はこの大きな柿を信州の空っ風で乾燥させて作った物だったかもしれないと思った。信州の人は日本で一番寿命が長い。柿の生り年は医者が青くなるなどの言葉もある。柿を食べていれば元気でいれそう。
静岡のスーパでは見かけない、ぐじゅんぐじゅした柿。家に帰って美味しいのか不安だったが皮をめくってスプーンですくって食べてみた。美味しいではないか!! 百目柿の名前の由来は百もんめ(375g)の重さがあってつけられらしい。実際には大きいものは500gもあるらしい。
そんな体験の後、地元のおばあちゃんに3個の百目柿を偶然もらった。形がくずれていなかった。「どこで手に入れたの?」と聞くと自分の家の裏の山だという。えー!! 静岡県でもあるんだとびっくりした。
友の会会員レクチャー申込受付中
友の会会員レクチャー「1968年激動の時代の芸術」
★日 時 平成31年2月24日(日)13:00~ 30分程度 (定員20名程度)
★集合場所 2階 企画展入口 ★持ち物 友の会会員証
★受講料 無料ですが、企画展入場券が必要となります。
★締 切 平成31年2月21日(木)
★申込方法 事務局までお電話、Faxにてお申込み下さい。お申込みの際にはレクチャー
希望・お名前・会員番号・電話番号をお知らせください。
尚、特別会員様のみ1名同伴可能です。
★お申込み先 友の会事務局(火・木・金在館)TEL・FAX 054-264-0897
一般のフロアレクチャーより人数も少なくとても好評です
ぜひご参加してください
★日 時 平成31年2月24日(日)13:00~ 30分程度 (定員20名程度)
★集合場所 2階 企画展入口 ★持ち物 友の会会員証
★受講料 無料ですが、企画展入場券が必要となります。
★締 切 平成31年2月21日(木)
★申込方法 事務局までお電話、Faxにてお申込み下さい。お申込みの際にはレクチャー
希望・お名前・会員番号・電話番号をお知らせください。
尚、特別会員様のみ1名同伴可能です。
★お申込み先 友の会事務局(火・木・金在館)TEL・FAX 054-264-0897
一般のフロアレクチャーより人数も少なくとても好評です
ぜひご参加してください
第2回実技講座申込受付中
会員様から
お茶の香ロード2018

町おこしにもいろいろある。この「お茶の香ロード」を立ち上げたのは、東京の大学を卒業しそのままサラリーマンとして暮らした人の物語だ。毎年藤枝に帰省するたびに・・町や山の元気が失われている・・と思い自分で出来ることを・・と考えた人がいた。行政や政治とは関わらない立ち位置で地元の人達を巻き込む活動を続けてきた堀田一牛(いちぎゅう)氏だ。2004年に第一回「お茶の香ロード」が立ち上がった。それまでに至る5年間を横浜の家族と離れ単身赴任で一人住まいをしながらの活動開始だった。
初めて掘田氏に出会った時「茶町に帰ってきたら、昔の賑やかさが消えていて、何とかしたい」と熱く語る言葉に「裂織で良ければ協力できることはします」と交流が始まった。茶町の一言正廣(ひとことまさひろ)氏も賛同し、茶工場がギャラリーや寄席やライブホールにも変身した。
茶町は、江戸時代の宿場町だった商店街の上伝馬から500㍍離れているが、そこまでを中心にしてのエリアがロードになった。散策しながら楽しめるイベント。
私は西野商店の蔵で裂織り作品展示しながら、エリアをKURAガーデンと名づけた。お茶を楽しみながらの交流がはじまった。14年間参加して、毎年出会える人達と・・元気だった!!・・と1年ぶりの挨拶が出来るのも楽しい。毎回大判焼きを届けてくれるファンも有難い。
一昨年堀田氏が体を壊して、横浜に帰ってしまった。その後を地元の有志が引き継いているが賛同者の一言氏も亡くなってしまった。どうなるのかなと思ったが、地元の町おこしは何とか続けている。鬼願寺の広場のお茶席や蕎麦打ちも縮小し、場所を変えて続けている。
今年イベント中に堀田氏が横浜から来て寄ってくれた。「このイベントを立ち上げられて、本当に良かったと思っている」と話してた。一昨年よりは心身ともに元気になりつつ感じられた。家族と一緒で食事のバランスもとれ、良かったなーと思った。皆が堀田氏の情熱を良い意味で継承している。それぞれの立ち位置で、力まず続けているので私もやめないでいられる。
町おこしにもいろいろある。この「お茶の香ロード」を立ち上げたのは、東京の大学を卒業しそのままサラリーマンとして暮らした人の物語だ。毎年藤枝に帰省するたびに・・町や山の元気が失われている・・と思い自分で出来ることを・・と考えた人がいた。行政や政治とは関わらない立ち位置で地元の人達を巻き込む活動を続けてきた堀田一牛(いちぎゅう)氏だ。2004年に第一回「お茶の香ロード」が立ち上がった。それまでに至る5年間を横浜の家族と離れ単身赴任で一人住まいをしながらの活動開始だった。
初めて掘田氏に出会った時「茶町に帰ってきたら、昔の賑やかさが消えていて、何とかしたい」と熱く語る言葉に「裂織で良ければ協力できることはします」と交流が始まった。茶町の一言正廣(ひとことまさひろ)氏も賛同し、茶工場がギャラリーや寄席やライブホールにも変身した。
茶町は、江戸時代の宿場町だった商店街の上伝馬から500㍍離れているが、そこまでを中心にしてのエリアがロードになった。散策しながら楽しめるイベント。
私は西野商店の蔵で裂織り作品展示しながら、エリアをKURAガーデンと名づけた。お茶を楽しみながらの交流がはじまった。14年間参加して、毎年出会える人達と・・元気だった!!・・と1年ぶりの挨拶が出来るのも楽しい。毎回大判焼きを届けてくれるファンも有難い。
一昨年堀田氏が体を壊して、横浜に帰ってしまった。その後を地元の有志が引き継いているが賛同者の一言氏も亡くなってしまった。どうなるのかなと思ったが、地元の町おこしは何とか続けている。鬼願寺の広場のお茶席や蕎麦打ちも縮小し、場所を変えて続けている。
今年イベント中に堀田氏が横浜から来て寄ってくれた。「このイベントを立ち上げられて、本当に良かったと思っている」と話してた。一昨年よりは心身ともに元気になりつつ感じられた。家族と一緒で食事のバランスもとれ、良かったなーと思った。皆が堀田氏の情熱を良い意味で継承している。それぞれの立ち位置で、力まず続けているので私もやめないでいられる。
会員様から
いわき市立草野心平文学館

草野心平の声で詩が流れる。あの懐かしい富士山の詩。小学校時代に教科書に載っていて大好きな詩。
少女たちはうまごやしの花を摘んでは巧みな手さばきで花環をつくる。
それをなわにして縄跳びをする。
花環を描くとそのなかに富士がはいる。
その度に富士は近づき。
とおくに座る。
耳には行行子(よしきり)。
頬にはひかり。
詩を聴きながら、レンゲの花を集めて編んで縄跳びをしたことを一枚の絵のように思い出す。私の住む地域の田圃ではうまごやし(シロツメクサ)はなくて、レンゲの花だった。その場所からは富士山も見えなかったけれど、心平さんの詩のイメージが遊びの中にいつもあった。
本物の心平さんに会ったのは高校時代。東京での講演会に出かけて行った時。着物姿でゆっくり壇上に現れ、開口一番「お酒が残っていますが・・」と語りはじめた。当時の私はそれだけで・・さすが詩人!と思ってしまった。そんなことも懐かしく思い出す。その後、高校時代には私も詩も書いた。詩人に憧れていたのだ。校内発行の文学雑誌にも投稿していた。
たどり着いた小高い丘にとんがり帽子のようなかわいい小さな建物が記念館だった。スイッチを押すと心平さんの声で詩が流れる空間があり、ためらわずにたくさんの詩の選択スイッチの中から富士山を押した私だった。『火の車』という飲み屋を経営していて・・詩では食べていけない現実があった。建物の中にその『火の車』が復元されていて、昭和の時代にタイムスリップした。飲み屋の椅子に座って幸せな時間をしばらく過ごした。
草野心平の声で詩が流れる。あの懐かしい富士山の詩。小学校時代に教科書に載っていて大好きな詩。
少女たちはうまごやしの花を摘んでは巧みな手さばきで花環をつくる。
それをなわにして縄跳びをする。
花環を描くとそのなかに富士がはいる。
その度に富士は近づき。
とおくに座る。
耳には行行子(よしきり)。
頬にはひかり。
詩を聴きながら、レンゲの花を集めて編んで縄跳びをしたことを一枚の絵のように思い出す。私の住む地域の田圃ではうまごやし(シロツメクサ)はなくて、レンゲの花だった。その場所からは富士山も見えなかったけれど、心平さんの詩のイメージが遊びの中にいつもあった。
本物の心平さんに会ったのは高校時代。東京での講演会に出かけて行った時。着物姿でゆっくり壇上に現れ、開口一番「お酒が残っていますが・・」と語りはじめた。当時の私はそれだけで・・さすが詩人!と思ってしまった。そんなことも懐かしく思い出す。その後、高校時代には私も詩も書いた。詩人に憧れていたのだ。校内発行の文学雑誌にも投稿していた。
たどり着いた小高い丘にとんがり帽子のようなかわいい小さな建物が記念館だった。スイッチを押すと心平さんの声で詩が流れる空間があり、ためらわずにたくさんの詩の選択スイッチの中から富士山を押した私だった。『火の車』という飲み屋を経営していて・・詩では食べていけない現実があった。建物の中にその『火の車』が復元されていて、昭和の時代にタイムスリップした。飲み屋の椅子に座って幸せな時間をしばらく過ごした。