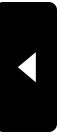会員様から
平成最後の文化展・10月
遠州横須賀ちっちゃな文化展20回
ちっちゃなと言うけれと、横須賀地区に残る古い町並み2キロをそっくりそのまま美術館にして県内で初めて成功した文化イベントである。普段生活しているお宅の軒先・土間を借りてアートを展示している。参加アーティストは70組。どうしたら町おこしで成功できるのかと・・どの町もこの横須賀のイベントから学ぶために行政関係者もアーティスト集団も見学に来ている。
オファーが来たのが平成20年。国民文化祭徳島で受賞した話題がテレビ局でとりあげられた後に「参加して欲しい」と誘われた。ということは10回参加したことになる。最初は八百甚(やおじん)の店。昔には華やかだったろうと思う結婚式のできる町の中心にある旅館。その後番屋で。
横須賀には城がある。城は徳川家康が武田信玄の高天神城を攻略するために大須賀康高に命じて築かれた。1581年に高天神を落とす。それからは横須賀藩の中心として発展する。めまぐるしく藩主が代わるが、14代西尾忠尚は老中も務めている。と言うことで、歴史がある町でもあるが、鉄道から離れているため町並みは昔のまま残った町でもある。道路は車がすれちがうことができるがとっても狭い。
ところで私が気に入っている番屋のこと。掛川市文化財になっている。「文化財の中で展示できるなんて何て幸せ」と思う。江戸時代には横須賀城のところにあったものを大須賀支市民交流センターの場所に移築している。地元の人が言うには移築費用だけでも2千万掛かったらしい。今でいう交番の元祖が番屋である。


遠州横須賀ちっちゃな文化展20回
ちっちゃなと言うけれと、横須賀地区に残る古い町並み2キロをそっくりそのまま美術館にして県内で初めて成功した文化イベントである。普段生活しているお宅の軒先・土間を借りてアートを展示している。参加アーティストは70組。どうしたら町おこしで成功できるのかと・・どの町もこの横須賀のイベントから学ぶために行政関係者もアーティスト集団も見学に来ている。
オファーが来たのが平成20年。国民文化祭徳島で受賞した話題がテレビ局でとりあげられた後に「参加して欲しい」と誘われた。ということは10回参加したことになる。最初は八百甚(やおじん)の店。昔には華やかだったろうと思う結婚式のできる町の中心にある旅館。その後番屋で。
横須賀には城がある。城は徳川家康が武田信玄の高天神城を攻略するために大須賀康高に命じて築かれた。1581年に高天神を落とす。それからは横須賀藩の中心として発展する。めまぐるしく藩主が代わるが、14代西尾忠尚は老中も務めている。と言うことで、歴史がある町でもあるが、鉄道から離れているため町並みは昔のまま残った町でもある。道路は車がすれちがうことができるがとっても狭い。
ところで私が気に入っている番屋のこと。掛川市文化財になっている。「文化財の中で展示できるなんて何て幸せ」と思う。江戸時代には横須賀城のところにあったものを大須賀支市民交流センターの場所に移築している。地元の人が言うには移築費用だけでも2千万掛かったらしい。今でいう交番の元祖が番屋である。
会員様から
大人の遠足①
秩父銘仙館 大正ロマン・昭和モダン

旧埼玉県繊維工業試験場
私の裂織(さきおり)の材料になる古布に銘仙の着物がある。デザインが大胆で日本人なのにこんな元気さを持っているなんてと感動する明るい色彩で大好き。着物生地なのにどうしてこんな風に織れるのだろうとずっと不思議だった。柄の出し方がわからなかった。表も裏も同じ色なので確かに織っているのだ。大正時代や昭和初期に銘仙は規格外の繭を使って大人の普段着になっていた。当時の華やかな雰囲気を想像すると、弾けていた日常がみえる。イベントに「藤枝おんぱく」がある。その情報誌の表紙を飾る人は銘仙の着物を着ている。着物姿の表紙でも、今の着物でないのが素敵。
秩父が銘仙の産地と知って行ってみる事にした。たどり着く道筋は山に囲まれ稲作をする田んぼがほとんど無かった。養蚕が盛んだったと思える風景だった。2013年に国の伝統的工芸品に指定された。日常で着物を着る人が減り、素敵な銘仙柄も理解する人が減っている。
埼玉県繊維工業試験場が秩父銘仙の織体験が出来る場所だった。そこには銘仙が出来るまでの工程が何となくわかる様に展示して置かれていた。縦糸をたてる。固定してから横糸を粗く織りこむ。型紙で模様を刷り、次に横糸を一度ほぐしながら正式に織りこむ・・という工程だった。仮織りで模様を染めていたのだ。織ってから染めている発想をしていなかったのでびっくりだった。そして染めてからまたほぐして織り直す織り方を考え付いた人が凄いと納得できたと思う見学だった。秩父の町の色も心に残った。


秩父銘仙館 大正ロマン・昭和モダン
旧埼玉県繊維工業試験場
私の裂織(さきおり)の材料になる古布に銘仙の着物がある。デザインが大胆で日本人なのにこんな元気さを持っているなんてと感動する明るい色彩で大好き。着物生地なのにどうしてこんな風に織れるのだろうとずっと不思議だった。柄の出し方がわからなかった。表も裏も同じ色なので確かに織っているのだ。大正時代や昭和初期に銘仙は規格外の繭を使って大人の普段着になっていた。当時の華やかな雰囲気を想像すると、弾けていた日常がみえる。イベントに「藤枝おんぱく」がある。その情報誌の表紙を飾る人は銘仙の着物を着ている。着物姿の表紙でも、今の着物でないのが素敵。
秩父が銘仙の産地と知って行ってみる事にした。たどり着く道筋は山に囲まれ稲作をする田んぼがほとんど無かった。養蚕が盛んだったと思える風景だった。2013年に国の伝統的工芸品に指定された。日常で着物を着る人が減り、素敵な銘仙柄も理解する人が減っている。
埼玉県繊維工業試験場が秩父銘仙の織体験が出来る場所だった。そこには銘仙が出来るまでの工程が何となくわかる様に展示して置かれていた。縦糸をたてる。固定してから横糸を粗く織りこむ。型紙で模様を刷り、次に横糸を一度ほぐしながら正式に織りこむ・・という工程だった。仮織りで模様を染めていたのだ。織ってから染めている発想をしていなかったのでびっくりだった。そして染めてからまたほぐして織り直す織り方を考え付いた人が凄いと納得できたと思う見学だった。秩父の町の色も心に残った。
会員様から
朱印状を発給できるのは将軍だけか (小川孫三あての朱印状)
藤枝市にはが、家康から渡されたという御朱印(全阿弥文書)を持っている小川孫三の子孫がいる。小川孫三は藤枝に土地を与えられ、住む町の名を白子(しろこ)町とよぶこととし、藤枝宿にありながら宿場業務など諸役御免となっていたことが記されている。現在は藤枝市本町と町名変更したが、小川眼科医院を経営しているのが御子孫である。医院の前にある「町名由来の碑」を見に行ったことがあるが、想像していたより小さかった。
この小川孫三は・・
天正十年(1582)織田信長が本能寺の変で倒れた時のこと。この時家康は信長の招きで上洛していた。信長の勧めで、京都見物をしたあと堺へ足を延ばして、堺の納屋衆(なやしゅう=納屋を所有し賃貸によって利益をあげていた堺の豪商)と茶の湯を楽しんでいる。そして本能寺の変を知った家康は・・急遽帰国。歴史好きにはたまらない興味の伊賀越えである。(本当のことは未だわかっていない)。伊勢に抜け白子(しらこ・三重県伊勢市)から海路三河大浜(愛知県碧南市)に渡り無事岡崎城に。家康を伊勢から三河まで船で送ったのが小川孫三。しかし、小田信孝から厳しい詮議を受け伊勢白子に住めなくなって家康を頼り、藤枝宿の東に草ぼうぼうの土地を与えられ、その地を白子町と名づけたと言われているのだ。
ところでこの朱印状である。家康の自筆だと皆思っている人が多いが、全阿弥 奉之と書かれている。朱印状を発給できるのは将軍のみというのではないという実例である。全阿弥は御伽衆(おとぎしゅう)と呼ばれる家康の側近の1人だったのだ。家康が書かせたのだ。家康の書体はもう少し細くて角ばっている。
藤枝市にはが、家康から渡されたという御朱印(全阿弥文書)を持っている小川孫三の子孫がいる。小川孫三は藤枝に土地を与えられ、住む町の名を白子(しろこ)町とよぶこととし、藤枝宿にありながら宿場業務など諸役御免となっていたことが記されている。現在は藤枝市本町と町名変更したが、小川眼科医院を経営しているのが御子孫である。医院の前にある「町名由来の碑」を見に行ったことがあるが、想像していたより小さかった。
この小川孫三は・・
天正十年(1582)織田信長が本能寺の変で倒れた時のこと。この時家康は信長の招きで上洛していた。信長の勧めで、京都見物をしたあと堺へ足を延ばして、堺の納屋衆(なやしゅう=納屋を所有し賃貸によって利益をあげていた堺の豪商)と茶の湯を楽しんでいる。そして本能寺の変を知った家康は・・急遽帰国。歴史好きにはたまらない興味の伊賀越えである。(本当のことは未だわかっていない)。伊勢に抜け白子(しらこ・三重県伊勢市)から海路三河大浜(愛知県碧南市)に渡り無事岡崎城に。家康を伊勢から三河まで船で送ったのが小川孫三。しかし、小田信孝から厳しい詮議を受け伊勢白子に住めなくなって家康を頼り、藤枝宿の東に草ぼうぼうの土地を与えられ、その地を白子町と名づけたと言われているのだ。
ところでこの朱印状である。家康の自筆だと皆思っている人が多いが、全阿弥 奉之と書かれている。朱印状を発給できるのは将軍のみというのではないという実例である。全阿弥は御伽衆(おとぎしゅう)と呼ばれる家康の側近の1人だったのだ。家康が書かせたのだ。家康の書体はもう少し細くて角ばっている。
会員様から
ヴォーリズの想いを今にかさねて
静岡マッケンジー邸

ヴォーリズ建築の旧伊庭家住宅を訪ねた。近江八幡エリアで安土城跡の近くだった。建物は2013年に指定文化財に。 建物の中に入ると案内の人達の説明があり愛情が伝わってきて見学できたことを感謝した。わかり易くて上手だった。ボランティアの1人が「自分の家をほったらかしで、案内している」と楽しそうに笑った。大正2年に建てられたもので、和洋式木造住宅地。住友財閥2代目総領事である伊庭氏の息子の邸宅だったもの。そしてぼろぼろの酷い状態になっていたらしい。修理して洒落た古風な味にもどっていた。前日はウォーリズ記念館も訪ねていたので、木造だけど洒落た家のつくりの印象が深まった。
ヴォーリズ建築
5年程前東京生まれ東京育ちの畑中さんを案内して久能山東照宮のロープウェイに乗った。市内の案内の中で「連れて行って欲しい」といわれた場所が、1939年に建築された旧マッケンジー邸だった。マッケンジー邸は茶貿易商の住居であった。国登録文化財になっているその建物がヴォーリズ建築だったのだ。私自身は特にヴォーリズを意識したこともなかったが、根強いファンがいることをその時知った。駿河区高松の海に沿っての道からちょっと迷ってたどり着いた。2階のフロアーにある陶器のシンクの緑がかった青の色彩が心に残った。
最近自称熟女の星の彼女と水中ウォーキングをしながらマッケンジー邸の話をした。すると「多分4歳くらいの時おじいさんに連れて行ってもらったことがあったよ。キャデラックの車があったのよ。アメリカ人でご主人は既に亡くなっていたけど。エミリーさんはメイドカフェ風の真っ白のエプロンだった。で、フルーツポンチの中に真ん丸くカットされたスイカがあって・・手作りのお菓子を貰った。クリスマスのときは自分も歌をうたったことを覚えている・・」と懐かしい目で話した。50年以上前の思い出。リアルな話を身近に聞けて感動した。ちなみにおじいさんはお茶関係の仕事だった。
9/14の新聞で「名建築家ヴォーリズ設計」の見出しが目にとまった。静岡・森下小学校が静岡大火で焼失し、建て替えの時ウォーリズに依頼し、43年に完成。でも45年の空襲で焼け落ちてしまったという記事だった。
静岡マッケンジー邸
ヴォーリズ建築の旧伊庭家住宅を訪ねた。近江八幡エリアで安土城跡の近くだった。建物は2013年に指定文化財に。 建物の中に入ると案内の人達の説明があり愛情が伝わってきて見学できたことを感謝した。わかり易くて上手だった。ボランティアの1人が「自分の家をほったらかしで、案内している」と楽しそうに笑った。大正2年に建てられたもので、和洋式木造住宅地。住友財閥2代目総領事である伊庭氏の息子の邸宅だったもの。そしてぼろぼろの酷い状態になっていたらしい。修理して洒落た古風な味にもどっていた。前日はウォーリズ記念館も訪ねていたので、木造だけど洒落た家のつくりの印象が深まった。
ヴォーリズ建築
5年程前東京生まれ東京育ちの畑中さんを案内して久能山東照宮のロープウェイに乗った。市内の案内の中で「連れて行って欲しい」といわれた場所が、1939年に建築された旧マッケンジー邸だった。マッケンジー邸は茶貿易商の住居であった。国登録文化財になっているその建物がヴォーリズ建築だったのだ。私自身は特にヴォーリズを意識したこともなかったが、根強いファンがいることをその時知った。駿河区高松の海に沿っての道からちょっと迷ってたどり着いた。2階のフロアーにある陶器のシンクの緑がかった青の色彩が心に残った。
最近自称熟女の星の彼女と水中ウォーキングをしながらマッケンジー邸の話をした。すると「多分4歳くらいの時おじいさんに連れて行ってもらったことがあったよ。キャデラックの車があったのよ。アメリカ人でご主人は既に亡くなっていたけど。エミリーさんはメイドカフェ風の真っ白のエプロンだった。で、フルーツポンチの中に真ん丸くカットされたスイカがあって・・手作りのお菓子を貰った。クリスマスのときは自分も歌をうたったことを覚えている・・」と懐かしい目で話した。50年以上前の思い出。リアルな話を身近に聞けて感動した。ちなみにおじいさんはお茶関係の仕事だった。
9/14の新聞で「名建築家ヴォーリズ設計」の見出しが目にとまった。静岡・森下小学校が静岡大火で焼失し、建て替えの時ウォーリズに依頼し、43年に完成。でも45年の空襲で焼け落ちてしまったという記事だった。
会員様から
一途さ生んだ戦争画
藤田嗣治展
前日、東京は豪雨で混乱しているニュースが流れていた。が、朝から何となく落ち着いたシトシト雨にかわった。不安な天気だったが東京都美術館で開催中の「没後50年 藤田嗣治展」を観にいった。81歳の人生だった。自分の礼拝堂の壁画のために80歳を前にしてフレスコ技法に挑んでいる。聖母子像・受胎告知・東方三博士の礼拝・キリストの磔刑がある。「(礼拝堂の壁画を制作するための)足場の上で私は自分の80年の罪を購うよ。私の神は私に力を与えてくれる・・、終わった・・、だが人生は美しいんだ。」そしてシャンパーニュにノートル=ダム・ド・ラ・ぺ礼拝堂に眠った。後には奥さんの君代も一緒に。
今までに藤田嗣治の作品の中では・・「東京国立近代美術館」で従軍看護婦が傷病兵と共に描かれていた戦争画・箱根の「メナード美術館」で《誕生日》という部屋を覗き込む子供達がいる作品を見ていて印象的で忘れられない。
絵のインパクトとは別に気に掛かっていたのは彼の一生だった。結局日本を離れ、晩年に洗礼を受け、しかも礼拝堂を建築した。自分のしたい事が解かっているということは強い。何て幸せなんだろう。
あさひテレビや日曜美術館で「知られざる藤田嗣治~天才画家の遺言」の特集をしいて、藤田の声がテープから流れたシーンがあった。東京都美の中でも藤田の声が聞こえた。ちょっと遊び人風で、風流な人だったんだろう。「しばらくお待ちくださいませ。もう少ししたいことが残っております。どれだけの力が私にあるかを一つまとめて試したいのでござりまする」のせりふ。都都逸風の声も聞こえた。
東京都美の展示は混んでいて、人の流れにあわせて移動した。140点以上の絵は多すぎて、疲れた。藤田の描いた作品の流れを網羅していたので、藤田を理解したい人にはバランスが良い展示だったかも知れない。私はフランス国立近代美術館所蔵の《カフェにて》の憂い顔の女性のポーズがじっくり見られて幸せだった。この絵はニューヨークで描いたが、窓外はパリの街角「ラ・プティット・マドレーヌ」で、解説では〈画面からはもうすぐ始まるパリでの生活への期待と不安が入り混じった、画家の複雑な心情が垣間見える〉と書かれていた。憂い顔をそう理解した解説も面白いが、藤田嗣治の他の絵の表情も似たものだと思う。でもその絵はフランスぽくって美しかった。

藤田嗣治展
前日、東京は豪雨で混乱しているニュースが流れていた。が、朝から何となく落ち着いたシトシト雨にかわった。不安な天気だったが東京都美術館で開催中の「没後50年 藤田嗣治展」を観にいった。81歳の人生だった。自分の礼拝堂の壁画のために80歳を前にしてフレスコ技法に挑んでいる。聖母子像・受胎告知・東方三博士の礼拝・キリストの磔刑がある。「(礼拝堂の壁画を制作するための)足場の上で私は自分の80年の罪を購うよ。私の神は私に力を与えてくれる・・、終わった・・、だが人生は美しいんだ。」そしてシャンパーニュにノートル=ダム・ド・ラ・ぺ礼拝堂に眠った。後には奥さんの君代も一緒に。
今までに藤田嗣治の作品の中では・・「東京国立近代美術館」で従軍看護婦が傷病兵と共に描かれていた戦争画・箱根の「メナード美術館」で《誕生日》という部屋を覗き込む子供達がいる作品を見ていて印象的で忘れられない。
絵のインパクトとは別に気に掛かっていたのは彼の一生だった。結局日本を離れ、晩年に洗礼を受け、しかも礼拝堂を建築した。自分のしたい事が解かっているということは強い。何て幸せなんだろう。
あさひテレビや日曜美術館で「知られざる藤田嗣治~天才画家の遺言」の特集をしいて、藤田の声がテープから流れたシーンがあった。東京都美の中でも藤田の声が聞こえた。ちょっと遊び人風で、風流な人だったんだろう。「しばらくお待ちくださいませ。もう少ししたいことが残っております。どれだけの力が私にあるかを一つまとめて試したいのでござりまする」のせりふ。都都逸風の声も聞こえた。
東京都美の展示は混んでいて、人の流れにあわせて移動した。140点以上の絵は多すぎて、疲れた。藤田の描いた作品の流れを網羅していたので、藤田を理解したい人にはバランスが良い展示だったかも知れない。私はフランス国立近代美術館所蔵の《カフェにて》の憂い顔の女性のポーズがじっくり見られて幸せだった。この絵はニューヨークで描いたが、窓外はパリの街角「ラ・プティット・マドレーヌ」で、解説では〈画面からはもうすぐ始まるパリでの生活への期待と不安が入り混じった、画家の複雑な心情が垣間見える〉と書かれていた。憂い顔をそう理解した解説も面白いが、藤田嗣治の他の絵の表情も似たものだと思う。でもその絵はフランスぽくって美しかった。
会員様から
静岡県文花プログラムスペシャルトーク
2018―1
海の国 静岡

ちょっと地味なチラシに武蔵野美術大学博士・民俗学神野善治(かみのよしはる)氏 と静岡県立美術館館長木下直之氏の対談案内があった。チラシには浮き輪のように見える丸い形の、一見すると昔の石でできたお金みたいなイラストが描かれていた。何だろう。会場はレストラン&カフェ「グランテラス」。グランシップのレストランが講座室に変身しての講演会場だった。50人程が参加していた。
そんなに期待していなかったということもあったかも知れない。でも静岡の海の傍で暮らす人々が、どんな暮らしを営み、どんな文化を築いていて、その為の道具を「美しい道具」と話す神野さんの人柄・声・表情にすっかり魅了されてしまった。すべてが愛情表現だったのだ。神野さんは道具の1つ1つを見つけたときの感動をストレートに話した。そんな風に道具をチャーミングに話す人に私は初めて出会った。最初は昔の絵馬・絵図。豆州内浦のまぐろ漁の絵。湾内で普通にまぐろを捕っている絵だった。多分絵だけを見せられたとしても私の記憶に残らない絵だった。でも神野氏が話した後では、その絵が宝物に思えたことが不思議だった。会場は神野ワールドで洗脳された。
ところで神野氏は現在大学で700人の生徒に民俗学を教えているらしい。成績をつけるのも大変でと言いながら・・レポートで民族と書く生徒がいると嘆いていた。俗と族さえ意識できないことが許せないらしい。私も戸惑った。日常の会話で民俗学と意識してしゃべったことが無かったからだ。
鈴木兼平さんの「焼津漁労絵図」。近藤和船研究所の話。八丁櫓。こちらは私が岡部に住んでいるので身近な話題で、知っている事だったが聞いていて楽しかった。
蟹を捕る道具を古老につくってもらった写真もインパクトを感じた。それに網や針の道具を含めてたくさんの情報発信だった。そしてあのストーンだと思ったのは布で出来ていた。魚を木のたらい桶に入れ、売るための移動のとき頭に乗せるクッションだった。
最近文化プログラムの愛知県での新聞記事を読んだ。演出家、劇作家の野田秀樹さんが監修する「東京キャラバン」で、500人の人が集まり、多様性に富んだ「ゆるゆる」の夏祭りになったとある。前回・今回参加した静岡県文化プログラムの講座の存在はわかったが、文化発信の立ち位置がまだわからないでいる。
2018―1
海の国 静岡
ちょっと地味なチラシに武蔵野美術大学博士・民俗学神野善治(かみのよしはる)氏 と静岡県立美術館館長木下直之氏の対談案内があった。チラシには浮き輪のように見える丸い形の、一見すると昔の石でできたお金みたいなイラストが描かれていた。何だろう。会場はレストラン&カフェ「グランテラス」。グランシップのレストランが講座室に変身しての講演会場だった。50人程が参加していた。
そんなに期待していなかったということもあったかも知れない。でも静岡の海の傍で暮らす人々が、どんな暮らしを営み、どんな文化を築いていて、その為の道具を「美しい道具」と話す神野さんの人柄・声・表情にすっかり魅了されてしまった。すべてが愛情表現だったのだ。神野さんは道具の1つ1つを見つけたときの感動をストレートに話した。そんな風に道具をチャーミングに話す人に私は初めて出会った。最初は昔の絵馬・絵図。豆州内浦のまぐろ漁の絵。湾内で普通にまぐろを捕っている絵だった。多分絵だけを見せられたとしても私の記憶に残らない絵だった。でも神野氏が話した後では、その絵が宝物に思えたことが不思議だった。会場は神野ワールドで洗脳された。
ところで神野氏は現在大学で700人の生徒に民俗学を教えているらしい。成績をつけるのも大変でと言いながら・・レポートで民族と書く生徒がいると嘆いていた。俗と族さえ意識できないことが許せないらしい。私も戸惑った。日常の会話で民俗学と意識してしゃべったことが無かったからだ。
鈴木兼平さんの「焼津漁労絵図」。近藤和船研究所の話。八丁櫓。こちらは私が岡部に住んでいるので身近な話題で、知っている事だったが聞いていて楽しかった。
蟹を捕る道具を古老につくってもらった写真もインパクトを感じた。それに網や針の道具を含めてたくさんの情報発信だった。そしてあのストーンだと思ったのは布で出来ていた。魚を木のたらい桶に入れ、売るための移動のとき頭に乗せるクッションだった。
最近文化プログラムの愛知県での新聞記事を読んだ。演出家、劇作家の野田秀樹さんが監修する「東京キャラバン」で、500人の人が集まり、多様性に富んだ「ゆるゆる」の夏祭りになったとある。前回・今回参加した静岡県文化プログラムの講座の存在はわかったが、文化発信の立ち位置がまだわからないでいる。
会員向けレクチャー募集中!
「めがねと旅する美術展」レクチャー
<日 時> 平成30年12月2日(日)11:00~ 30分程度(定員30名)
<集合場所> 2F 企画展入口
<持 ち 物> 友の会会員証
<受 講 料> 無料ですが、企画展入場券が必要となります。
<締 切> 11月29日(木)
<申込方法> 事務局までお電話、FAXにてお申込み下さい。
お申込みの際にはレクチャー希望・お名前・会員番号・電話番号をお知らせください。
尚、特別会員様のみ1名同伴可能です。
<お申込み先> 友の会事務局 (火・木・金在館) 電話・FAX 054-264-0897
<日 時> 平成30年12月2日(日)11:00~ 30分程度(定員30名)
<集合場所> 2F 企画展入口
<持 ち 物> 友の会会員証
<受 講 料> 無料ですが、企画展入場券が必要となります。
<締 切> 11月29日(木)
<申込方法> 事務局までお電話、FAXにてお申込み下さい。
お申込みの際にはレクチャー希望・お名前・会員番号・電話番号をお知らせください。
尚、特別会員様のみ1名同伴可能です。
<お申込み先> 友の会事務局 (火・木・金在館) 電話・FAX 054-264-0897
会員様から
「極北へ」 石川直樹
アラスカ飛行場に向かう空から私が見たマッキンリー(デナリ)は今まで見たどんな景色よりも美しかった記憶がある。光が白銀の世界の山々を染めていたので、タイミングも良かったかもしれない。神々しい景色だった。デナリはマッキンリーと同じ山で、2015年に名前が変わったばかり。理由は北米先住民のコユコン族の「高きもの」を意味する「デナリ」をオバマ大統領が正式に認めたからだ。私は個人的にはマッキンリーの響きが好きなのだが、1897年のアメリカ大統領のウイリアム・マッキンリーの名前だったので、時代の流れで当然アラスカ人の好むデナリに変わったというわけだ。
石川直樹の本「極北へ」を読んでいる。2018年3月に発行されたばかり。静岡県立美術館に県内在住の太田正樹氏が石川直樹氏の撮影した富士山の写真を寄贈した。東京の画廊スカイザバスハウスで手に入れたものだ。新館蔵品展(2018 7/4~9/2)で5作品が展示中だった。
石川直樹氏とはどんな人?
冒険家+文筆家+写真家・・何て贅沢な肩書きだ。新館蔵品期間中に石川氏が来館した。自分の冒険の話もしながら、出版された本掲載の写真をスクリーンに写しながら、撮影したときの心境を語る講座に参加した。7大陸最高峰の登頂体験を持っていると聞いていたのに、お会いした本人は筋肉隆々でもなく大柄でもなかった。「きれいな風景写真を撮りたいわけでもなく、富士山と自分との関わりを撮っている」と語った。「経験を写真で撮っている」・・たとえば写真を見て高山病でふらふらしている自分を思い出す・・ということなのだ。撮影に使っているのは中判カメラ「Plaubel makina」(プラウエル マキナ) というカメラ。昔は1本で20枚撮れたが、今では10枚のフィルムになってしまったそうだ。同じカメラは6台持っている。今まで何台だめにしたかわからないとも。畳めば小型になり、1250gと軽量。蛇腹がかっこよかった。
「極北へ」の本の冒頭には「世界中を旅して写真を撮り、文章を書いて生きていくためにはどうしたらいいか」と考えていた受験生時代の気持ちが書かれている。40代の今は冒険家として、多くのファンを集めて人生を語っている。話を聞きながら、私も自分の人生を振り返っていた。
「言葉が通じないところでは20歳の頃は怖くない」と言った言葉が心に広がった。
アラスカ飛行場に向かう空から私が見たマッキンリー(デナリ)は今まで見たどんな景色よりも美しかった記憶がある。光が白銀の世界の山々を染めていたので、タイミングも良かったかもしれない。神々しい景色だった。デナリはマッキンリーと同じ山で、2015年に名前が変わったばかり。理由は北米先住民のコユコン族の「高きもの」を意味する「デナリ」をオバマ大統領が正式に認めたからだ。私は個人的にはマッキンリーの響きが好きなのだが、1897年のアメリカ大統領のウイリアム・マッキンリーの名前だったので、時代の流れで当然アラスカ人の好むデナリに変わったというわけだ。
石川直樹の本「極北へ」を読んでいる。2018年3月に発行されたばかり。静岡県立美術館に県内在住の太田正樹氏が石川直樹氏の撮影した富士山の写真を寄贈した。東京の画廊スカイザバスハウスで手に入れたものだ。新館蔵品展(2018 7/4~9/2)で5作品が展示中だった。
石川直樹氏とはどんな人?
冒険家+文筆家+写真家・・何て贅沢な肩書きだ。新館蔵品期間中に石川氏が来館した。自分の冒険の話もしながら、出版された本掲載の写真をスクリーンに写しながら、撮影したときの心境を語る講座に参加した。7大陸最高峰の登頂体験を持っていると聞いていたのに、お会いした本人は筋肉隆々でもなく大柄でもなかった。「きれいな風景写真を撮りたいわけでもなく、富士山と自分との関わりを撮っている」と語った。「経験を写真で撮っている」・・たとえば写真を見て高山病でふらふらしている自分を思い出す・・ということなのだ。撮影に使っているのは中判カメラ「Plaubel makina」(プラウエル マキナ) というカメラ。昔は1本で20枚撮れたが、今では10枚のフィルムになってしまったそうだ。同じカメラは6台持っている。今まで何台だめにしたかわからないとも。畳めば小型になり、1250gと軽量。蛇腹がかっこよかった。
「極北へ」の本の冒頭には「世界中を旅して写真を撮り、文章を書いて生きていくためにはどうしたらいいか」と考えていた受験生時代の気持ちが書かれている。40代の今は冒険家として、多くのファンを集めて人生を語っている。話を聞きながら、私も自分の人生を振り返っていた。
「言葉が通じないところでは20歳の頃は怖くない」と言った言葉が心に広がった。
会員様から
舟形屋敷 洪水から屋敷を守る

台風や梅雨前線の雨で河が氾濫したり、土砂崩れで家の中に土が入り込んだりの災害が続いている。台風も立て続けにやってきていて、テレビのニュースでは警戒を呼びかけていた。
そんな時大井川流域の屋敷の中には敷地の先端を大井川上流に向けて、洪水の流れを左右に分け被害を免れていた舟形屋敷を訪ねたことを思い出した。青野さんの家だった。地元では舟形屋敷の存在は有名らしいが、私はその時まで見た事がなく知らなかった。
敷地そのものが舟の形になっていた。溢れる水害体験のなかから生み出した貴重な生活の知恵の敷地の形であった。どうして造られたかと言うと、青野さんご先祖達は文政年間(1828)子年の大水で命が危ない被害にあい、その後につくった屋敷だったのだ。
大井川は長さだけだと天竜川に次いで2番目なのに、急勾配の川床を持っている。水源は高度3000㍍で2000㍍の分水嶺からの水を集めていて、一気に海に流れ込む荒れ川。洪水の記録は4年に一度は大井川流域のどこかでおきていた。
舟形屋敷は建物を中心にその周りに舟のような形に高さ1.5から2㍍前後の石垣堤防をつくり、その土に松を何十本と植えていた。屋敷の先端は勿論川上流を向いていて、先端には竹を植えていた。先端にいくと、竹や松などの木が勝手に成長していて、地面は石がごろごろしていた。青野さんは高齢だったが、私の質問にも朴訥に返事をしてくれた。興味を持った人が訪ねても同じように対応している感じだった。時代が変わり、沢山あった舟形屋敷も減っているとの事だった。
核家族が増え自分もローンを組んで家を買った。ローンの関係で土地を自由に選べない状況だった。今のところは大丈夫。でもニュースで大水の被害に会った家が昔からの安全な場所でなく新たに造成された土地だったとしたら、人災でもある気がする。
青野さんが元気でいて時代のリアルを語り続けて欲しいと心から思った。
台風や梅雨前線の雨で河が氾濫したり、土砂崩れで家の中に土が入り込んだりの災害が続いている。台風も立て続けにやってきていて、テレビのニュースでは警戒を呼びかけていた。
そんな時大井川流域の屋敷の中には敷地の先端を大井川上流に向けて、洪水の流れを左右に分け被害を免れていた舟形屋敷を訪ねたことを思い出した。青野さんの家だった。地元では舟形屋敷の存在は有名らしいが、私はその時まで見た事がなく知らなかった。
敷地そのものが舟の形になっていた。溢れる水害体験のなかから生み出した貴重な生活の知恵の敷地の形であった。どうして造られたかと言うと、青野さんご先祖達は文政年間(1828)子年の大水で命が危ない被害にあい、その後につくった屋敷だったのだ。
大井川は長さだけだと天竜川に次いで2番目なのに、急勾配の川床を持っている。水源は高度3000㍍で2000㍍の分水嶺からの水を集めていて、一気に海に流れ込む荒れ川。洪水の記録は4年に一度は大井川流域のどこかでおきていた。
舟形屋敷は建物を中心にその周りに舟のような形に高さ1.5から2㍍前後の石垣堤防をつくり、その土に松を何十本と植えていた。屋敷の先端は勿論川上流を向いていて、先端には竹を植えていた。先端にいくと、竹や松などの木が勝手に成長していて、地面は石がごろごろしていた。青野さんは高齢だったが、私の質問にも朴訥に返事をしてくれた。興味を持った人が訪ねても同じように対応している感じだった。時代が変わり、沢山あった舟形屋敷も減っているとの事だった。
核家族が増え自分もローンを組んで家を買った。ローンの関係で土地を自由に選べない状況だった。今のところは大丈夫。でもニュースで大水の被害に会った家が昔からの安全な場所でなく新たに造成された土地だったとしたら、人災でもある気がする。
青野さんが元気でいて時代のリアルを語り続けて欲しいと心から思った。
会員様から
掛川市二の丸美術館&磐田市香りの博物館
静岡から少し足をのばして掛川市二の丸美術館へ。
我が家の娘がはまった映画に掛川城がでていたから行きたい!
ちょうど私も香りの博物館で開催中の「コーヒーと香り展」をテレビでみて
行きたいなぁ~と思っていたので家族で西まで足をのばすことに。
二の丸美術館で開催中の「掛川城と高知城」ちょうど社会でならった
戦いの絵が展示されていました。知っている名前もでてきて
良い勉強に?なったのでは。きっかけはどうあれ色んなことに
どんどん興味を持ってくれたら嬉しいです。

香りの博物館は毎年県内小学生に配布されるしずおかミュージアムパスポートを見せると
小学生は無料で入館できます。もちろんスタンプも押してもらいました。
色んな香りを楽しんでいる間こどもたちはオリジナル香水をつくっていました。

静岡から少し足をのばして掛川市二の丸美術館へ。
我が家の娘がはまった映画に掛川城がでていたから行きたい!
ちょうど私も香りの博物館で開催中の「コーヒーと香り展」をテレビでみて
行きたいなぁ~と思っていたので家族で西まで足をのばすことに。
二の丸美術館で開催中の「掛川城と高知城」ちょうど社会でならった
戦いの絵が展示されていました。知っている名前もでてきて
良い勉強に?なったのでは。きっかけはどうあれ色んなことに
どんどん興味を持ってくれたら嬉しいです。

香りの博物館は毎年県内小学生に配布されるしずおかミュージアムパスポートを見せると
小学生は無料で入館できます。もちろんスタンプも押してもらいました。
色んな香りを楽しんでいる間こどもたちはオリジナル香水をつくっていました。