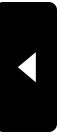会員様から
静岡平和資料館

今年の第65回安倍川花火は台風12号の影響で雨のため順延になり、8月末にはそれも中止になった。昭和28年の開始以来初めてだという。
しずおか平和資料館のボランティアをしている田中さんに「来てください」と誘われていて、今回訪ねて安倍川の花火は戦没者の慰霊のためだったと知った。展示作品やビデオを見て戦禍のすさまじさも知った。駿府城のまわりは壊滅状態でB29にやられた写真があった。安倍川の河川敷まで水を求めて逃げた人たちが沢山いたが、亡くなった人達を川原で荼毘にふした。江戸時代に家康の命令で多くのキリシタンを殺害した河川敷である。
子育て中、花火の日は朝から七輪と鍋におでん種を入れて、安倍川の橋下の日陰でおでんを温めながら水遊びしたりして花火の打ち上げを待ったこともあった。
去年は河川敷に理路整然と並んでいるシートを敷き詰めたところで、のんびり花火見物をした。川原を裸足で歩きまわることが懐かしい。弱ったからだが悲しいが、受け入れざるを得ない。でも花火は好きだ。夏休みは子供達を連れて、鹿島花火・静波花火・焼津海上花火・蓮華寺花火・日本平花火と花火行脚した日々が懐かしい。いろんな花火の中では日本平が印象的だ。打ち上げ方向の一番先端に陣取ると「これより危険」の合図のロープが掛かっていた。アルバイトの男の子が安全確認チェックで座っていた。そして最初の花火がドーンと打ちあがった瞬間、男の子が吃驚して這って逃げた。その慌てぶりが面白かった。私は体にドーンと響く音が好きだ。そして火の粉が落ちてくるのを避けたり、花火の破片の殻を集めたりした。懐かしい思い出だ。
戦没者の慰霊法要は、今年は本部主催で8/25日にとりおこなわれていた。
平和資料館で展示してある物の中で祝着があった。お宮参りの着物だ。柄が戦意高揚絵入りのもので、絹で出来た一つ身袷綿入れ着。飛行機・日の丸・船艦が描かれていた。KUVOHIUKAとロープウェイのボディーに文字が書かれていて、<空母日向>と読むらしい。そんな祝着も私は裂き織の材料で集めていた。また<陽子さんのもんぺとたび>もあり、私が今コレクションしている絣の柄で出来ていた。私はその戦火を想像するしかなかったが、家族を亡くした人の悲しみはとてもわかるので、この資料館の存続を心から願った。
今年の第65回安倍川花火は台風12号の影響で雨のため順延になり、8月末にはそれも中止になった。昭和28年の開始以来初めてだという。
しずおか平和資料館のボランティアをしている田中さんに「来てください」と誘われていて、今回訪ねて安倍川の花火は戦没者の慰霊のためだったと知った。展示作品やビデオを見て戦禍のすさまじさも知った。駿府城のまわりは壊滅状態でB29にやられた写真があった。安倍川の河川敷まで水を求めて逃げた人たちが沢山いたが、亡くなった人達を川原で荼毘にふした。江戸時代に家康の命令で多くのキリシタンを殺害した河川敷である。
子育て中、花火の日は朝から七輪と鍋におでん種を入れて、安倍川の橋下の日陰でおでんを温めながら水遊びしたりして花火の打ち上げを待ったこともあった。
去年は河川敷に理路整然と並んでいるシートを敷き詰めたところで、のんびり花火見物をした。川原を裸足で歩きまわることが懐かしい。弱ったからだが悲しいが、受け入れざるを得ない。でも花火は好きだ。夏休みは子供達を連れて、鹿島花火・静波花火・焼津海上花火・蓮華寺花火・日本平花火と花火行脚した日々が懐かしい。いろんな花火の中では日本平が印象的だ。打ち上げ方向の一番先端に陣取ると「これより危険」の合図のロープが掛かっていた。アルバイトの男の子が安全確認チェックで座っていた。そして最初の花火がドーンと打ちあがった瞬間、男の子が吃驚して這って逃げた。その慌てぶりが面白かった。私は体にドーンと響く音が好きだ。そして火の粉が落ちてくるのを避けたり、花火の破片の殻を集めたりした。懐かしい思い出だ。
戦没者の慰霊法要は、今年は本部主催で8/25日にとりおこなわれていた。
平和資料館で展示してある物の中で祝着があった。お宮参りの着物だ。柄が戦意高揚絵入りのもので、絹で出来た一つ身袷綿入れ着。飛行機・日の丸・船艦が描かれていた。KUVOHIUKAとロープウェイのボディーに文字が書かれていて、<空母日向>と読むらしい。そんな祝着も私は裂き織の材料で集めていた。また<陽子さんのもんぺとたび>もあり、私が今コレクションしている絣の柄で出来ていた。私はその戦火を想像するしかなかったが、家族を亡くした人の悲しみはとてもわかるので、この資料館の存続を心から願った。
会員様から
講演『石川直樹が見た静岡井川・南アルプス』
9月に入ってまた台風情報がテレビから流れてきた。目を覚ましてからずっと雨音が太鼓のようだ。講演会+井川神楽+在来野菜を求めて井川の町へ。参加申し込み段階で、「自分の車で行きたいんですけど」と言うと、用意されたバス乗車が参加条件だった。何としても『石川直樹が見た静岡井川・南アルプス』の講演に参加したかったので了解した。
大型バス3台で静岡駅から出発したが山道でのすれ違いに苦労していた。途中富士見峠では霧がかかっていたのに、井川湖に到着する時は霧も晴れ、雨も上がっていた。
講演会入り口のテントで、地場産品を売っていた。在来なすは太くて見慣れた形の2倍の大きさ。在来きゅうりは短くてちょっとずんぐりしていた。意識して在来物を見たのははじめてだった。在来作物は120種類以上あり、1つの地域で残っているのはとても珍しいとのこと。在来作物を食べることは「風景を食べること」らしい。皆さんは争って買っていた。
先週、静岡県立美術館友の会の会報誌「プロムナード」の表紙に石川氏の富士の写真《Mt.Fuji#38》掲載許可の件で本人と話したばかりだ。その後石川氏は一週間の間に、東海フォレスト山岳ガイドや静岡市の職員と一緒に南アルプスに登っていて、写真を撮っているはずだった。でも講演では石川氏の撮影した写真披露はなかった。残念だった。登山に同行した撮影映像を見ながら「私は山に登ったり、本をつくったりが自分の仕事です。今回山を登る機会を得ました。天気が悪くて白樺荘~千枚で残念ながら引き返しました」と話しはじめた。石川氏の写真が楽しみで参加した知り合いは少し怒っていた。結局南アルプスの全貌は判らなかった。ただ雷鳥の親と3羽の子供達の写真が心に残った。
講演後、石川直樹ファンがサインを求めで並んだ。私も「極北へ」の本を持参していたので、便乗してサインしてもらった。優しい美しい字のサインだった。ツーショット写真も撮ってもらえた。
井川神楽保存会の人達の舞が始まった。緑・白・オレンジの衣装を着て豊作を祈願した演目「三宝舞」や太刀を使った「五拍子舞」を披露していた。昔お茶壷姫に密着したとき、見せていただいた井川神楽だった。その時は外の景色の中での舞いだった。自然の光の中での衣装がきれいに見えていたことを懐かしく思い出した。
9月に入ってまた台風情報がテレビから流れてきた。目を覚ましてからずっと雨音が太鼓のようだ。講演会+井川神楽+在来野菜を求めて井川の町へ。参加申し込み段階で、「自分の車で行きたいんですけど」と言うと、用意されたバス乗車が参加条件だった。何としても『石川直樹が見た静岡井川・南アルプス』の講演に参加したかったので了解した。
大型バス3台で静岡駅から出発したが山道でのすれ違いに苦労していた。途中富士見峠では霧がかかっていたのに、井川湖に到着する時は霧も晴れ、雨も上がっていた。
講演会入り口のテントで、地場産品を売っていた。在来なすは太くて見慣れた形の2倍の大きさ。在来きゅうりは短くてちょっとずんぐりしていた。意識して在来物を見たのははじめてだった。在来作物は120種類以上あり、1つの地域で残っているのはとても珍しいとのこと。在来作物を食べることは「風景を食べること」らしい。皆さんは争って買っていた。
先週、静岡県立美術館友の会の会報誌「プロムナード」の表紙に石川氏の富士の写真《Mt.Fuji#38》掲載許可の件で本人と話したばかりだ。その後石川氏は一週間の間に、東海フォレスト山岳ガイドや静岡市の職員と一緒に南アルプスに登っていて、写真を撮っているはずだった。でも講演では石川氏の撮影した写真披露はなかった。残念だった。登山に同行した撮影映像を見ながら「私は山に登ったり、本をつくったりが自分の仕事です。今回山を登る機会を得ました。天気が悪くて白樺荘~千枚で残念ながら引き返しました」と話しはじめた。石川氏の写真が楽しみで参加した知り合いは少し怒っていた。結局南アルプスの全貌は判らなかった。ただ雷鳥の親と3羽の子供達の写真が心に残った。
講演後、石川直樹ファンがサインを求めで並んだ。私も「極北へ」の本を持参していたので、便乗してサインしてもらった。優しい美しい字のサインだった。ツーショット写真も撮ってもらえた。
井川神楽保存会の人達の舞が始まった。緑・白・オレンジの衣装を着て豊作を祈願した演目「三宝舞」や太刀を使った「五拍子舞」を披露していた。昔お茶壷姫に密着したとき、見せていただいた井川神楽だった。その時は外の景色の中での舞いだった。自然の光の中での衣装がきれいに見えていたことを懐かしく思い出した。
会員様から
日坂宿
山岡鉄舟の書に出会う


<東には東海道の難所「小夜の中山」が控え、西には「事任八幡宮」が鎮座する小さな宿場町でした>と書かれたお茶のペットボトルを、昔からある小夜の中山の茶店で買った。世界農業遺産茶草場農法の里東海道の25番目の宿場町日坂でつくられているお茶だった。お茶のペットボトルの種類はたくさんあるが、茶草場の濃いお茶は初めて飲んだ。
小雨の中目的地の本陣跡に向かって走った。今まで日坂宿を通ることが無かったことが不思議。でも国1がまだ旧道を走っていた頃も日坂はほんのちょっぴり道から外れていたから通っていないのだ。宿場としては坂下(三重県鈴鹿)、由比に次ぐ小さな宿場。
萬屋・藤文・かえで屋・問屋場跡・川坂屋などの中で印象深かったのは、川坂屋。宿場の中で1番西にあった旅籠屋で、身分の高い武士や公家などが宿泊した格の高い脇本陣格の建物だった。そしてそこで山岡鉄舟(1836~1888)の書を見つけた。襖に貼ってあり、バランスも良く味のある書だった。心が釘付けになった。明治初頭に一旦廃業後も要人に宿を提供したことから書が残っていたのかと思った。7言律詩だったが読み取ることは出来なかった。幕末の3舟(勝海舟・高橋泥舟・山岡鉄舟)の1人で明治維新後、徳川家達に従い駿府で活躍した人の書だ。牧の原のお茶の助言もしていた。「鉄舟のいない世の中は生きるに値しない」と胃癌で亡くなった時言われたそうだ。素敵な人だったんだと想像できる。
私は山岡鉄舟の書が好きだ。2年ほど前に浜松の方広寺の正面中央軒下の扁額《山奥深(じんおうざん)》を見たとき感動したが、調べたら鉄舟の字だった。膠液で溶いた胡粉で書かれた文字。山林火災で方広寺の伽藍の多くが焼失したとき沢山の書を書いて費用を捻出して応援し、しかも再建した本堂の開堂時に掲げた文字だ。力強い美しさだった。人から頼まれれば断らずに書いて鉄舟の書は一説では100万枚あるとの事だった。
日坂観光ボランティアの鈴木克美さんが建物の中で「日坂馬子唄」を歌ってくれた。お父さんが良く歌っていたので、耳で覚えてしまったとの事だった。
小夜の中山 疲れもしたがナ
登りゃうれしや 飴の餅
馬がもの言うた 峠の茶屋でナ
おさんどんなら ただ乗せる
江戸時代の風情を感じる歌だった。
山岡鉄舟の書に出会う
<東には東海道の難所「小夜の中山」が控え、西には「事任八幡宮」が鎮座する小さな宿場町でした>と書かれたお茶のペットボトルを、昔からある小夜の中山の茶店で買った。世界農業遺産茶草場農法の里東海道の25番目の宿場町日坂でつくられているお茶だった。お茶のペットボトルの種類はたくさんあるが、茶草場の濃いお茶は初めて飲んだ。
小雨の中目的地の本陣跡に向かって走った。今まで日坂宿を通ることが無かったことが不思議。でも国1がまだ旧道を走っていた頃も日坂はほんのちょっぴり道から外れていたから通っていないのだ。宿場としては坂下(三重県鈴鹿)、由比に次ぐ小さな宿場。
萬屋・藤文・かえで屋・問屋場跡・川坂屋などの中で印象深かったのは、川坂屋。宿場の中で1番西にあった旅籠屋で、身分の高い武士や公家などが宿泊した格の高い脇本陣格の建物だった。そしてそこで山岡鉄舟(1836~1888)の書を見つけた。襖に貼ってあり、バランスも良く味のある書だった。心が釘付けになった。明治初頭に一旦廃業後も要人に宿を提供したことから書が残っていたのかと思った。7言律詩だったが読み取ることは出来なかった。幕末の3舟(勝海舟・高橋泥舟・山岡鉄舟)の1人で明治維新後、徳川家達に従い駿府で活躍した人の書だ。牧の原のお茶の助言もしていた。「鉄舟のいない世の中は生きるに値しない」と胃癌で亡くなった時言われたそうだ。素敵な人だったんだと想像できる。
私は山岡鉄舟の書が好きだ。2年ほど前に浜松の方広寺の正面中央軒下の扁額《山奥深(じんおうざん)》を見たとき感動したが、調べたら鉄舟の字だった。膠液で溶いた胡粉で書かれた文字。山林火災で方広寺の伽藍の多くが焼失したとき沢山の書を書いて費用を捻出して応援し、しかも再建した本堂の開堂時に掲げた文字だ。力強い美しさだった。人から頼まれれば断らずに書いて鉄舟の書は一説では100万枚あるとの事だった。
日坂観光ボランティアの鈴木克美さんが建物の中で「日坂馬子唄」を歌ってくれた。お父さんが良く歌っていたので、耳で覚えてしまったとの事だった。
小夜の中山 疲れもしたがナ
登りゃうれしや 飴の餅
馬がもの言うた 峠の茶屋でナ
おさんどんなら ただ乗せる
江戸時代の風情を感じる歌だった。
会員様から
ダンボール織り機で富士山
毎年の展覧会準備の中で、作品制作は勿論だが、会場をどう運営するのかも大切だ。今年は8月に3ヶ所の展示会があった。それぞれの環境で、対象も含め色々試して今回はワークショップができる作品づくりにたどり着いた。《ダンボール織り機で富士山を作ってみよう》である。
18年ほど前は、工房から織り機を会場に運び無料で親子体験の企画を数年続けた。「お話にでてくる鶴の恩返しの織り機と一緒。体験してみる?」と声をかけるとお母さんたちも積極的で、子供にやらせたがった。子供達は物語の絵本でしか知らない織り機に初めは恐る恐るだったのに、体験は楽しく喜んでくれた。
その後、別のワークショップを色々試した。難しかったのは3年前の《原始機を使ってもじり織りで織ってみよう》のワークショップで、これは私も東京まで習いに行き「志太裂織り・織り倶楽部」のメンバーの手助けも借りて開いたこともある。全国紙の体験案内に載ったところ、京都から体験したいと申し込みがあり新幹線で駆けつけてくれた人にびっくりした企画になった。そして今回はダンボール織り機だ。
①きれいなお菓子の空き箱を見つける。
②上箱を額縁にして中央を切り貫く。
③箱の大きさに合わせて切ったダンボールに糸を巻く。
④用意した布で織り機の理論で織る。
⑤作品を箱の中に入れて飾る。
実際は体験してもらうまでの準備がとても大変だった。体験時間の関係もある。でもいろんな人から空箱を提供してもらったり、大きさ・色が異なる箱を生かして作品をつくるアイディアを考えるのが楽しかった。
体験当日に3人兄弟の小学生がいた。3人とも違う箱でそれぞれ個性的な作品が出来上がった。感想発表では小学1年の男の子が「この箱を選んでよかった」と嬉しそうに抱えてくれたのを見たとき、感動してしまった。
体験の人の中に学童保育の担当者や障害の施設の担当の人がいた。覚えて子供達に教えてあげたいというので、私が苦労して考えた裏技というかポイントをすべて教えてあげた。楽しく作っている子供達の様子を想像して幸せだった。
登呂遺跡に織り機の破片が出土している。いつかダンボール織りのワークシヨップを登呂遺跡でやってみたいと思った。実現できるといいなー・・。
毎年の展覧会準備の中で、作品制作は勿論だが、会場をどう運営するのかも大切だ。今年は8月に3ヶ所の展示会があった。それぞれの環境で、対象も含め色々試して今回はワークショップができる作品づくりにたどり着いた。《ダンボール織り機で富士山を作ってみよう》である。
18年ほど前は、工房から織り機を会場に運び無料で親子体験の企画を数年続けた。「お話にでてくる鶴の恩返しの織り機と一緒。体験してみる?」と声をかけるとお母さんたちも積極的で、子供にやらせたがった。子供達は物語の絵本でしか知らない織り機に初めは恐る恐るだったのに、体験は楽しく喜んでくれた。
その後、別のワークショップを色々試した。難しかったのは3年前の《原始機を使ってもじり織りで織ってみよう》のワークショップで、これは私も東京まで習いに行き「志太裂織り・織り倶楽部」のメンバーの手助けも借りて開いたこともある。全国紙の体験案内に載ったところ、京都から体験したいと申し込みがあり新幹線で駆けつけてくれた人にびっくりした企画になった。そして今回はダンボール織り機だ。
①きれいなお菓子の空き箱を見つける。
②上箱を額縁にして中央を切り貫く。
③箱の大きさに合わせて切ったダンボールに糸を巻く。
④用意した布で織り機の理論で織る。
⑤作品を箱の中に入れて飾る。
実際は体験してもらうまでの準備がとても大変だった。体験時間の関係もある。でもいろんな人から空箱を提供してもらったり、大きさ・色が異なる箱を生かして作品をつくるアイディアを考えるのが楽しかった。
体験当日に3人兄弟の小学生がいた。3人とも違う箱でそれぞれ個性的な作品が出来上がった。感想発表では小学1年の男の子が「この箱を選んでよかった」と嬉しそうに抱えてくれたのを見たとき、感動してしまった。
体験の人の中に学童保育の担当者や障害の施設の担当の人がいた。覚えて子供達に教えてあげたいというので、私が苦労して考えた裏技というかポイントをすべて教えてあげた。楽しく作っている子供達の様子を想像して幸せだった。
登呂遺跡に織り機の破片が出土している。いつかダンボール織りのワークシヨップを登呂遺跡でやってみたいと思った。実現できるといいなー・・。
会員様から
林叟院 と スティーブ・ジョブズ
1498年に明応の大地震があり、焼津の『林叟院記録』に・・「而溺死者大凡二萬六千人也 林叟之旧地忽変巨海也」と記されているお寺を訪ねた。今騒がれている地震。過去の南海トラフ巨大地震に類似の地震を察知した高僧の助言で、焼津の海の傍にあった寺を今の坂本に移し天災から助かったお寺である。小雨の中林叟院に向かう道には美しく咲くアジサイの色彩に溢れていた。有名な長谷川平蔵(池波正太郎鬼平犯科帳で知られているが、実在人物は江戸幕府の役人で、火付盗賊改役)の祖先の法栄長者(長谷川政宣)の墓があり、この林叟院はその当時法栄長者が建てたものだ。
本堂では法事が行われていたので、左横の池の見える部屋にいると、鈴木抱一住職がすーっと入ってきて話し始めた。
「昨日、岡山県禅寺洞松寺で座禅の仕事をして帰ってきたばかり。今は坊さんの7割が外国人。15分の話をすると英語で通訳、それからフランス語で。朝は皆おかゆを頂いて・・」
私が抱一住職と知り合ったのは、もう30年以上前。寺の中庭で「土の虫」の会の陶芸家たちが作品を売っていた頃。陶芸家のプロの知り合いがたくさんできたのはこの時で、人気のある会だった。
「古い文字で佛という言葉はめざめるという意味ですが、仏教が日本に入ってくるとき、音としての佛=ブッダが入ってきたんです。めざめる、悟るという意味です。座禅堂で大きな宇宙と私たちは離ればなれではないと感じてほしい。自分は27歳のときから住職で52年経ちました。でももうちょっとやらしてもらいます。」
住職のお父さんは、サンフランシスコで禅を広めた鈴木俊隆(1905~1971)氏。27歳でタイム誌の表紙を飾ったスティーブ・ジョブズにも影響を与えた人で・・56歳でジョブは死んじゃったけど・・禅を学んでいたのだと話していた。瞑想をして自分探しをしたとのことだった。
帰りに植木の地中に隠れて咲くきのこのレースだけを見つけた。とても綺麗で生まれて初めて見た植物。きのことジョブズの話が心に強く残った林叟院だった。

1498年に明応の大地震があり、焼津の『林叟院記録』に・・「而溺死者大凡二萬六千人也 林叟之旧地忽変巨海也」と記されているお寺を訪ねた。今騒がれている地震。過去の南海トラフ巨大地震に類似の地震を察知した高僧の助言で、焼津の海の傍にあった寺を今の坂本に移し天災から助かったお寺である。小雨の中林叟院に向かう道には美しく咲くアジサイの色彩に溢れていた。有名な長谷川平蔵(池波正太郎鬼平犯科帳で知られているが、実在人物は江戸幕府の役人で、火付盗賊改役)の祖先の法栄長者(長谷川政宣)の墓があり、この林叟院はその当時法栄長者が建てたものだ。
本堂では法事が行われていたので、左横の池の見える部屋にいると、鈴木抱一住職がすーっと入ってきて話し始めた。
「昨日、岡山県禅寺洞松寺で座禅の仕事をして帰ってきたばかり。今は坊さんの7割が外国人。15分の話をすると英語で通訳、それからフランス語で。朝は皆おかゆを頂いて・・」
私が抱一住職と知り合ったのは、もう30年以上前。寺の中庭で「土の虫」の会の陶芸家たちが作品を売っていた頃。陶芸家のプロの知り合いがたくさんできたのはこの時で、人気のある会だった。
「古い文字で佛という言葉はめざめるという意味ですが、仏教が日本に入ってくるとき、音としての佛=ブッダが入ってきたんです。めざめる、悟るという意味です。座禅堂で大きな宇宙と私たちは離ればなれではないと感じてほしい。自分は27歳のときから住職で52年経ちました。でももうちょっとやらしてもらいます。」
住職のお父さんは、サンフランシスコで禅を広めた鈴木俊隆(1905~1971)氏。27歳でタイム誌の表紙を飾ったスティーブ・ジョブズにも影響を与えた人で・・56歳でジョブは死んじゃったけど・・禅を学んでいたのだと話していた。瞑想をして自分探しをしたとのことだった。
帰りに植木の地中に隠れて咲くきのこのレースだけを見つけた。とても綺麗で生まれて初めて見た植物。きのことジョブズの話が心に強く残った林叟院だった。
会員様から
木喰仏(もくじきぶつ)
生誕300年

木喰さんが生まれたのは1718年。だから生誕300年。全国を行脚しながら数多くの仏像を残したお坊さんで710体が確認されている。
そして私の住む岡部にもやってきていた。83才のときだ。高草山のふもとで無住寺院や付属の建物の中で夜間に仏像を彫った。寛政12年(1800)6月13日から8月13日までの2ヶ月間で13体つくり、11体が現存している。岡部の町にその大切な木喰仏が残されていることは誇りだ。
もともと大正13年頃柳宗悦が木喰仏を偶然見つけ感動していなかったら、今のように残ってはいないと思う。そして昭和40年ころ文化的価値が認められた。柳宗悦氏が「太子像の中でも傑作」と褒めた聖徳太子像が光泰寺にある。最近では大きなケースの中に入れられ、触れないようになっている。20年程前には、触って背面の文字も見ることができた。墨で制作年月日が大きく書いてあり、結果として行脚の道が理解できたのだ。
木喰さんは山梨県身延町生まれているのに、旅日記をつけていた。
「木喰の里微笑館」に「四国堂心願鏡」「納経帳」「南無阿弥陀仏国々御宿帳」の古文書や仏像が残っている。その中に 六月ヨリ ヲカべ イナ川やの文字を見つけたときは嬉しかった。
光泰寺・十輪寺・梅林院に仏像がある。

生誕300年
木喰さんが生まれたのは1718年。だから生誕300年。全国を行脚しながら数多くの仏像を残したお坊さんで710体が確認されている。
そして私の住む岡部にもやってきていた。83才のときだ。高草山のふもとで無住寺院や付属の建物の中で夜間に仏像を彫った。寛政12年(1800)6月13日から8月13日までの2ヶ月間で13体つくり、11体が現存している。岡部の町にその大切な木喰仏が残されていることは誇りだ。
もともと大正13年頃柳宗悦が木喰仏を偶然見つけ感動していなかったら、今のように残ってはいないと思う。そして昭和40年ころ文化的価値が認められた。柳宗悦氏が「太子像の中でも傑作」と褒めた聖徳太子像が光泰寺にある。最近では大きなケースの中に入れられ、触れないようになっている。20年程前には、触って背面の文字も見ることができた。墨で制作年月日が大きく書いてあり、結果として行脚の道が理解できたのだ。
木喰さんは山梨県身延町生まれているのに、旅日記をつけていた。
「木喰の里微笑館」に「四国堂心願鏡」「納経帳」「南無阿弥陀仏国々御宿帳」の古文書や仏像が残っている。その中に 六月ヨリ ヲカべ イナ川やの文字を見つけたときは嬉しかった。
光泰寺・十輪寺・梅林院に仏像がある。
会員様から
大人の修学旅行
中学時代の修学旅行で訪ねて以来、何十年ぶりだろう。あの頃は国宝だと言ってもまだ歴史に裏打ちされた知識も少ししか持たず、皆でわいわいと先生に連れられて回った記憶しかなかった。あの頃は「玉虫の厨子」と「百済観音」の2つに興味があった。玉虫を装飾に使っていることと、百済という地名の異国の香りだった。
法隆寺にたどり着き、百済観音に対峙した。記憶の中の作品はあんなに大きく感じていたのに、今回は小さく感じて不思議だった。中学生の私は見惚れて立ち止まった。ふと気がついたときにはまわりに学校の仲間が誰もいなくて焦ったことを思い出す。外に向けて走りドキドキして建物から出ると皆並んでいた。列に加わり、間に合ってほっとしたことが思い出される。玉虫は直接捕まえたことがあった虫で、それをどんなふうに飾りにしているのだろうと感心があった。昔はまだ家にカミキリムシなども電灯の光を求めてやってくることがあり、その中に玉虫もいた。そのつやつやとしている緑の美しさを飾りに使っている。今回はその玉虫の羽も少なく多分剥げ落ちちゃって地味に感じた。玉虫厨子は推古天皇の愛用品で仏像を安置するための厨子。そこに玉虫の光る羽で装飾してあったのだ。生きてきた分少しは知識も増えたが、感動はとっても少なくなっていた。大人の修学旅行はそんなことを確認した旅行だった。
玉虫といえば2011年に日韓合作ドキュメンタリー映画「海峡をつなぐ光」という映画製作に協力した『玉虫』の関係者がいた。地元の岡部公民館大ホールでの映画鑑賞があり応援も兼ねて誘われた。会場でのご挨拶で玉虫の飼育に成功した芦沢七郎さん(現在80代)のことを知った。『玉虫を飼育できる』と知ったときは吃驚した。「博物館に玉虫の育て方を聞いても、分からないと言われたので、自分で観察して試行錯誤の末、飼育に成功しました」と語っていた。知らないことに興味を持って自分で観察・飼育に成功させた人生の生き様は脱帽だ。自分の人生でそんな風に突き進む生き様は無かったなーと反省の様な意識があった。エノキの木が餌だと言っていた。二ヶ月位生きているけど、その後は美しい羽を加工して装飾品を作っているらしい。
多分私の中では玉虫は宝石みたいな扱いのイメージが強いのかもしれない。玉虫厨子の装飾がたとえ光を失っていても、宝物なのだ。玉虫を装飾に使おうと思った昔の人の心を思った。

中学時代の修学旅行で訪ねて以来、何十年ぶりだろう。あの頃は国宝だと言ってもまだ歴史に裏打ちされた知識も少ししか持たず、皆でわいわいと先生に連れられて回った記憶しかなかった。あの頃は「玉虫の厨子」と「百済観音」の2つに興味があった。玉虫を装飾に使っていることと、百済という地名の異国の香りだった。
法隆寺にたどり着き、百済観音に対峙した。記憶の中の作品はあんなに大きく感じていたのに、今回は小さく感じて不思議だった。中学生の私は見惚れて立ち止まった。ふと気がついたときにはまわりに学校の仲間が誰もいなくて焦ったことを思い出す。外に向けて走りドキドキして建物から出ると皆並んでいた。列に加わり、間に合ってほっとしたことが思い出される。玉虫は直接捕まえたことがあった虫で、それをどんなふうに飾りにしているのだろうと感心があった。昔はまだ家にカミキリムシなども電灯の光を求めてやってくることがあり、その中に玉虫もいた。そのつやつやとしている緑の美しさを飾りに使っている。今回はその玉虫の羽も少なく多分剥げ落ちちゃって地味に感じた。玉虫厨子は推古天皇の愛用品で仏像を安置するための厨子。そこに玉虫の光る羽で装飾してあったのだ。生きてきた分少しは知識も増えたが、感動はとっても少なくなっていた。大人の修学旅行はそんなことを確認した旅行だった。
玉虫といえば2011年に日韓合作ドキュメンタリー映画「海峡をつなぐ光」という映画製作に協力した『玉虫』の関係者がいた。地元の岡部公民館大ホールでの映画鑑賞があり応援も兼ねて誘われた。会場でのご挨拶で玉虫の飼育に成功した芦沢七郎さん(現在80代)のことを知った。『玉虫を飼育できる』と知ったときは吃驚した。「博物館に玉虫の育て方を聞いても、分からないと言われたので、自分で観察して試行錯誤の末、飼育に成功しました」と語っていた。知らないことに興味を持って自分で観察・飼育に成功させた人生の生き様は脱帽だ。自分の人生でそんな風に突き進む生き様は無かったなーと反省の様な意識があった。エノキの木が餌だと言っていた。二ヶ月位生きているけど、その後は美しい羽を加工して装飾品を作っているらしい。
多分私の中では玉虫は宝石みたいな扱いのイメージが強いのかもしれない。玉虫厨子の装飾がたとえ光を失っていても、宝物なのだ。玉虫を装飾に使おうと思った昔の人の心を思った。
会員様から
秋野不矩さん大好き
今までに出会った女の人でとっても心に残っている人がいる。その人は秋野不矩さん。お会いしたのは今から25年前のこと。子育てに追われバタバタ暮らしている時に彼女に会って話をすることが出来たことが、その後の私の人生の心の支えにもなったり、エネルギーの元になったりした。2001年に亡くなってしまったけど、天竜二俣で静岡県出身ということも誇りである。
丁度第25回日本芸術大賞を受賞した時、お祝いのパーティーを静岡でもした。その時声を掛けていただき参加させていただいたことがある。
「絵描きとして生きてきて、ためすんです」という言葉の意味も25年前には理解できなかった。今は生きてきて、ためすその内包するエネルギーを私も私なりに保ちたいと思うようになっている。
何という力強さなんだろうと河を渡る水牛の大作『渡河』の作品。氾濫するダヤ河で滔々たる流れをくだる水牛の群れ。143.0× 365.0㌢のスケールだ。雄大な自然把握とみずみずしい色彩。作品から受けるパワーに圧倒される。
「画家は自分の色を出すために色に苦心しているのですが、たとえば『廻廊』ではインドの光の強さを表現するのに光の部分に金箔を5枚位貼って表わしたりしました。作品を描くときには、単に場所を描くということではなく、光と影の中で、インドの深い感じ、渇いた感じを表現しようとしました。心のメモをのせるということかもしれない・・」と語った言葉も忘れられない。
お会いした浜松市美術館で『ナヴァグラハ』が展示されていた。サンスクリットでは9つの惑星・・神様なのだが、竹紙に黒で描いてあり、インパクトがあった。竹紙は竹を叩き柔らかくし、和紙を漉くようにつくった紙である。インドでは人々が神の像を描くことがすなわち祈り。竹紙に描いた力強い線がそのまま祈りだとしてもボコボコと盛り上がって出来ている竹紙と共鳴していた。「竹紙は水上勉氏の工房で漉いてもらった」と聞いて、その後水上勉氏の工房『若州一滴文庫』を福井県大飯郡おおい町まで訪ねて行ったことも懐かしい思い出になっている。その後私は地元で朝比奈和紙保存会の人達と『和紙を織る』体験のワークショップを企画したりもした。私なりに色々試していたんだと秋野不矩さんとの出会いを感謝した。

今までに出会った女の人でとっても心に残っている人がいる。その人は秋野不矩さん。お会いしたのは今から25年前のこと。子育てに追われバタバタ暮らしている時に彼女に会って話をすることが出来たことが、その後の私の人生の心の支えにもなったり、エネルギーの元になったりした。2001年に亡くなってしまったけど、天竜二俣で静岡県出身ということも誇りである。
丁度第25回日本芸術大賞を受賞した時、お祝いのパーティーを静岡でもした。その時声を掛けていただき参加させていただいたことがある。
「絵描きとして生きてきて、ためすんです」という言葉の意味も25年前には理解できなかった。今は生きてきて、ためすその内包するエネルギーを私も私なりに保ちたいと思うようになっている。
何という力強さなんだろうと河を渡る水牛の大作『渡河』の作品。氾濫するダヤ河で滔々たる流れをくだる水牛の群れ。143.0× 365.0㌢のスケールだ。雄大な自然把握とみずみずしい色彩。作品から受けるパワーに圧倒される。
「画家は自分の色を出すために色に苦心しているのですが、たとえば『廻廊』ではインドの光の強さを表現するのに光の部分に金箔を5枚位貼って表わしたりしました。作品を描くときには、単に場所を描くということではなく、光と影の中で、インドの深い感じ、渇いた感じを表現しようとしました。心のメモをのせるということかもしれない・・」と語った言葉も忘れられない。
お会いした浜松市美術館で『ナヴァグラハ』が展示されていた。サンスクリットでは9つの惑星・・神様なのだが、竹紙に黒で描いてあり、インパクトがあった。竹紙は竹を叩き柔らかくし、和紙を漉くようにつくった紙である。インドでは人々が神の像を描くことがすなわち祈り。竹紙に描いた力強い線がそのまま祈りだとしてもボコボコと盛り上がって出来ている竹紙と共鳴していた。「竹紙は水上勉氏の工房で漉いてもらった」と聞いて、その後水上勉氏の工房『若州一滴文庫』を福井県大飯郡おおい町まで訪ねて行ったことも懐かしい思い出になっている。その後私は地元で朝比奈和紙保存会の人達と『和紙を織る』体験のワークショップを企画したりもした。私なりに色々試していたんだと秋野不矩さんとの出会いを感謝した。
会員様から
佐川美術館
「生誕110年 田中一村展」
日曜美術館で「田中一村」の作品を見た時衝撃を受けた。いきなりファンになった。今から34年前のことである。タイトルは「黒潮の画譜~異端の画家田中一村」きっと日本中の田中ファンが生まれた瞬間なんだろう。その後一村出身地の千葉市美術館にも作品展を観に出かけている。
独特の画風で日本のゴーギャンと言われているが、晩年の写真では痩せたおじさんの姿。お宝の番組「出張なんでも鑑定団」で今月7月に奄美からの放送があった。田中一村氏が染色工として歩いていた姿を見かけていた人の登場だった。当時は学生だと言っていた。鉛筆で描いた親戚の夫婦の肖像画をお宝として出したのだ。丁寧に描いてありA4位で大きくなかった。会場舞台では一村のトレードマークになったステテコ姿で誰かが歩いていた。会場には笑いが起きていたが、温かみのある笑いで、リスペクトされている様子が伝わった。
箱根にある岡田美術館もやはり「初公開 田中一村の絵画―奄美を愛した孤高の画家」で展覧会をやっている。・白花と赤翡翠 ・熱帯魚三枚 ・あじさい など。同時期での展覧会。一村人気は凄い。
3年前佐川美術館を初めて訪れたときに水を湛えた入り口の景色にびっくりしたことを思い出す。サライ7月号に佐川美術館の一村の特集が載っていたので買ってみた。・初夏の海に赤翡翠(あかしょうびん) ・菊図 個人蔵 ・蓮図 奈良県立万葉文化館蔵 ・忍冬に尾長 個人蔵(田中一村美術館寄託) ・枇榔樹の森に崑崙花 田中一村美術館蔵 ・アダンの海辺 個人蔵(千葉市美術館寄託) ・クロトンと熱帯魚 田中一村記念美術館 がとりあげられていた。静謐な画面の本物に会いたいなと思った。
暑い夏の展覧会でも入館者は多かった。毎日千人ほどの人が一村の作品に会いに来ていると知った。作品数は180点。一度にこんなに沢山の絵に会えて幸せだ。その中でやはり 初夏の海に赤翡翠 の前には人だかりが。
私は7歳の時の「菊図」が一部破れていても現存されていたことが凄いなーと思った。愛されていなければ作品が残るなんて考えられない。千葉時代の作品で「椿図」の屏風も心に残った。二曲一双で右隻にはあでやかな椿。左隻は金箔が貼ってあるだけだった。「落款が無いのでもしかしたら未完成かも・・」と学芸員は話していた。そんな作品にも出会えて嬉しかった。また「NHKでの放映が5日後に決まっていて、1.5倍の入館者数になるので、混雑前の今日来られて良かったですね」とも話していた。
「生誕110年 田中一村展」
日曜美術館で「田中一村」の作品を見た時衝撃を受けた。いきなりファンになった。今から34年前のことである。タイトルは「黒潮の画譜~異端の画家田中一村」きっと日本中の田中ファンが生まれた瞬間なんだろう。その後一村出身地の千葉市美術館にも作品展を観に出かけている。
独特の画風で日本のゴーギャンと言われているが、晩年の写真では痩せたおじさんの姿。お宝の番組「出張なんでも鑑定団」で今月7月に奄美からの放送があった。田中一村氏が染色工として歩いていた姿を見かけていた人の登場だった。当時は学生だと言っていた。鉛筆で描いた親戚の夫婦の肖像画をお宝として出したのだ。丁寧に描いてありA4位で大きくなかった。会場舞台では一村のトレードマークになったステテコ姿で誰かが歩いていた。会場には笑いが起きていたが、温かみのある笑いで、リスペクトされている様子が伝わった。
箱根にある岡田美術館もやはり「初公開 田中一村の絵画―奄美を愛した孤高の画家」で展覧会をやっている。・白花と赤翡翠 ・熱帯魚三枚 ・あじさい など。同時期での展覧会。一村人気は凄い。
3年前佐川美術館を初めて訪れたときに水を湛えた入り口の景色にびっくりしたことを思い出す。サライ7月号に佐川美術館の一村の特集が載っていたので買ってみた。・初夏の海に赤翡翠(あかしょうびん) ・菊図 個人蔵 ・蓮図 奈良県立万葉文化館蔵 ・忍冬に尾長 個人蔵(田中一村美術館寄託) ・枇榔樹の森に崑崙花 田中一村美術館蔵 ・アダンの海辺 個人蔵(千葉市美術館寄託) ・クロトンと熱帯魚 田中一村記念美術館 がとりあげられていた。静謐な画面の本物に会いたいなと思った。
暑い夏の展覧会でも入館者は多かった。毎日千人ほどの人が一村の作品に会いに来ていると知った。作品数は180点。一度にこんなに沢山の絵に会えて幸せだ。その中でやはり 初夏の海に赤翡翠 の前には人だかりが。
私は7歳の時の「菊図」が一部破れていても現存されていたことが凄いなーと思った。愛されていなければ作品が残るなんて考えられない。千葉時代の作品で「椿図」の屏風も心に残った。二曲一双で右隻にはあでやかな椿。左隻は金箔が貼ってあるだけだった。「落款が無いのでもしかしたら未完成かも・・」と学芸員は話していた。そんな作品にも出会えて嬉しかった。また「NHKでの放映が5日後に決まっていて、1.5倍の入館者数になるので、混雑前の今日来られて良かったですね」とも話していた。
会員様から
「花泥棒」・下北沢
下北沢は地名。でも私の中では聖地かも。心の!!と思う。
子供が東京に住み始めてしばらく経った頃会いに出かけた。待ち合わせの場所が下北沢だった。「花泥棒」・・ヴォルール・ドゥ・フルールという喫茶店。涙が流れた。子供は自分の人生の好きなことをやろうと親の私に夢を話している。応援している私もがんばって働いて送金している。夢を応援するのは親の喜びであるので頑張れる。涙をそっと手で拭ってベトナムコーヒーを飲んだ。美味しかった。
「花泥棒」は花盗人。今までに1度だけ花を盗んでみたいと思う誘惑にかられたことがある。季節は冬。場所は岡部町。岡部氏の本拠地で今川義元に勝利を導いた岡部左京進親綱の朝日山城跡にのぼっていく道の脇に咲いていたアジサイ。冬にも拘わらずしっかり手毬の形で残って色彩が美しかった。リーフグリーンの上にワインレッドの上書き。神様が作り出した以上の色彩だと思った。アジサイの形がそのまま残っていることも奇跡だ。家の庭では梅雨の季節が終わると自然に花は無くなってしまうのに。山の木々に囲まれることで風の強さにも守られてそのままの形が残るのだろう。そして霜にあたって耐えて生まれた色。心が吸い込まれそう。天国の弟に「見て見て!綺麗でしょ」と話しかけたあの寒い日。

下北沢は地名。でも私の中では聖地かも。心の!!と思う。
子供が東京に住み始めてしばらく経った頃会いに出かけた。待ち合わせの場所が下北沢だった。「花泥棒」・・ヴォルール・ドゥ・フルールという喫茶店。涙が流れた。子供は自分の人生の好きなことをやろうと親の私に夢を話している。応援している私もがんばって働いて送金している。夢を応援するのは親の喜びであるので頑張れる。涙をそっと手で拭ってベトナムコーヒーを飲んだ。美味しかった。
「花泥棒」は花盗人。今までに1度だけ花を盗んでみたいと思う誘惑にかられたことがある。季節は冬。場所は岡部町。岡部氏の本拠地で今川義元に勝利を導いた岡部左京進親綱の朝日山城跡にのぼっていく道の脇に咲いていたアジサイ。冬にも拘わらずしっかり手毬の形で残って色彩が美しかった。リーフグリーンの上にワインレッドの上書き。神様が作り出した以上の色彩だと思った。アジサイの形がそのまま残っていることも奇跡だ。家の庭では梅雨の季節が終わると自然に花は無くなってしまうのに。山の木々に囲まれることで風の強さにも守られてそのままの形が残るのだろう。そして霜にあたって耐えて生まれた色。心が吸い込まれそう。天国の弟に「見て見て!綺麗でしょ」と話しかけたあの寒い日。